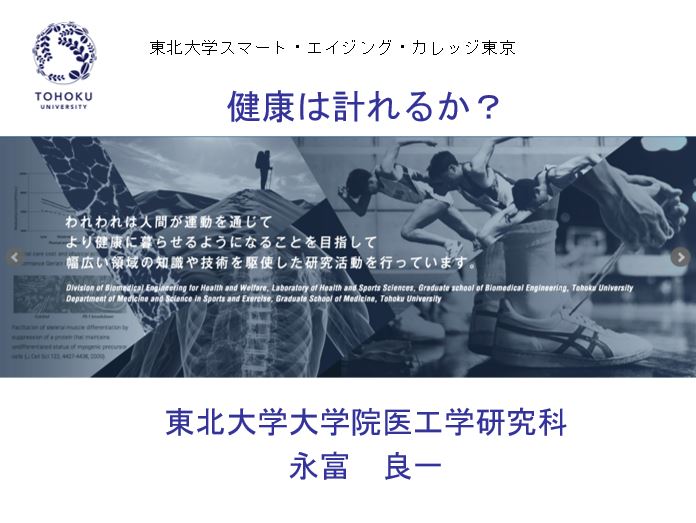SAC東京4期コースⅠ第10回月例会 参加者の声
3月20日SAC東京コースⅠ第10回月例会 参加者の声

3月20日、SAC東京4期 第10回月例会開催されました。講師は、心理学(感情・ストレス・化粧・災害)専門の阿部恒之教授。講義テーマは「美しさと加齢」でした。
講義では、「生と死に対する人の向き合い方」が歴史とともに変化してきたこと。しかしいつの時代においても誕生・成長・老い・死という過程を経ることは共通しており、その中で最も長いのが、老いの過程であるということ。しぼむ、衰える、美しさから遠ざかるという否定的な側面ばかりにとらわれる減点法のではなく、加点法の美意識もあり得るというお話の中から、老いの積極的な側面を紹介いただきました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。


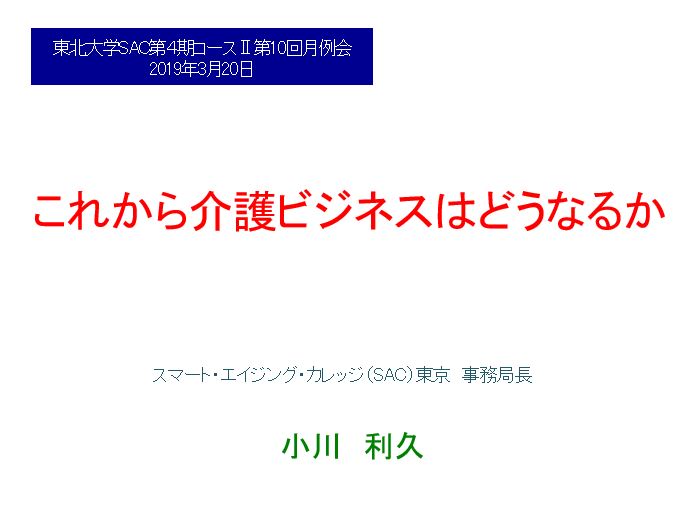
 健康増進効果をうたった商品・サービスが市場で急増している。背景には高齢化率が28%を超えた「超々高齢社会」になったことに加え、「人生100年時代」という見方が広がり、消費者の健康志向がますます強まっていることがある。
健康増進効果をうたった商品・サービスが市場で急増している。背景には高齢化率が28%を超えた「超々高齢社会」になったことに加え、「人生100年時代」という見方が広がり、消費者の健康志向がますます強まっていることがある。