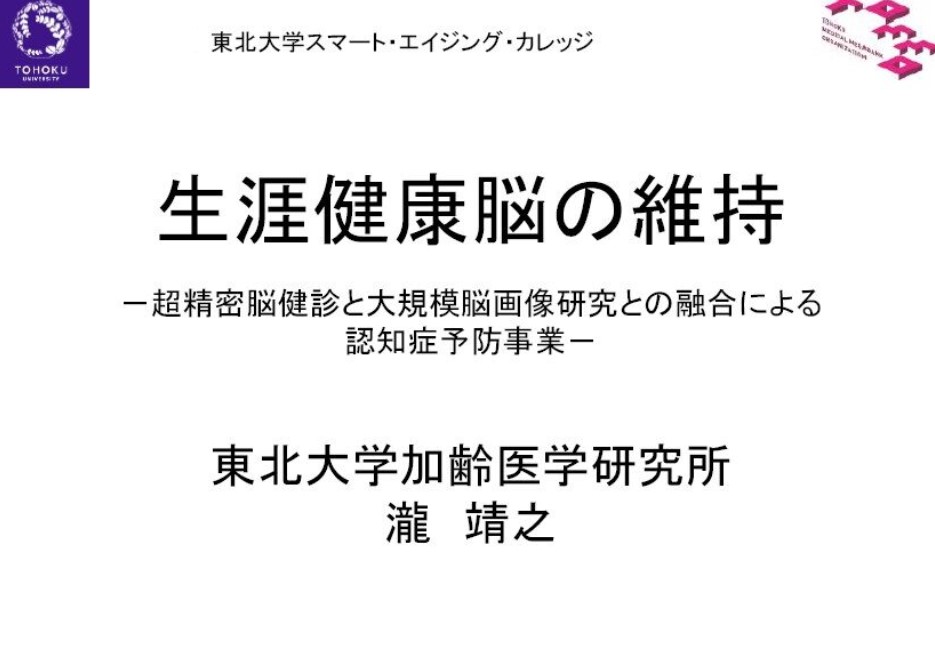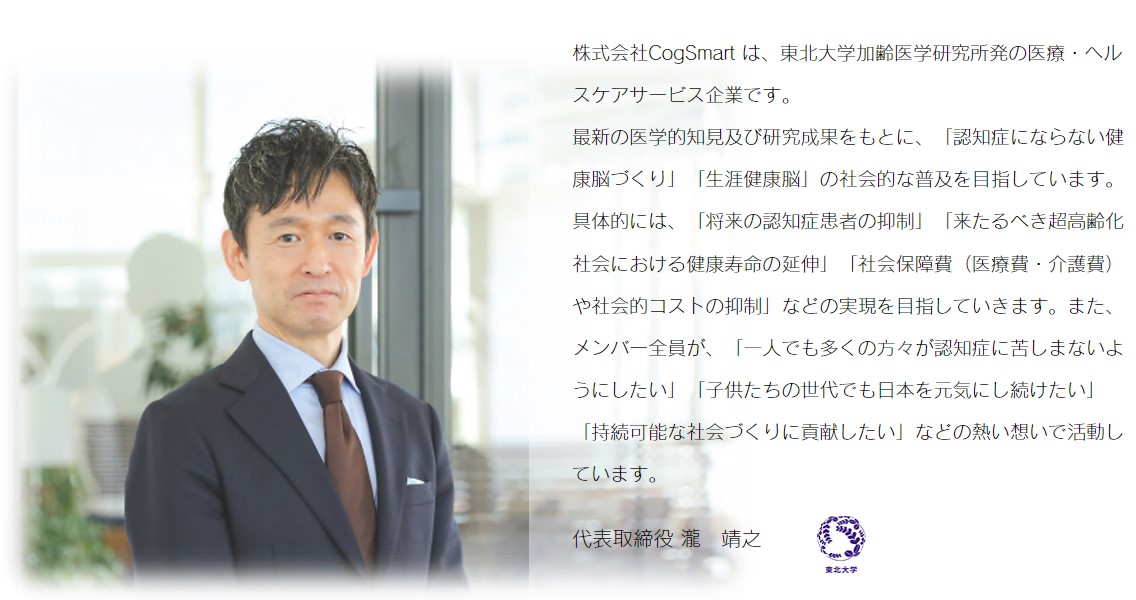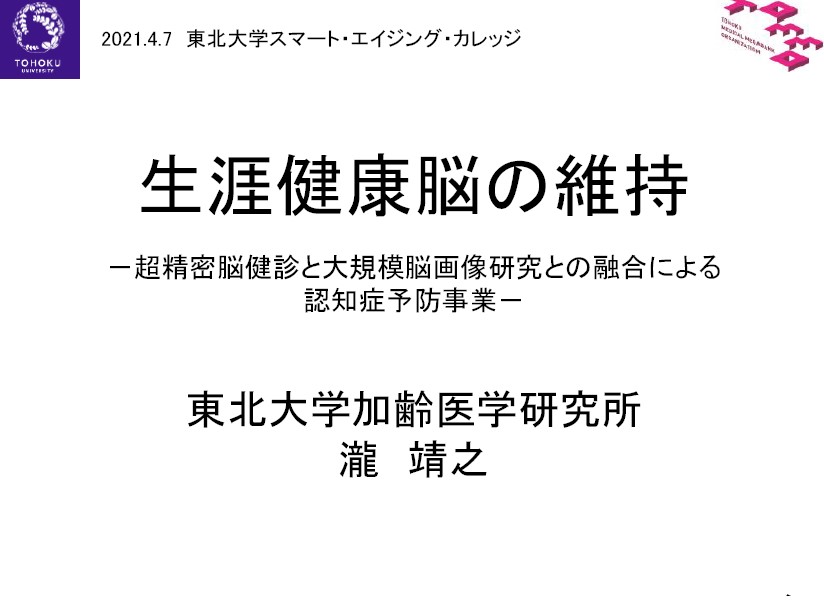瀧 靖之 教授「生涯健康脳の維持」
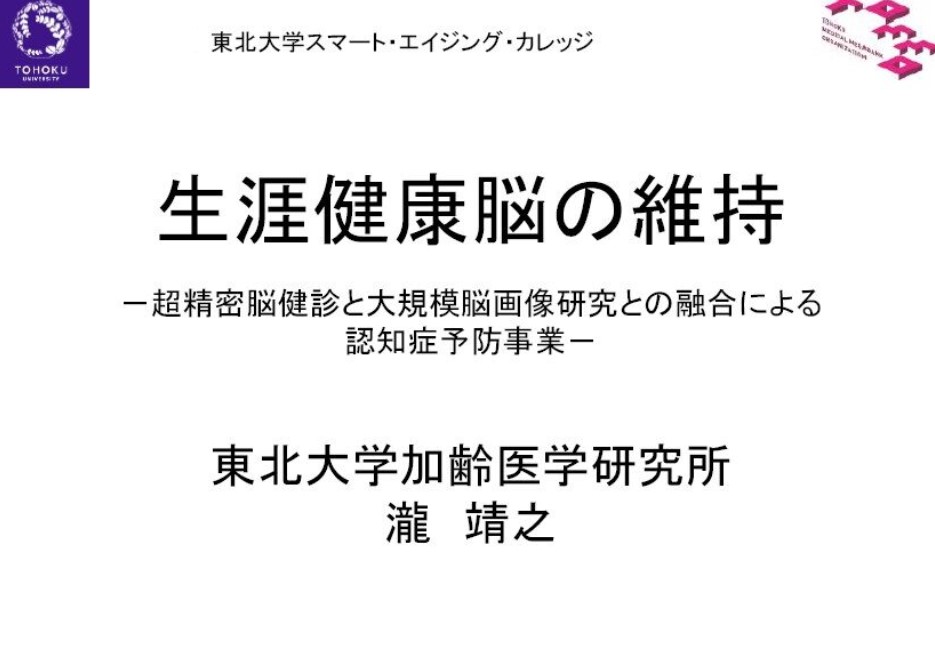
2022年6月21日、SAカレッジ22年度コースⅠ第3回月例会 質疑セッションが開催されました。
講師は、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長、瀧 靖之(たき やすゆき)教授。講義テーマは「生涯健康脳の維持」でした。
質疑セッション前の最新情報で「有酸素運動での、海馬の神経新生促進だけでなく、不安やストレス領域の扁桃体の過活動を抑えてくれるのでそれらの解消に非常にいいということが分かっている」というお話がありました。
また「高齢者のサルコペニアは社会活動が抑えらえてしまうので、いかに筋力を保つかが大事になってくる。ジムに行かなくても、1日1回からはじめて、1回から3回と少しずつ増やしていくスモールステップがすごく有効である」というお話や「趣味活動がいいのは、仕事や勉強と違い、学習の自己主体性といって自分で楽しいからやる、それが実は様々な能力の獲得にいいということがいわれている。なかなかまとまった時間はとれないので、隙間隙間にいろんなことをいれていくと、いろんなことが少しずつ習得できて、気がつけばいろんな能力が獲得てきている」「会話がなぜ大事かというと、感情を伝え合うときに言葉だけでなく、表情やしぐさ・声の欲能などのノンバーバルな部分が感情の伝達に大事である」などなど濃厚なお話がたくさんありました。
質疑セッションの最後に「東北大学の中でも当方の研究室は、様々な企業さんとかなりの産学連携をしており、運動や食分野だけでなく、例えばファッションや旅行など一見関係のないような分野もやっております。それぞれの会社さまがお持ちのソリューションやサービスは、脳科学にダイレクトにつながるところが、実は多いのです。もし興味がありましたら、エビデンスを出すなど様々なことができますので、お声がけくだされば幸いです。また大学発ベンチャーの、CogSmart(コグスマート)というところで、いろんな企業様と連携しながら、脳の健康維持というところをやっております。こちらの方でももしご興味がありましたらご連絡いただけると幸いです。私たちが動くことで、国民医療費がどんどん下がっていきますので、これこそが日本の未来にとても大事になります。ぜひ何かご一緒できる機会がありましたらお声がけくだされば幸いです」という内容で締めくくられました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
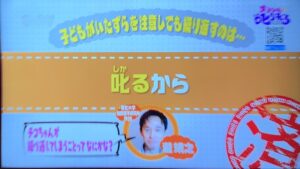 SAカレッジの講師でもあり、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長、瀧 靖之(たき やすゆき)教授が、2月3日放送 NHK総合「チコちゃんに叱られる!」に出演されていました。
SAカレッジの講師でもあり、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長、瀧 靖之(たき やすゆき)教授が、2月3日放送 NHK総合「チコちゃんに叱られる!」に出演されていました。