SAカレッジ21年度 コースⅡ 第10回月例会 参加者の声
石垣 司 准教授「ビッグデータ&ベイズモデリングで一人一人の消費者を理解する」
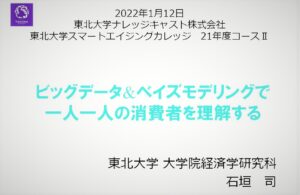 2022年1月12日、SAカレッジ21年度コースⅡ第10回月例会開催されました。講師は、経済学研究科 石垣 司(いしがき つかさ)准教授。講義テーマは「ビッグデータ&ベイズモデリングで一人一人の消費者を理解する」でした。
2022年1月12日、SAカレッジ21年度コースⅡ第10回月例会開催されました。講師は、経済学研究科 石垣 司(いしがき つかさ)准教授。講義テーマは「ビッグデータ&ベイズモデリングで一人一人の消費者を理解する」でした。
日本政府が世界に先駆けて実現すると宣言した「Society 5.0」。サイバー空間と現実空間を高度に融合させ、あらゆる人が活き活きと快適に暮らせる社会「Society 5.0」を実現するためには、「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する」ことにより、様々な分野で新たな社会的価値を創造する取り組みが求められます。そのためには、まず、もの・サービスを受容する消費者、ひいては、我々生活者を理解することが必要不可欠となります。
今回の月例会では、ビッグデータやベイズモデリングなどのデータサイエンスに立脚し、一人一人の消費者・生活者を理解するための個別化技術について紹介いただきました。具体的には、小売サービス、医療サポート、マーケティング等におけるデータ駆動型アプローチによる消費者(サービス受容者)理解の研究事例を詳しく解説していただきました。
すでに様々な分野で活用されているIoTやAI、ビッグデータなどの最新ICTですが、参加企業の皆様のビジネスにおいてどのような活用が可能なのか、それによりビジネスはどう変わるのか、皆様のビジネスの先で暮らす一人一人の消費者・生活者を理解することで、どのような価値創出が可能となるのか等々、新たなビジネスを構想するヒントが得られたのではないでしょうか。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

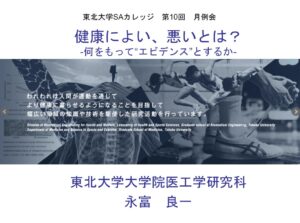
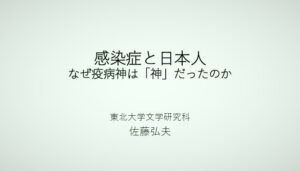
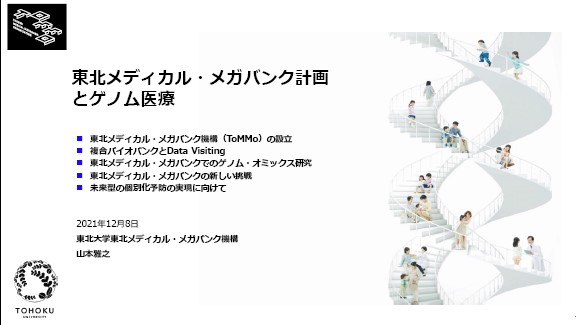 12月8日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第9回月例会開催されました。講師は、東北メディカル・メガバンク機構長、東北大学医学系研究科 教授(医化学分野) 山本 雅之(やまもと まさゆき)教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。
12月8日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第9回月例会開催されました。講師は、東北メディカル・メガバンク機構長、東北大学医学系研究科 教授(医化学分野) 山本 雅之(やまもと まさゆき)教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。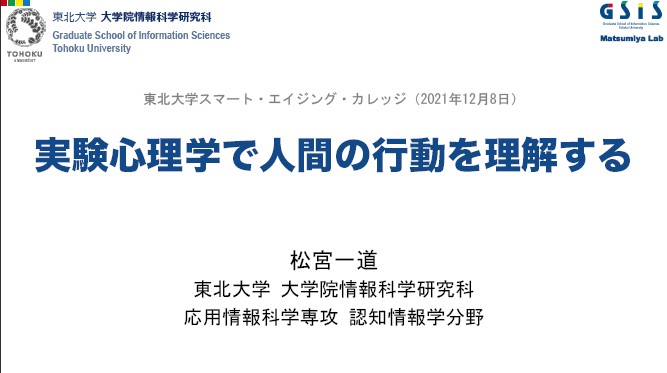 12月8日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第9回月例会開催されました。講師は、大学院情報科学研究科 応用情報科学専攻 認知情報学分野 松宮 一道(まつみや かずみち)教授。講義テーマは「実験心理学で人間の行動を理解する」でした。
12月8日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第9回月例会開催されました。講師は、大学院情報科学研究科 応用情報科学専攻 認知情報学分野 松宮 一道(まつみや かずみち)教授。講義テーマは「実験心理学で人間の行動を理解する」でした。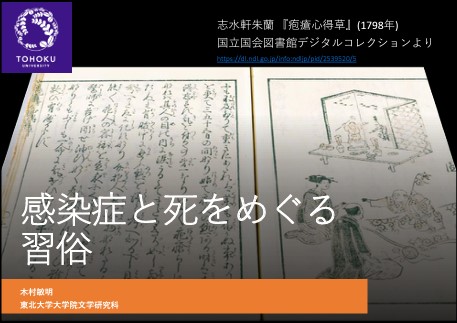 11月24日、SAカレッジ21年度コースⅢ 第8回月例会開催されました。講師は、文学研究科副研究科長、災害科学世界トップレベル学際研究拠点兼務教員 木村 敏明(きむら としあき)教授。講義テーマは「感染症と死をめぐる習俗」でした。
11月24日、SAカレッジ21年度コースⅢ 第8回月例会開催されました。講師は、文学研究科副研究科長、災害科学世界トップレベル学際研究拠点兼務教員 木村 敏明(きむら としあき)教授。講義テーマは「感染症と死をめぐる習俗」でした。