SAC東京5期コースⅡ第2回月例会 参加者の声
5月22日、SAC東京コースⅡ第2回月例会 参加者の声
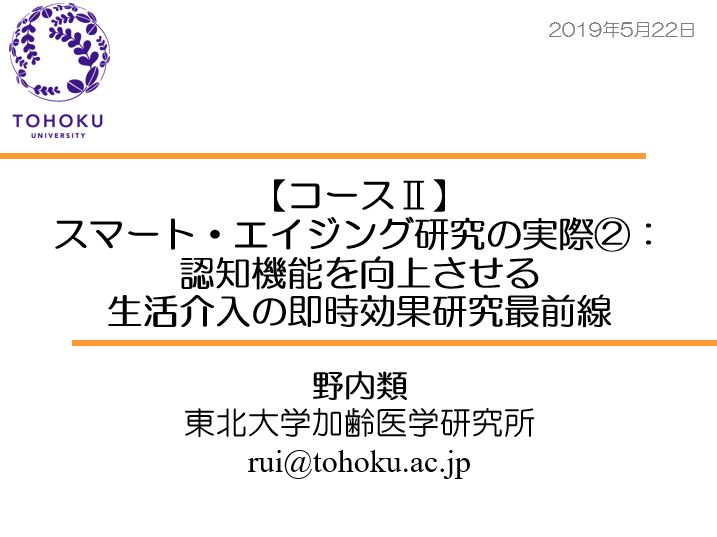
5月22日、SAC東京5期 第2回月例会開催されました。
私たちの認知機能(情報を判断したり、覚えたりする能力)は、加齢と共に低下していきます。この加齢による認知機能の低下は、高齢期の社会生活や日常生活を困難にする要因の一つとなります。
認知機能の低下は、軽度認知障害(MCI)や認知症のリスクファクターとなることから、認知機能を向上させる方法について、大きな関心が寄せられています。
本講義では、認知機能を向上させる脳トレなどの認知介入・ウォーキングなどの運動介入・食品やサプリメントを摂取する栄養介入を用いた生活介入方法についてお話しいただきました。
また、現在の研究トレンドである1回の生活介入による認知機能の向上(生活介入の即時効果)についても、最新の成果を紹介していただきました。特に、産学連携で実施された研究を中心に説明していただいたことで、今後どのような研究が社会・企業・大学側から期待されているのか、共同で研究を進めることの必要性とメリット(デメリット)について、など興味深い話が多くありました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。




