SAC東京5期コースⅡ第8回月例会 事務局レポート
人間の心と行動の不思議 —その裏側を脳機能イメージングでひも解く—

「人間の心と行動の不思議 —その裏側を脳機能イメージングでひも解く—」をテーマに加齢医学研究所 杉浦元亮教授のご登壇です。
脳の働きから人間を理解したい。人間を理解することが、加齢医学や災害に関する研究にも、ひいては社会生活やビジネスにも役立つ。杉浦教授が人間脳科学を研究する目的のお話から熱のこもった講義が始まりました。

未来の幸福な健康社会をともにデザインし、その課題と解決のアプローチを学び、
求められるビジネスの方向性と可能性を探る
2024年5月より『東北大学ヘルステックカレッジ』第2期が開講!
詳細・お申込みはこちら

「人間の心と行動の不思議 —その裏側を脳機能イメージングでひも解く—」をテーマに加齢医学研究所 杉浦元亮教授のご登壇です。
脳の働きから人間を理解したい。人間を理解することが、加齢医学や災害に関する研究にも、ひいては社会生活やビジネスにも役立つ。杉浦教授が人間脳科学を研究する目的のお話から熱のこもった講義が始まりました。
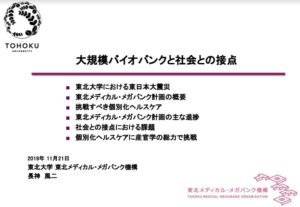
11月21日、SAC東京5期 第8回月例会開催されました。
講師は、東北大学 東北メディカル・メガバンク機構の長神風二 特任教授。講義テーマは「大規模バイオバンクと社会との接点」でした。
東北メディカル・メガバンク計画は、東北大学が東日本大震災からの復興事業の一環として進めている注目の事業です。これまでに15万人を超える地域住民から生体試料・各種情報の提供を受け、世界でも有数の大規模なバイオバンクを構築しています。
バイオバンクに蓄積された膨大な試料・情報は、構築にあたった東北大学のみならず民間企業を含む全国の研究機関で利活用が可能な仕組みが整えられています。
一方、こうした仕組み構築のためには、個人情報保護をはじめとしたセキュリティ面の対策、ヒト由来の試料・情報を利活用するための倫理面の配慮、有効に利活用されるための知的財産面のルールの整備など、社会との接点における多くの取組が必要となってきました。
今回は東北メディカル・メガバンク計画の概要を紹介すると共に、構築した大規模バイオバンクが持続可能な形で、社会で利活用され続けるための取組と今後の課題についてのお話があり、東北大学が世界に誇る未来型医療の最前線を知る絶好の機会となりました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
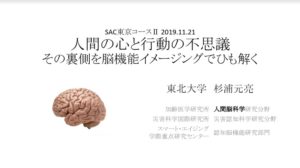
11月21日、SAC東京5期 第8回月例会開催されました。
講師は、東北大学 加齢医学研究所・災害科学国際研究所兼務の杉浦元亮 教授。講義テーマは「人間の心と行動の不思議:その裏側を脳機能イメージングでひも解く」でした。
人の心や行動は謎だらけです。しかし、最近の脳機能イメージング研究で、その裏側にある脳の仕組みがかなり見えてきました。例えば、
•人に話しかけることはなぜ難しいのでしょう?
•人はどうやって正解のない問題に答えるのでしょう?
•どうして私は英語が上手にならないのでしょう?
こうした問いへの答えと共に、人を幸せにする新しいサービス・商品のアイデアが脳の仕組みの中に見つかるかもしれません。
脳と人間行動理解に基づく新発想を製品・サービスの開発に活かしたい方、必聴の講義でした。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
国立大学法人東北大学(所在地:宮城県仙台市、総長:大野英男、以下「東北大学」)は、文部科学大臣の認可を受け、指定国立大学法人に限り出資可能な子会社にあたる、東北大学ナレッジキャスト株式会社を2019年10月9日付で設立しました。
東北大学ナレッジキャスト株式会社は、社会におけるイノベーション創出に向けて、東北大学の卓越した研究成果や研究者の深く広範な知見を活用して、企業が抱えるさまざまな事業課題の解決や技術的なブレイクスルーの実現を支援する「コンサルティング事業」と、その前段階として、企業の技術者や事業開発を担う人材に対して、東北大学の先端的な研究成果(事業シーズ)を紹介する技術解説セミナーや、さまざまな分野のイノベーティブ人材を育成し後押しする研修・講習事業を展開します。
事業の実施にあたっては、顧客ニーズに対応し、東北大学の約6000名の教職員、保有する知的財産・研究データ、研究施設・機器等のあらゆるリソースを機動的かつ柔軟に組み合わせることで、本会社にしかできない付加価値の高いサービスを展開します。
まず第一弾として、東北大学において民間企業との共同研究が急拡大しているライフサイエンス・ヘルスケア分野を対象に事業を展開します。その後、対象分野を拡げながら業容拡大を図り、5年後には売上高10億円を目指します。
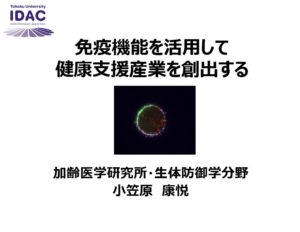 講師は、東北大学加齢医学研究所 生体防御学分野スマート・エイジング学際重点研究センター 生体防御システム研究部門長の小笠原康悦教授。講義テーマは「免疫機能を活用して健康支援産業を創出する」でした。
講師は、東北大学加齢医学研究所 生体防御学分野スマート・エイジング学際重点研究センター 生体防御システム研究部門長の小笠原康悦教授。講義テーマは「免疫機能を活用して健康支援産業を創出する」でした。
免疫のしくみを応用した産業として抗体医薬が有名で、今年度のノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑先生のがん免疫療法も一つです。しかし、抗体医薬以外にも免疫を応用した産業化の大きな可能性があります。今回の月例会はその話題でした。例えば、がん(抗原)にぴったり一致したT細胞受容体(抗体)が選択されることでがんをやっつけることができます。これが免疫の働きです。
T細胞受容体は10の18乗(100万テラバイト)という膨大な数の「レパートリー」と呼ばれる複数の形を持っています。この多様性に富む仕組みのために、私たちの体はどんな異物や病原体へも対応できます。このT細胞受容体の「レパートリー」を解析することで、生まれてから後天的に感染した病気やがんなどの刻々と変化している身体の状態を計測できるのです。この原理を用いて低コストのモニタリング商品が実用化できれば、遺伝子検査以上に高精度な健康管理商品として健康関連市場に大きなインパクトを与えられます。
最先端の免疫研究動向から事業化間近な研究成果の話が聴ける絶好の機会でした。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
 講師は、東北大学大学院文学研究科の坂井信之教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。
講師は、東北大学大学院文学研究科の坂井信之教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。
「おいしい食品」というコンセプトで商品を開発しても、消費者はそのように受け取ってくれるとは限らないという経験はありませんか?商品の設計意図と異なる受け取り方をされて予想以上に売れてしまった。しかし、原因がわからない、という経験もあるかもしれません。
今回は、これらの見込み違いについて、心理学や脳科学の観点から解説いただきました。
結論は「人はおいしさを舌で味わっているわけではない」「食品自体においしさが含まれているのではない」ということになります。消費者は商品の何に注目して購入を決定するのかも考察します。どのようにその商品を評価するのか。さらに、その商品に対する印象をどのように形成し、次の商品購入の基礎情報とするのか、などについても説明いただきました。
これらの知識は、食品に限らず、日用品やサービスにも適用でき、宣伝広告やマーケティング戦略の計画立案にも適用できるでしょう。心理学・認知神経科学に基づき、身近な話題で、購買行動に関して興味深い話を拝聴できる絶好の機会となりました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
Copyright (C) 2025東北大学&東北大学ナレッジキャスト All Rights Reserved.