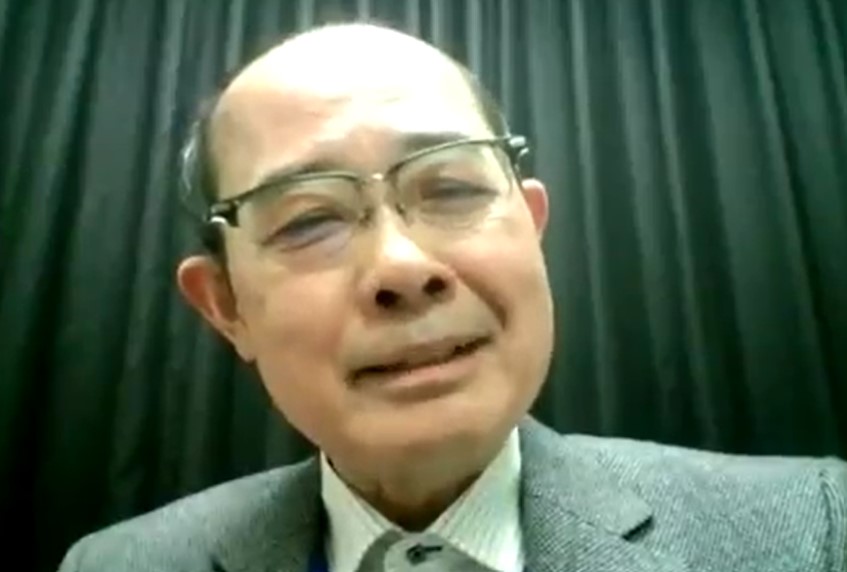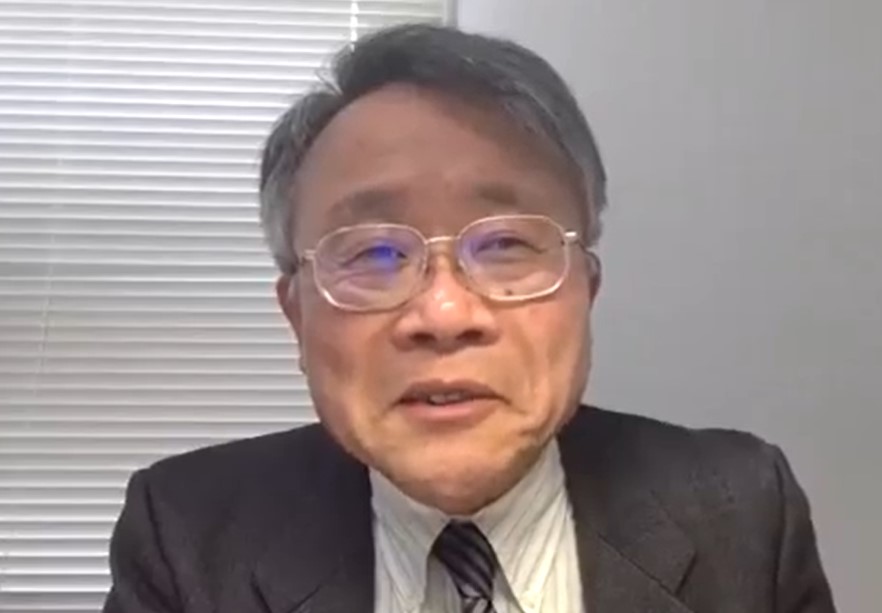SAC東京6期コースⅠ第12回月例会 事務局レポート
なぜ、今「看取り介護」なのか?―死の看取りから生ききる援助へ―

コースⅠ第12回月例会は、東北大学ナレッジキャスト株式会社、生活を支える看護師の会 会長 小林 悦子ファシリテーターによる『なぜ、今「看取り介護」なのか?―死の看取りから生ききる援助へ―』が講義テーマです。
小林講師は、介護施設での看取り介護を専門とし、核家族化した日本において「介護施設が支える新しい看取りの文化」を提唱しています。2006年から勤めた特別養護老人ホーム(東京都足立区)の看護職員として、生ききるための看取り介護の仕組みを確立しました。その後、施設長職を経て、2014年には「生活を支える看護師の会」を設立、主宰しています。現在は、セミナー等を行いながら「生ききるための看取り介護」の普及活動を行っています。


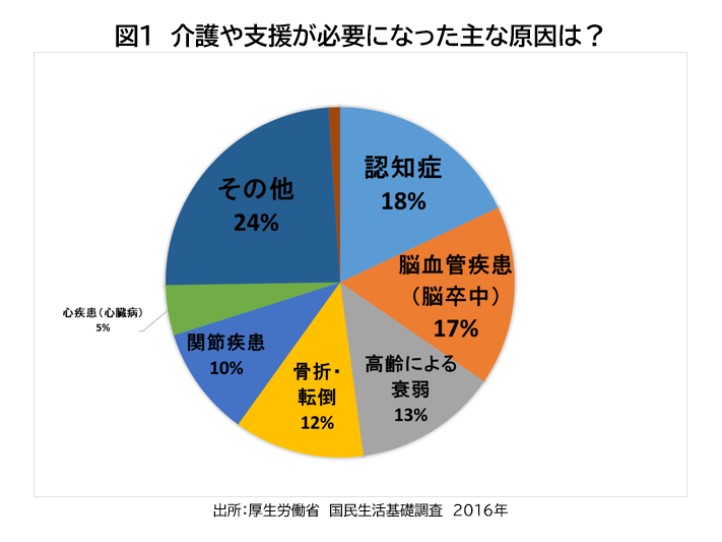 シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第7回が公開されました。
シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第7回が公開されました。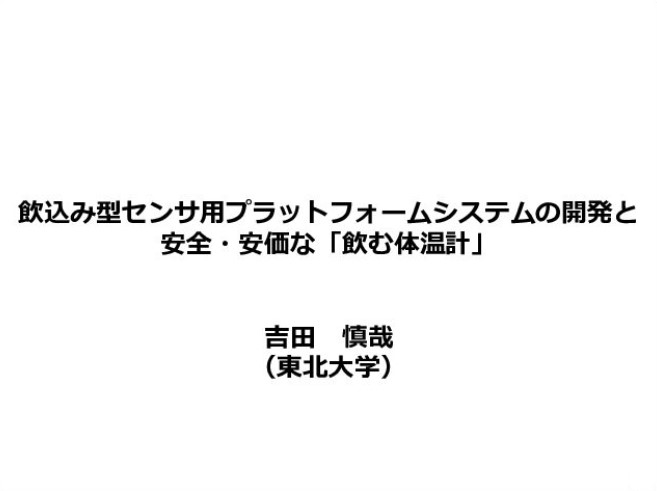 講師は大学院工学研究科 ロボティクス専攻 吉田慎哉 特任准教授。講義テーマは「飲込み型センサ用プラットフォームシステムの開発と安全・安価な「飲む体温計」でした。
講師は大学院工学研究科 ロボティクス専攻 吉田慎哉 特任准教授。講義テーマは「飲込み型センサ用プラットフォームシステムの開発と安全・安価な「飲む体温計」でした。