SAカレッジ21年度 コースⅠ第1回月例会 参加者の声
瀧 靖之 教授「生涯健康脳の維持 -超精密脳健診と大規模脳画像研究との融合による認知症予防事業-」
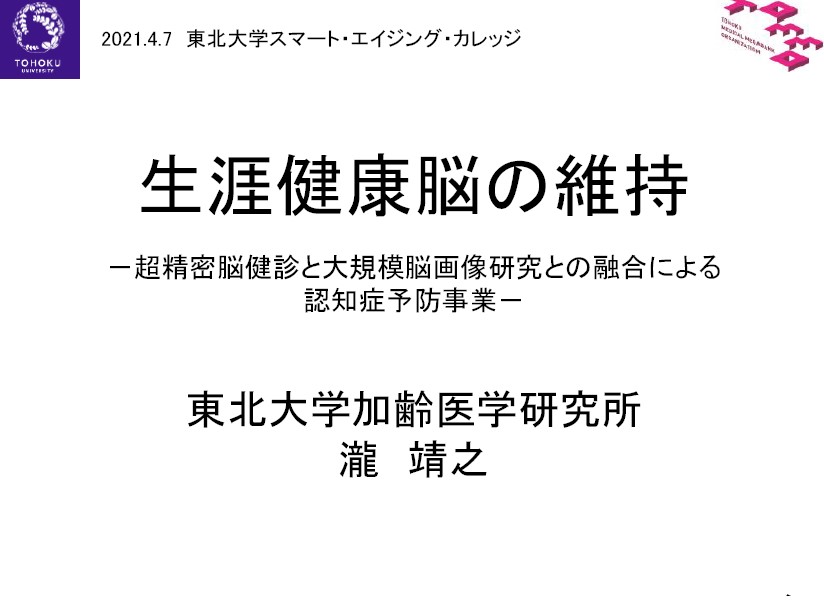 4月7日、SAカレッジ21年度 第1回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長、東北大学発ベンチャー株式会社CogSmart代表取締役・最高科学責任者(CSO)瀧 靖之(たき やすゆき)教授。講義テーマは「生涯健康脳の維持 -
4月7日、SAカレッジ21年度 第1回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長、東北大学発ベンチャー株式会社CogSmart代表取締役・最高科学責任者(CSO)瀧 靖之(たき やすゆき)教授。講義テーマは「生涯健康脳の維持 -
著書「生涯健康脳」「賢い子に育てる究極のコツ」が発売即10万部超の大ヒットとなり、気鋭の脳科学者として活躍中の瀧靖之教授がご登壇です。
認知症リスクを抑えるには脳を生涯に渡って健康に保つ事が重要ですが、東北大学には多数の方の脳のMRI計測データが集積されており、瀧教授らは生涯健康脳の維持に関わる多くの研究成果を発表してきました。
今回は、最新の脳科学の知見を基に、どのような生活習慣が脳の健やかな発達に貢献するか、どのような生活習慣が健康な脳や認知力の維持に影響を与え、認知症のリスクを下げるかをお話しいただきました。
更に、これらの知見に基づく、生涯健康脳に関する種々のサービス、商品事業化の展望もお話しいただきました。認知症予防に向けて何が重要かを包括的に理解する絶好の内容でした。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。


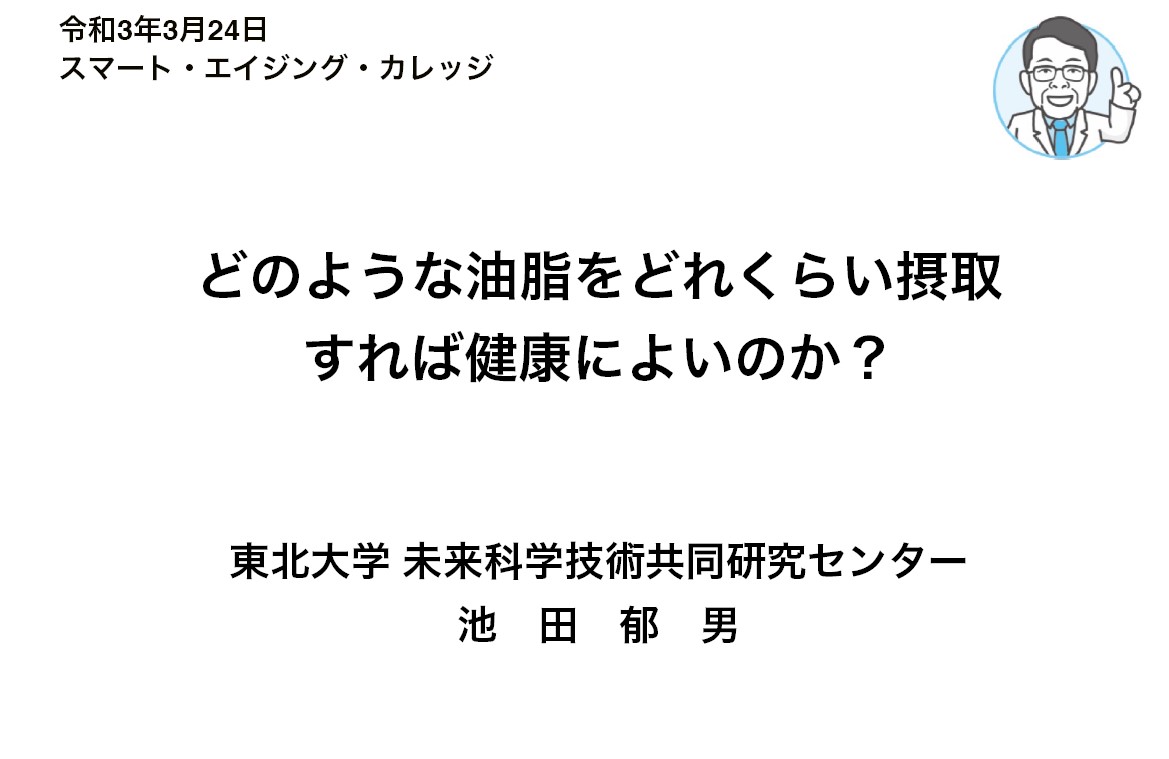 3月24日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は未来科学技術共同研究センター 池田 郁男(いけだ いくお)教授。講義テーマは「どのような油脂をどれくらい摂取すれば健康によいのか?」でした。
3月24日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は未来科学技術共同研究センター 池田 郁男(いけだ いくお)教授。講義テーマは「どのような油脂をどれくらい摂取すれば健康によいのか?」でした。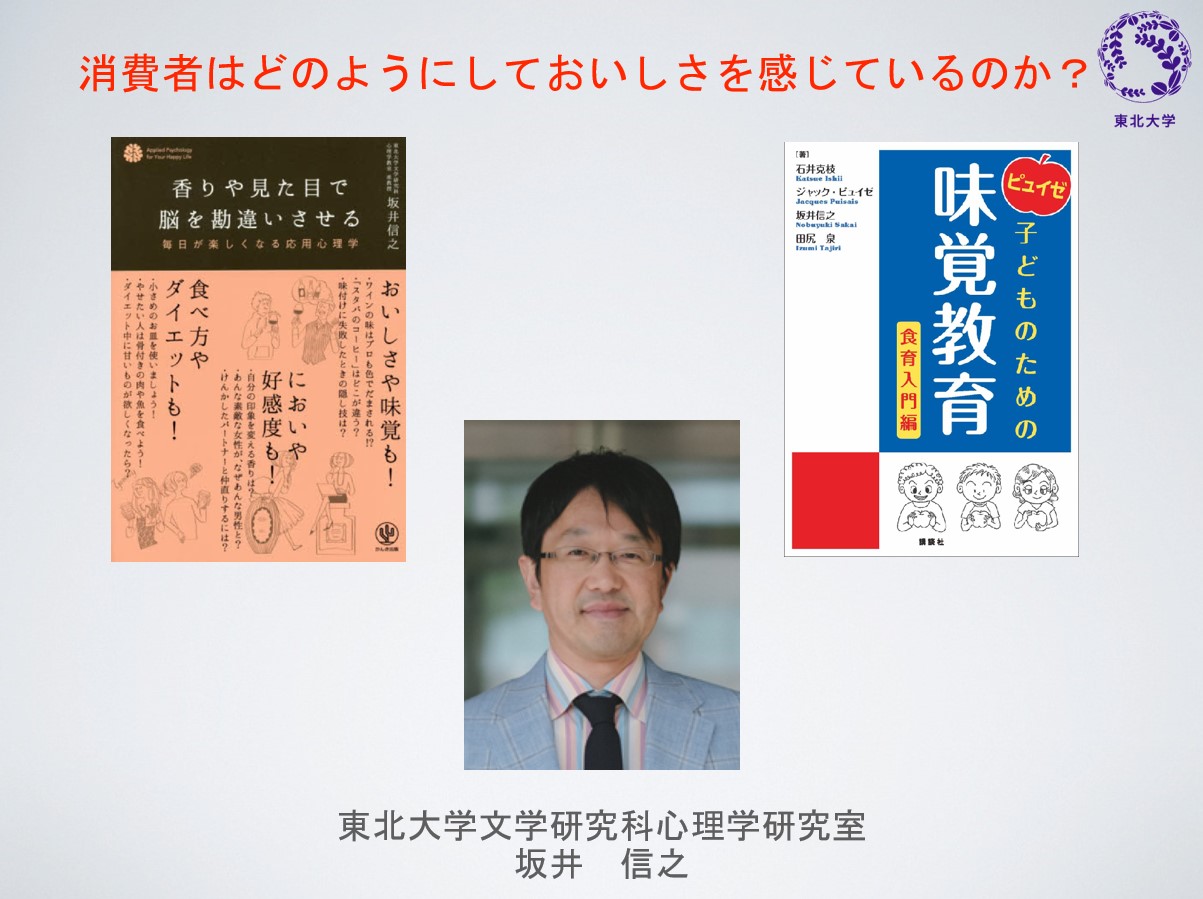 3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は大学院文学研究科心理学研究室 坂井 信之(さかい のぶゆき)教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。
3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は大学院文学研究科心理学研究室 坂井 信之(さかい のぶゆき)教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。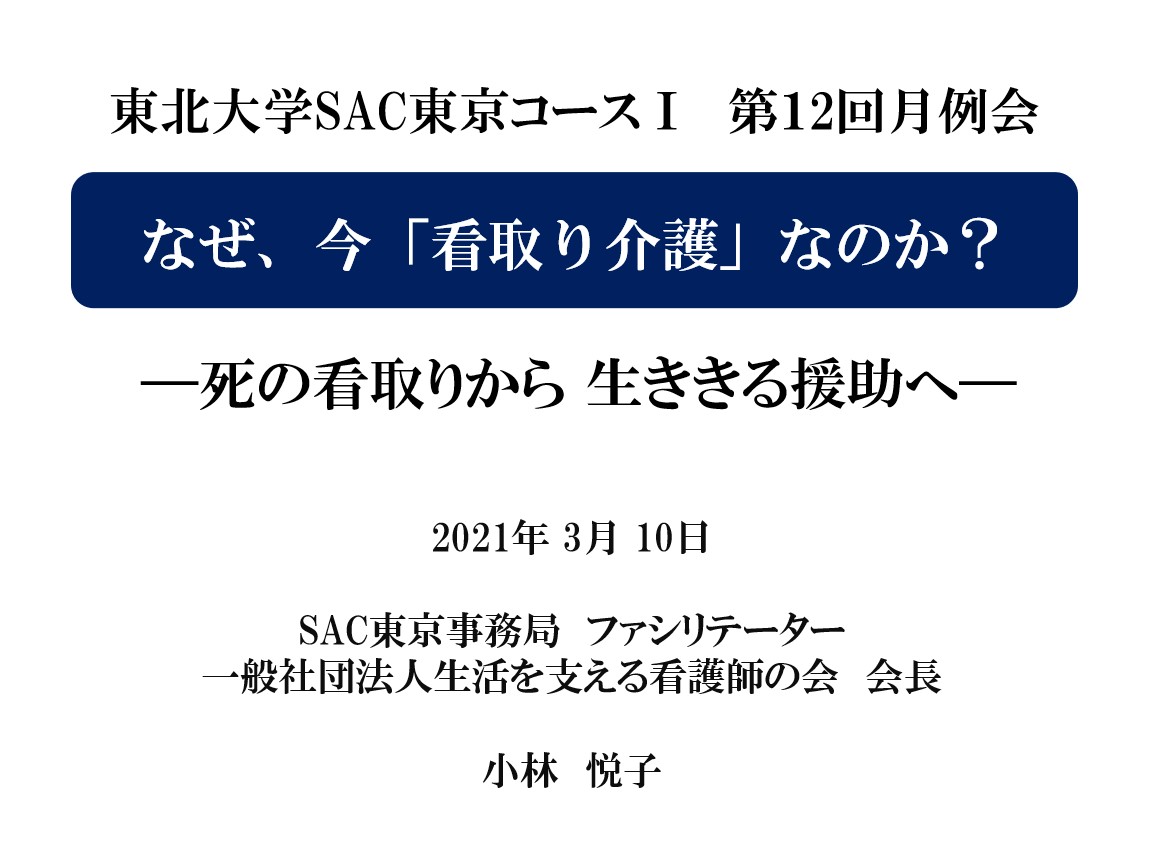 3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は東北大学ナレッジキャスト 小林 悦子(こばやし えつこ) ファシリテーター。講義テーマは「なぜ、今「看取り介護」なのか?―死の看取りから生ききる援助へ―」でした。
3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は東北大学ナレッジキャスト 小林 悦子(こばやし えつこ) ファシリテーター。講義テーマは「なぜ、今「看取り介護」なのか?―死の看取りから生ききる援助へ―」でした。
