SAC東京5期コースⅠ第10回月例会 参加者の声
1月23日、SAC東京コースⅠ第10回月例会 参加者の声
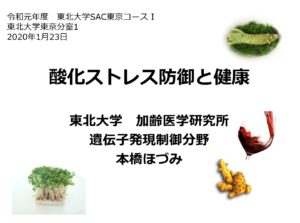 1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北大学 加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長の本橋ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。
1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北大学 加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長の本橋ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。
本橋先生は生化学・分子生物学がご専門で、わが国の酸化ストレス応答研究の第一人者です。
私たちの身体は環境中の毒性を感知し、遺伝子の発現を変化させることによって環境に対して応答・適応しています。
本橋先生は、生体の酸化ストレス応答を担う制御タンパク質Nrf2 が環境ストレスに対する応答を担う転写因子であることを世界に先駆けて発見しました。
また最近は、食品由来の化合物でNRF2を活性化させたアルツハイマー病モデルマウスに、中枢神経系の炎症の抑制と、記憶力の改善が見られることを発見しました。この発見は今後のアルツハイマー病治療への応用が期待されます
今回は酸化とストレス応答、環境適応のメカニズムから、生活環境における様々なストレスから身を守るための食生活の話まで、新規ビジネス発想のヒントになるお話をして頂きました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

 1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北メディカルメガバンク機構機構長 東北大学医学系研究科 教授(医化学分野)の山本雅之教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。
1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北メディカルメガバンク機構機構長 東北大学医学系研究科 教授(医化学分野)の山本雅之教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。

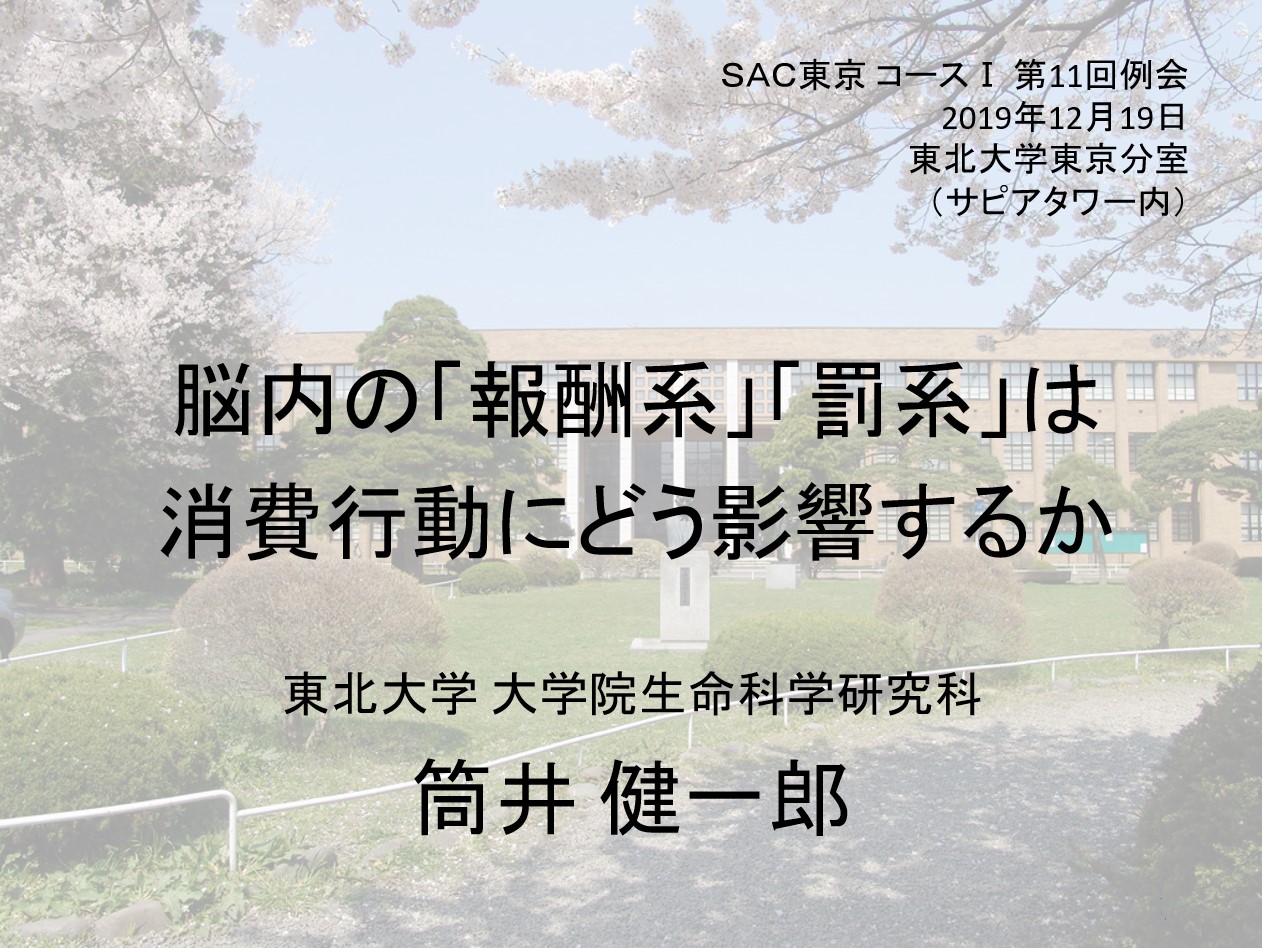
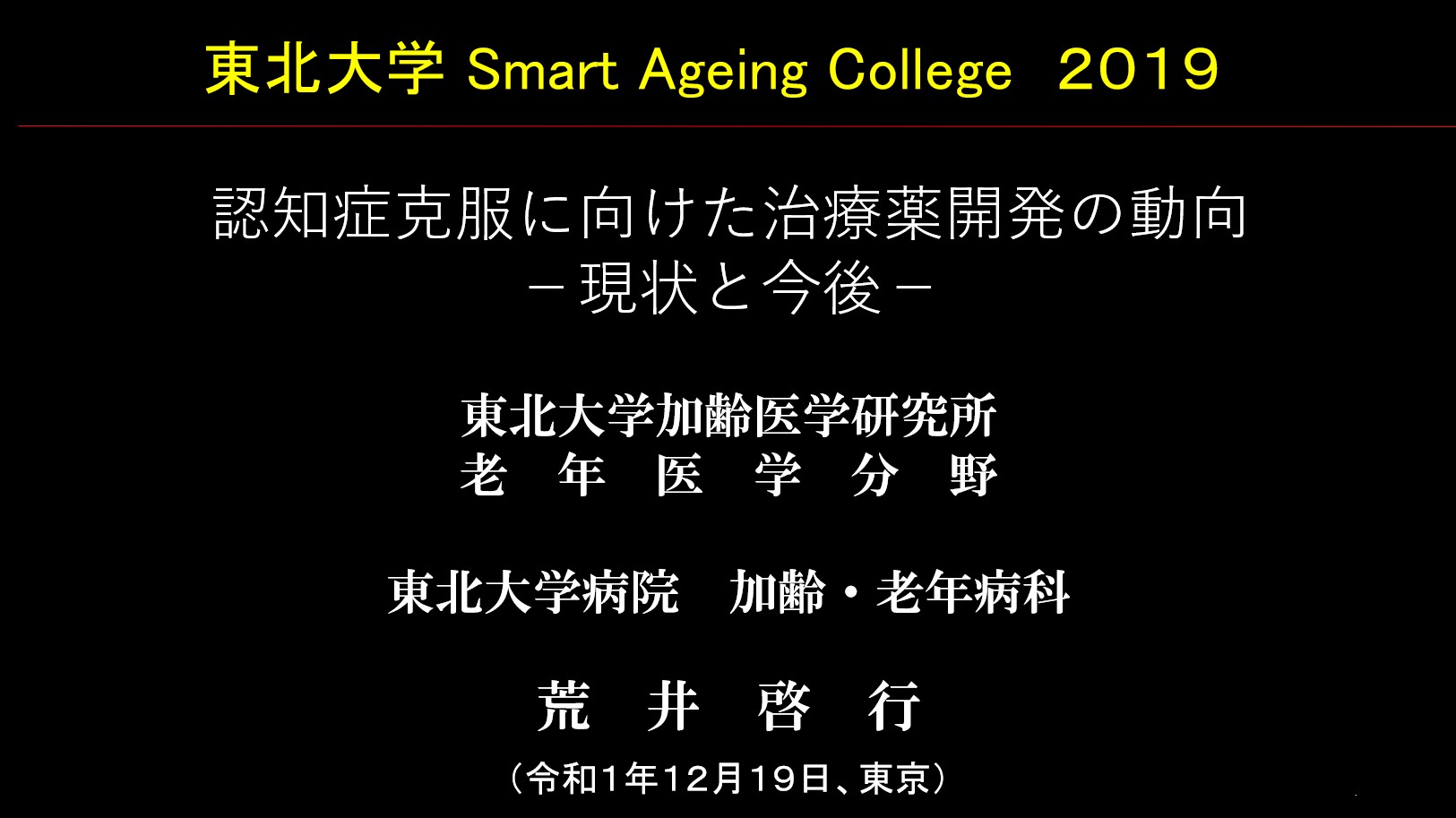 12月19日、SAC東京5期 第9回月例会開催されました。
12月19日、SAC東京5期 第9回月例会開催されました。