SAC東京6期コースⅡ第10回月例会 事務局レポート
酸化ストレス防御と健康
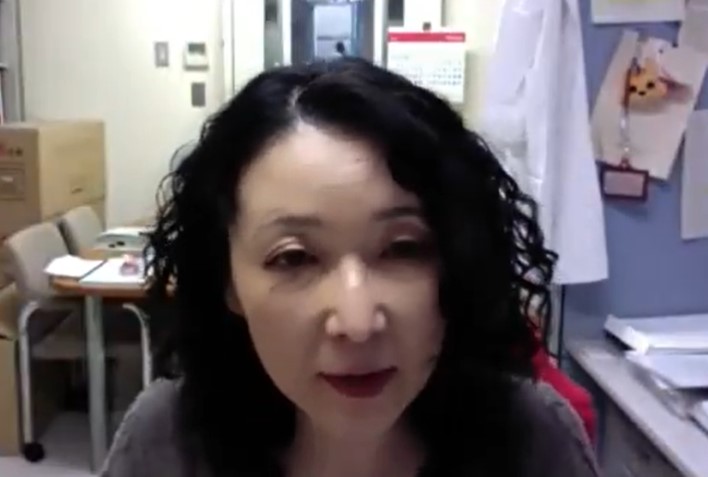
コースⅡ第10回月例会は、加齢医学研究所 副所長、加齢制御研究部門 遺伝子発現制御分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長の本橋ほづみ教授による「酸化ストレス防御と健康」が講義テーマです。
本橋先生の専門は生化学・分子生物学です。先生は生体の酸化ストレス応答を担う制御タンパク質NRF2(NF-E2 related factor)が環境ストレスに対する応答を担う転写因子であることを世界に先駆けて発見しました。酸化とストレス応答、環境適応のメカニズム、生活環境における様々なストレスから身を守るための食生活の話に加えて、SARS-CoV2(新型コロナウイルス)のビジネスヒントへと、ボリューム満載の講義となりました。

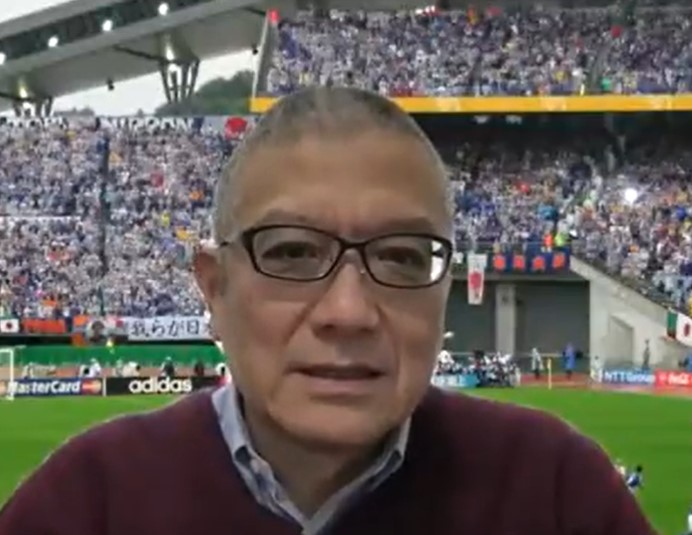
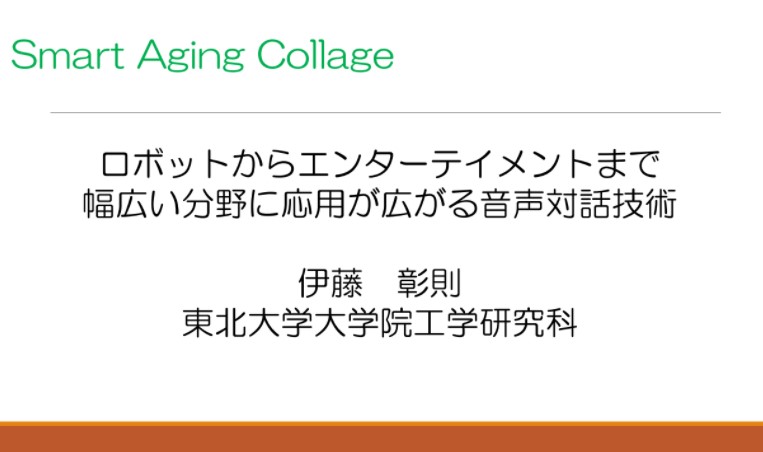 1月27日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は大学院工学研究科 総長特別補佐(情報基盤担当)情報シナジー機構 副機構長 伊藤 彰則教授。講義テーマは「ロボットからエンターテイメントまで ~幅広い分野に応用が広がる音声対話技術~」でした。
1月27日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は大学院工学研究科 総長特別補佐(情報基盤担当)情報シナジー機構 副機構長 伊藤 彰則教授。講義テーマは「ロボットからエンターテイメントまで ~幅広い分野に応用が広がる音声対話技術~」でした。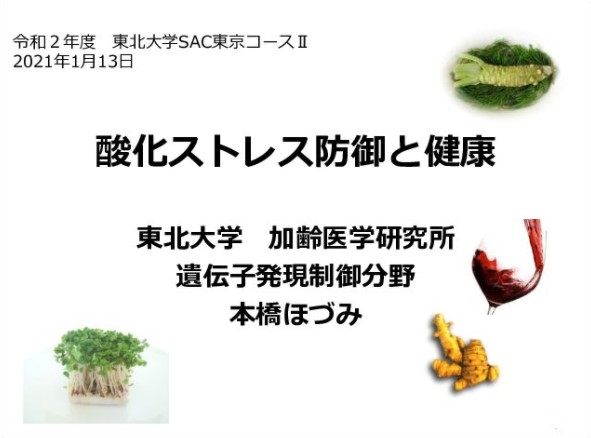 1月13日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は加齢医学研究所 加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野 スマート・エイジング学際重点研究センター副センター長 本橋 ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。
1月13日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は加齢医学研究所 加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野 スマート・エイジング学際重点研究センター副センター長 本橋 ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。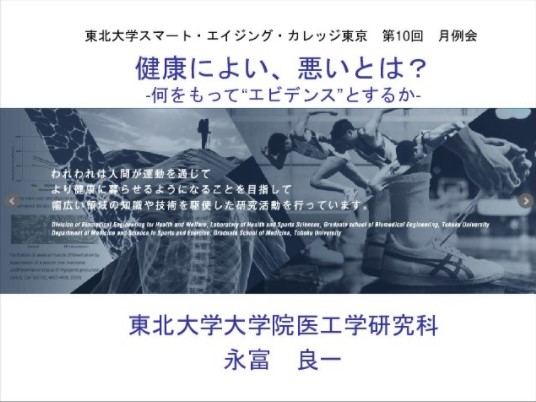 1月13日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は大学院医工学研究科長 創生応用医学研究センター永富 良一教授。講義テーマは「健康によい、悪いとは? —何を持って“エビデンス”とするか—」でした。
1月13日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は大学院医工学研究科長 創生応用医学研究センター永富 良一教授。講義テーマは「健康によい、悪いとは? —何を持って“エビデンス”とするか—」でした。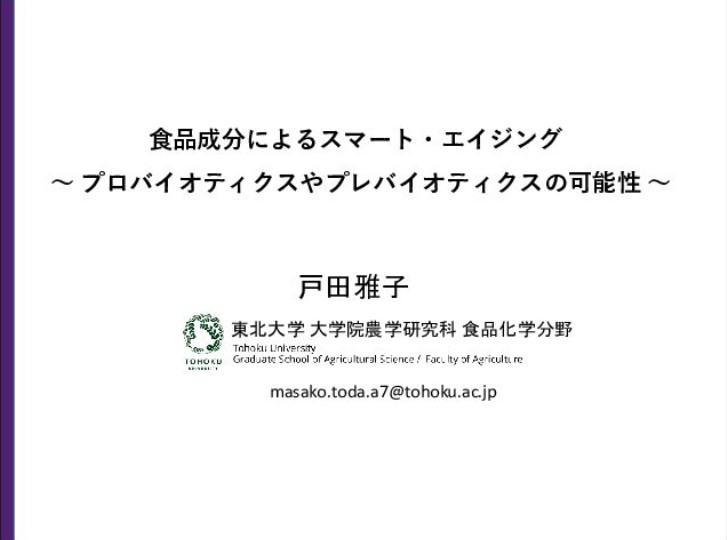 12月23日、SAC東京6期 第9回月例会開催されました。講師は大学院農学研究科食品化学分野、未来科学技術共同研究センター 戸田雅子教授。講義テーマは「食品成分によるスマ-ト・エイジング ~プロバイオティクスやプレバイオティクスの可能性~」でした。
12月23日、SAC東京6期 第9回月例会開催されました。講師は大学院農学研究科食品化学分野、未来科学技術共同研究センター 戸田雅子教授。講義テーマは「食品成分によるスマ-ト・エイジング ~プロバイオティクスやプレバイオティクスの可能性~」でした。