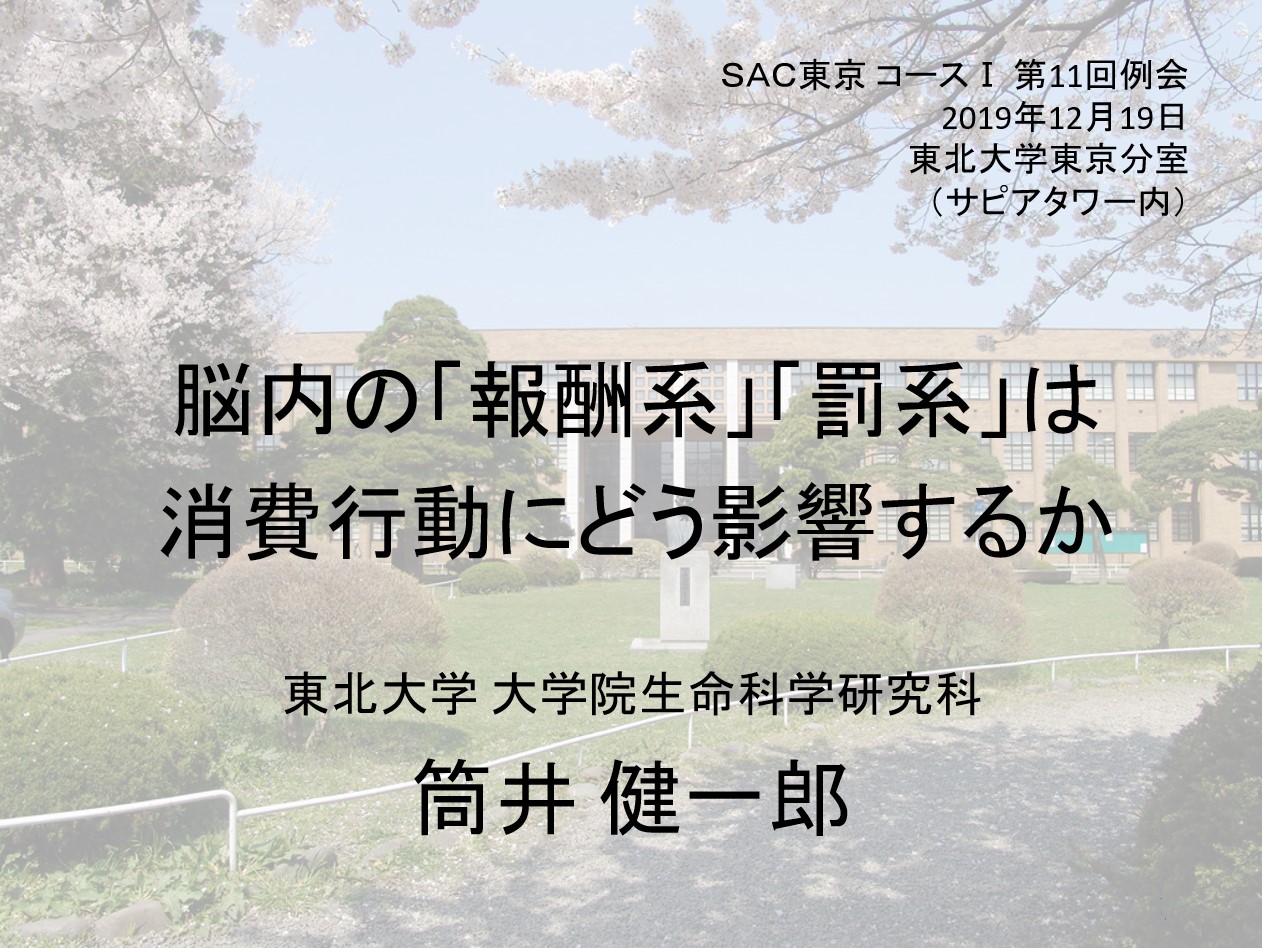SAC東京6期コースⅡ第1回月例会 参加者の声
5月12日、SAC東京コースⅡ第1回月例会 参加者の声
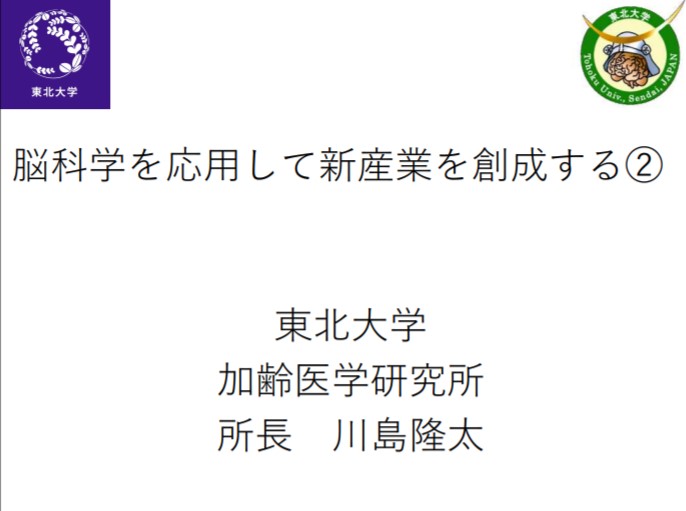 5月12日、SAC東京6期 第1回月例会開催されました。
5月12日、SAC東京6期 第1回月例会開催されました。
講師は、東北大学 加齢医学研究所 所長 兼 スマート・エイジング学際重点研究センター所長の川島隆太教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する②」でした。
第6期コースⅡの最初の月例会では、川島教授による脳科学の産業応用の最新動向についてでした。まず、様々な脳機能イメージング装置で何ができるかの基礎知識を次の項目で確認していきました。
-
- 脳機能イメージング装置の違いは?
- ブレインマッピングとは?
- デコーディングとは?
- ニューロ・マーケティングとは?
- コミュニケーションの質の定量化
そのうえで、最新応用事例として世界中の経営者が関心を持っている「マインドフルネス瞑想」を取り上げ、瞑想アプリの作成と社会実装の詳細についてお話されました。
最後に「バーチャルリアリティによる疑似運動」と脳活動の関係、「高齢者の安全運転能力向上脳トレ」など最新事例を通じて、脳科学からビジネスを生み出す際の勘所をお話いただきました。
脳機能イメージング研究の第一人者が脳科学と社会実装を余すことなく語る貴重な機会となりました。参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

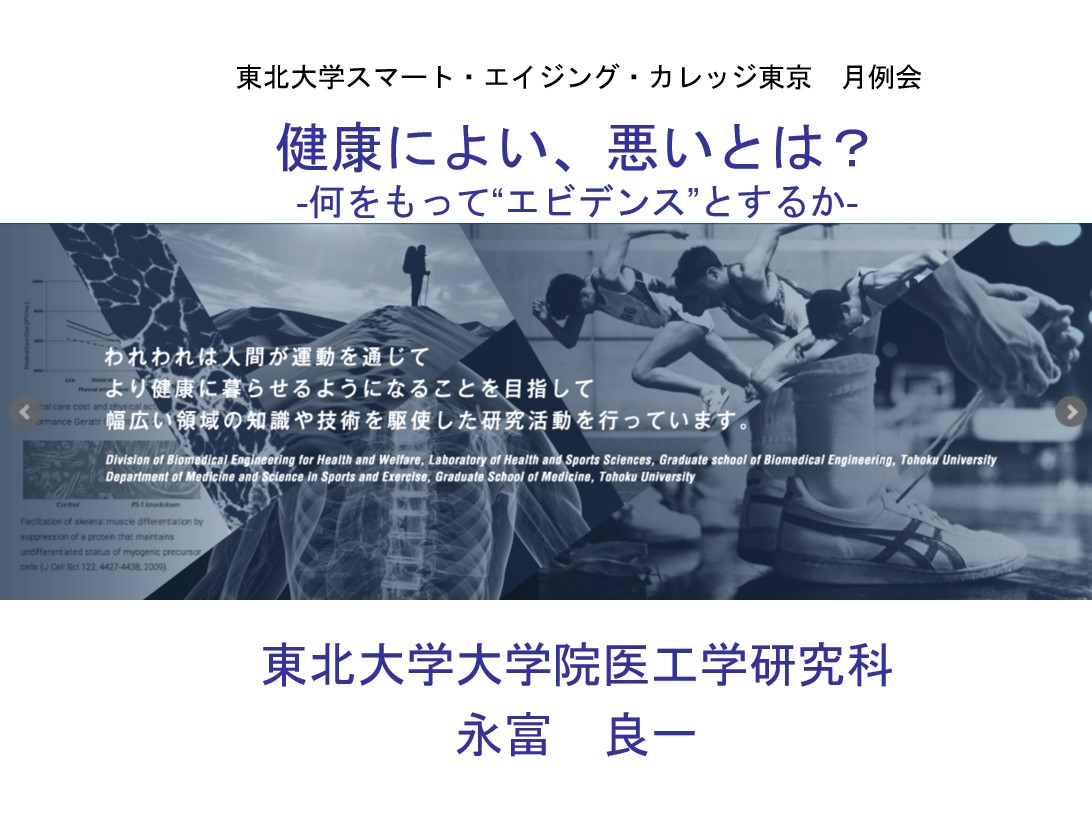 2月20日、SAC東京5期 第11回月例会開催されました。講師は、東北大学 医工学研究科副研究科長の永富良一教授。講義テーマは「健康によい、悪いとは? -何をもって“エビデンス”とするか-」でした。
2月20日、SAC東京5期 第11回月例会開催されました。講師は、東北大学 医工学研究科副研究科長の永富良一教授。講義テーマは「健康によい、悪いとは? -何をもって“エビデンス”とするか-」でした。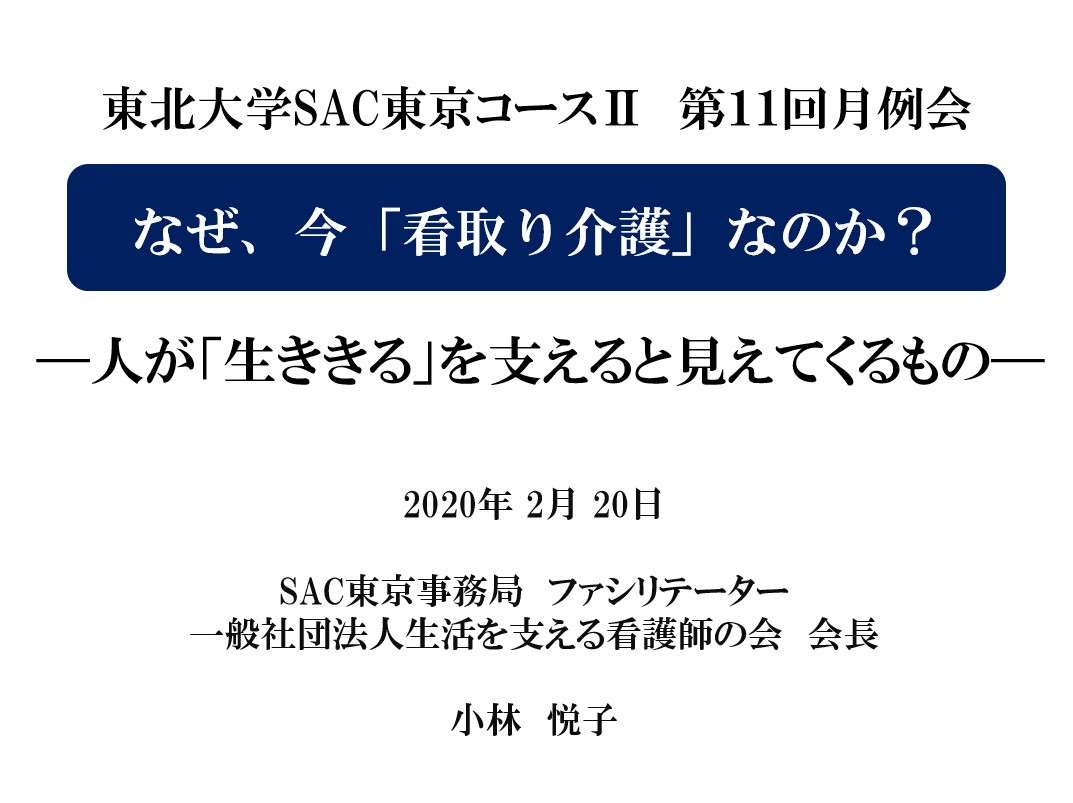 2月20日、SAC東京5期 第11回月例会開催されました。講師は、東北大学SAC東京事務局、生活を支える看護師の会会長の小林悦子ファシリテーター。講義テーマは「なぜ、今「看取り介護」なのか? ―人が「生ききる」を支えると見えてくるもの―」でした。
2月20日、SAC東京5期 第11回月例会開催されました。講師は、東北大学SAC東京事務局、生活を支える看護師の会会長の小林悦子ファシリテーター。講義テーマは「なぜ、今「看取り介護」なのか? ―人が「生ききる」を支えると見えてくるもの―」でした。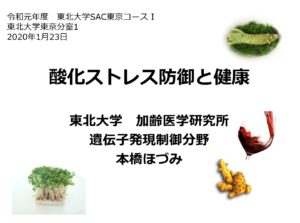 1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北大学 加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長の本橋ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。
1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北大学 加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長の本橋ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。 1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北メディカルメガバンク機構機構長 東北大学医学系研究科 教授(医化学分野)の山本雅之教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。
1月23日、SAC東京5期 第10回月例会開催されました。講師は、東北メディカルメガバンク機構機構長 東北大学医学系研究科 教授(医化学分野)の山本雅之教授。講義テーマは「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」でした。