SAC東京6期コースⅠ第5回月例会 参加者の声
8月19日、SAC東京コースⅠ第5回月例会 参加者の声
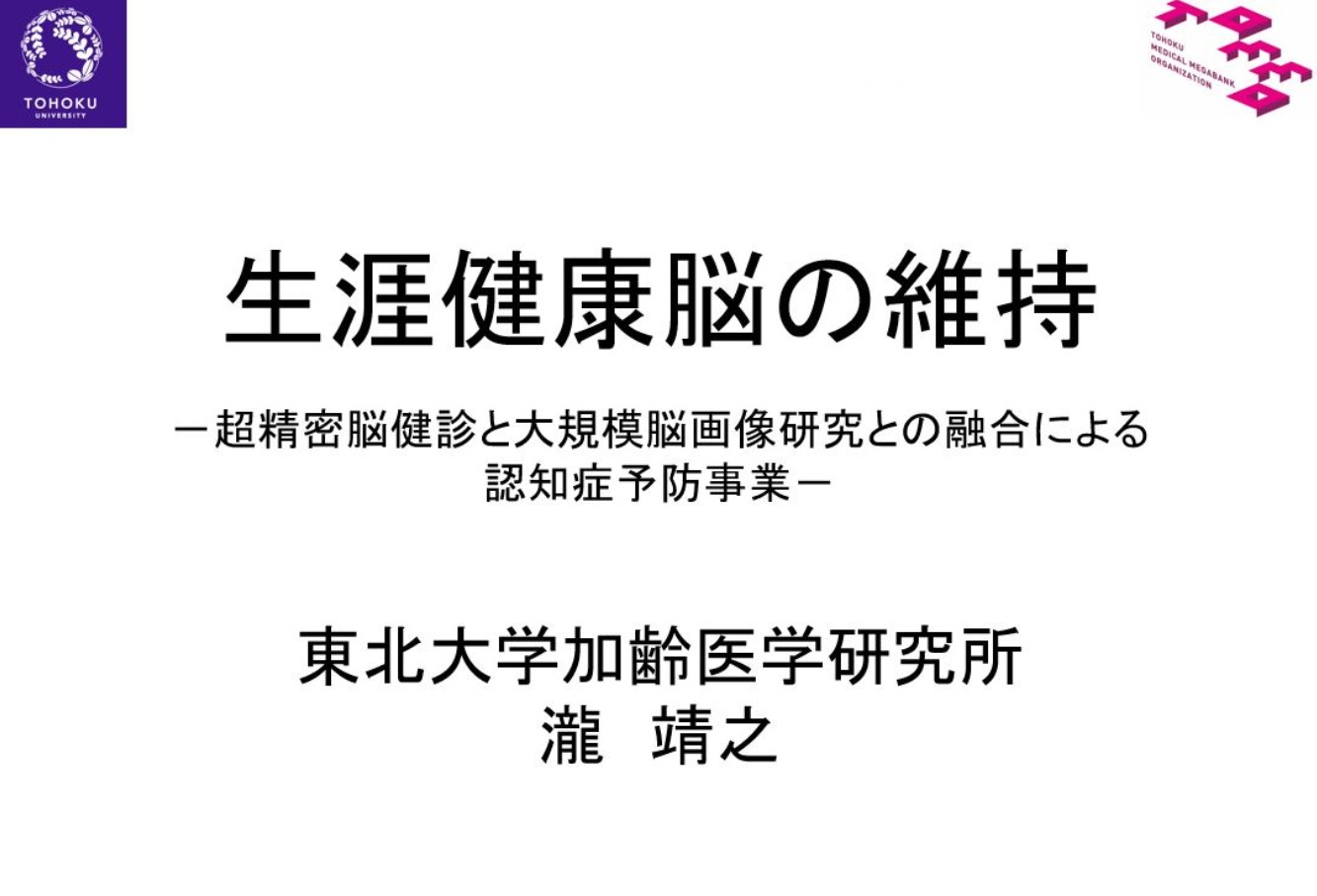 8月19日、SAC東京6期 第5回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長 瀧 靖之 教授。講義テーマは「生涯健康脳の維持①」でした。
8月19日、SAC東京6期 第5回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野 スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長 瀧 靖之 教授。講義テーマは「生涯健康脳の維持①」でした。
認知症リスクを抑えるには脳を生涯に渡って健康に保つ事が大変重要です。東北大学には、多数の方の脳のMRI計測データが集積されており、瀧教授らは生涯健康脳の維持に関わる多くの研究成果を発表してきました。
今回の講義では、最新の脳科学の知見を元に、どのような生活習慣が脳の健やかな発達に貢献するか、どのような生活習慣が健康な脳や認知力の維持に影響を与え、認知症のリスクを抑えていくか、お話しいただきました。
更に、これらの知見に基づく、生涯健康脳に関する種々のサービス、商品事業化の展望についてのお話もあり、認知症予防に向けて何が重要かを包括的に理解する絶好の機会となりました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

 7月22日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。
7月22日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。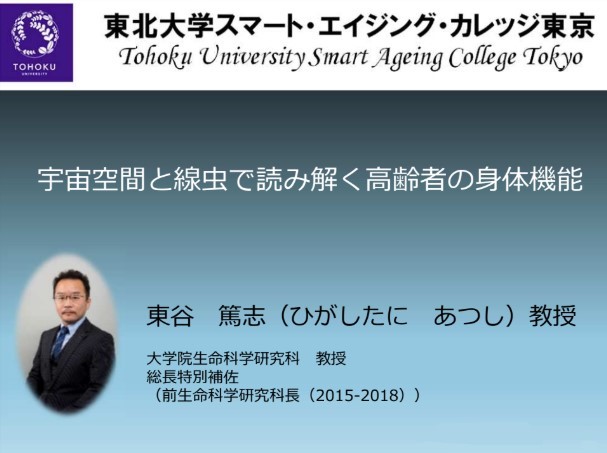 7月8日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。
7月8日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。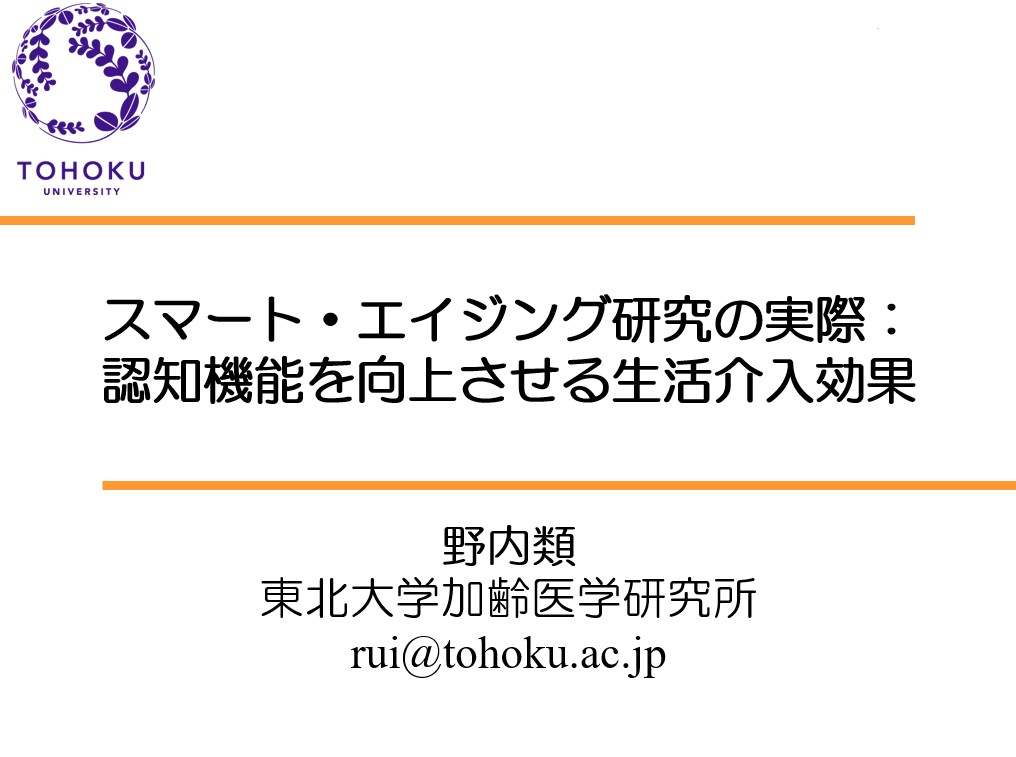 7月8日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。
7月8日、SAC東京6期 第4回月例会開催されました。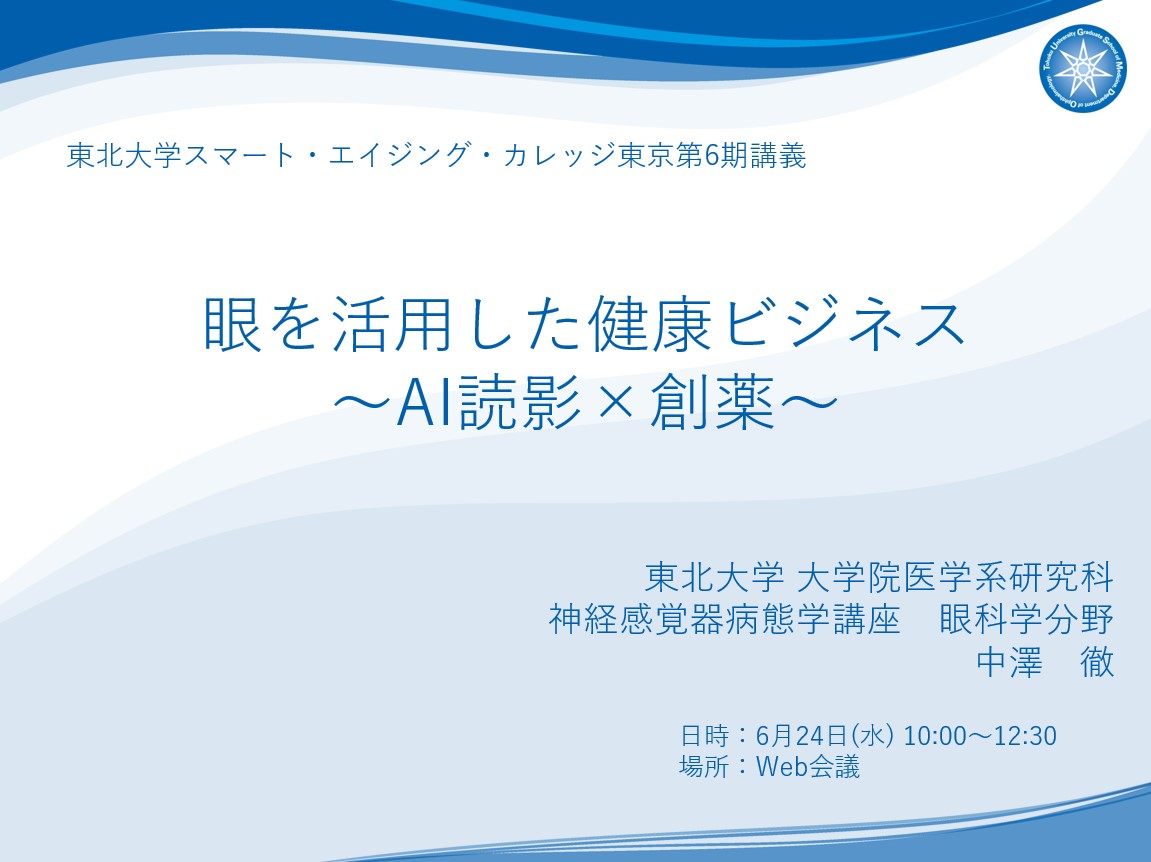 6月24日、SAC東京6期 第3回月例会開催されました。
6月24日、SAC東京6期 第3回月例会開催されました。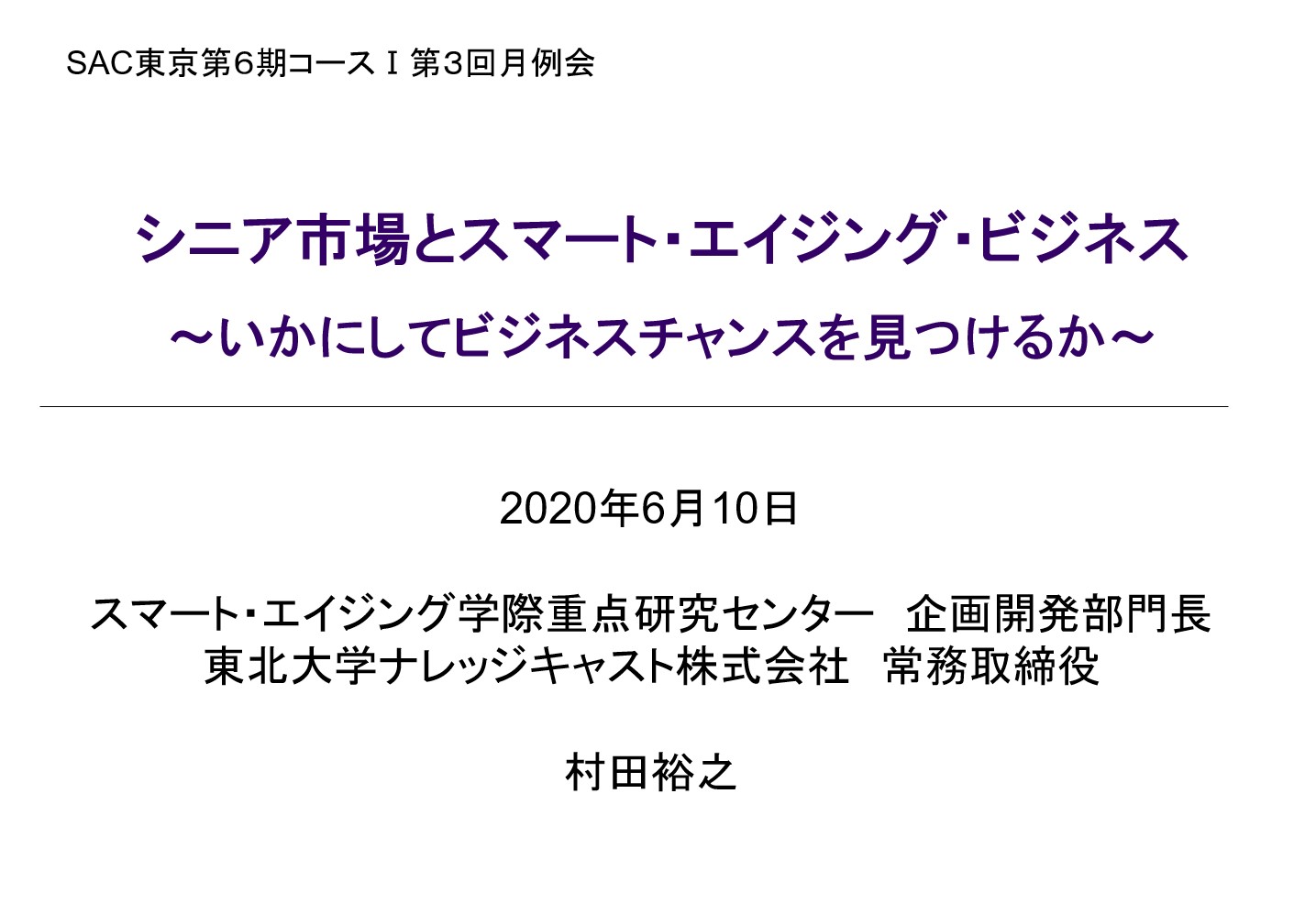 6月10日、SAC東京6期 第3回月例会開催されました。
6月10日、SAC東京6期 第3回月例会開催されました。