SAC東京6期 第1回産学共創フォーラム 参加者の声
SAC東京6期 第1回産学連携フォーラム 参加者の声
 11月25日、SAC東京6期 第1回産学連携フォーラムが開催されました。産学共創フォーラムは、通常の月例会を発展させ、SAC東京参加企業の皆様が一堂に学び合える機会です。
11月25日、SAC東京6期 第1回産学連携フォーラムが開催されました。産学共創フォーラムは、通常の月例会を発展させ、SAC東京参加企業の皆様が一堂に学び合える機会です。
第1部では「東北大学研究最前線」をテーマに、西條芳文教授には「東北大学の先端医工学技術で診る皮膚のエイジング」、杉田典大准教授には「室内に置かれた通信デバイス電波による”ウェアレス”活動量計」についてお話頂きました。
第2部の参加企業6社による「商品・サービス紹介ピッチ」では、各社の最新の商品・サービス動向などのプレゼンテーションが行われ、第3部ではグループトークとグループ別発表・質疑がありました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

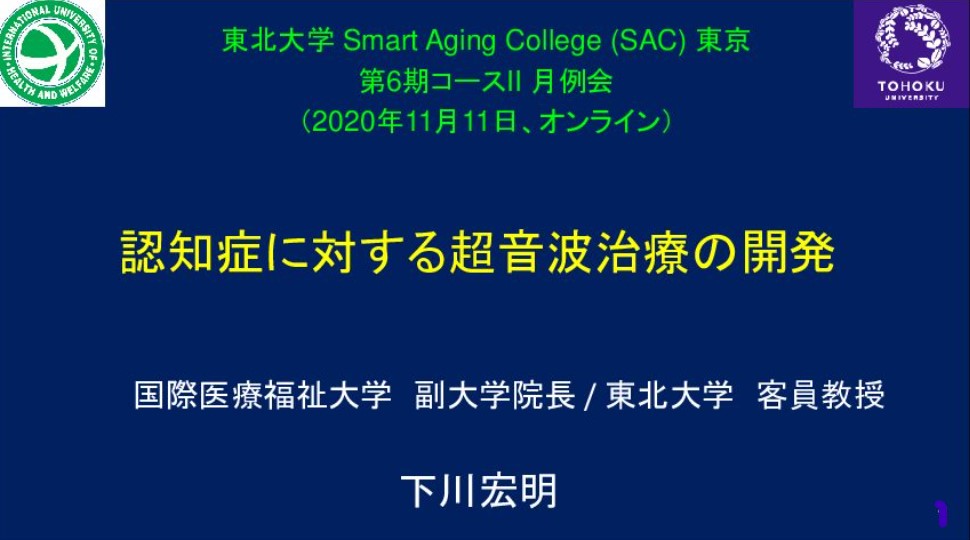 11月11日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。
11月11日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。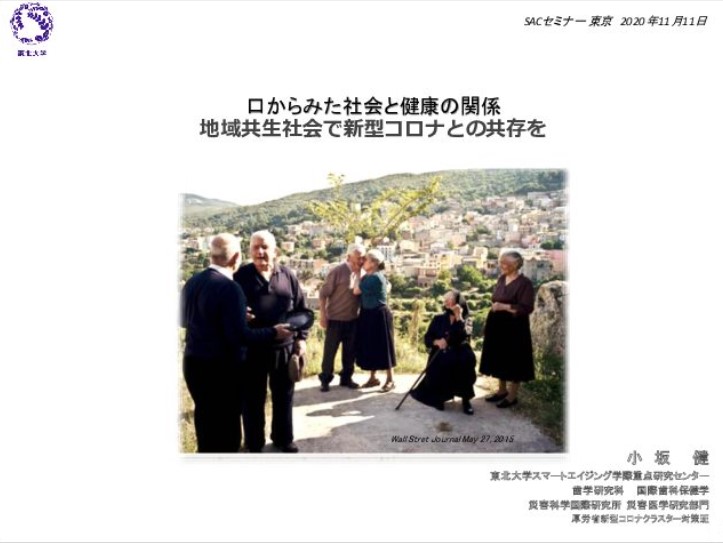 11月11日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。
11月11日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。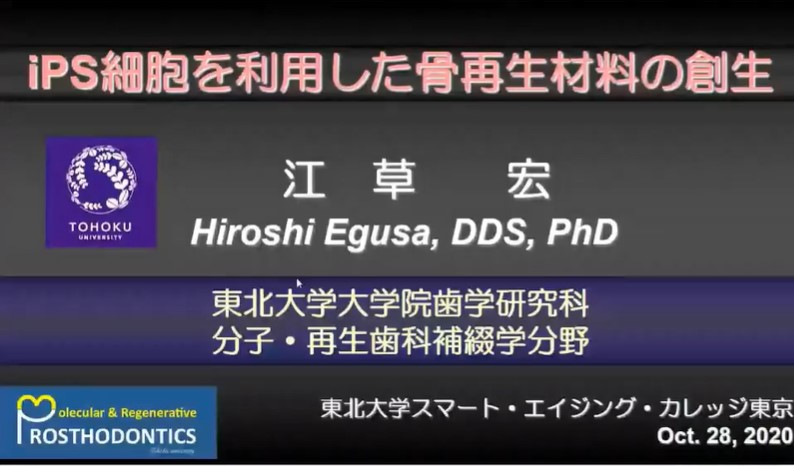 10月28日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。
10月28日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。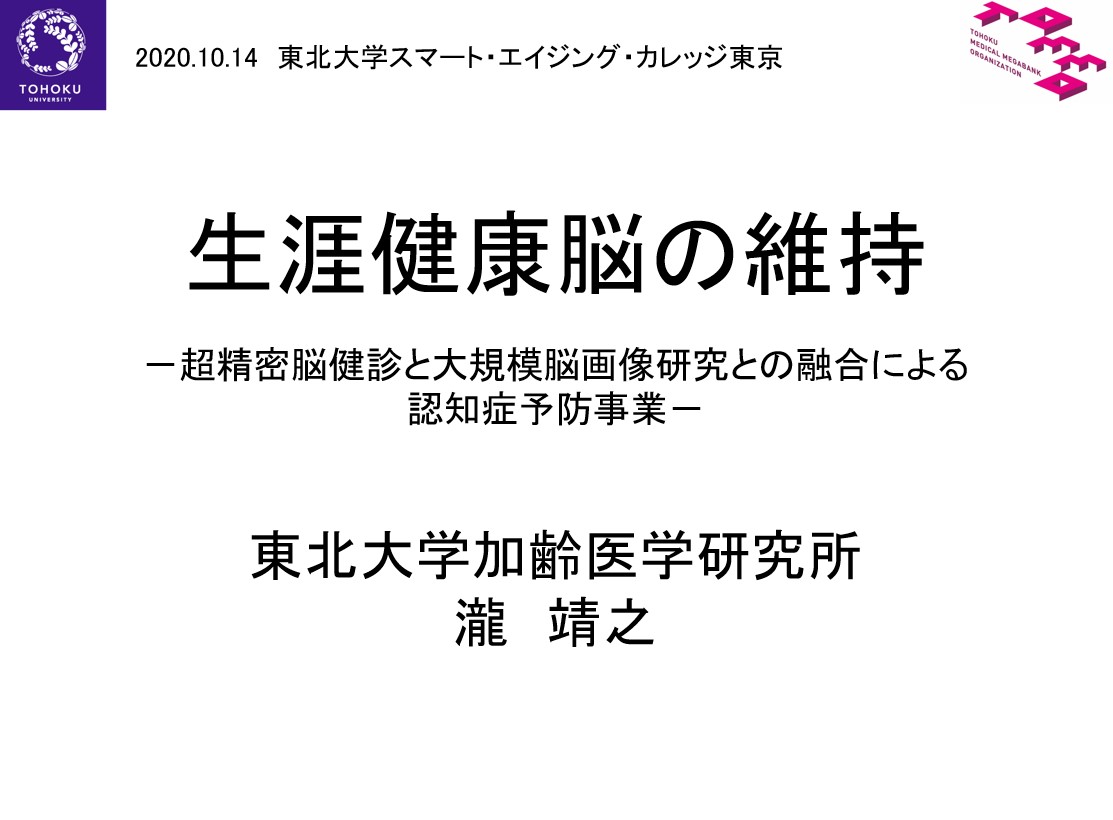 10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。
10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。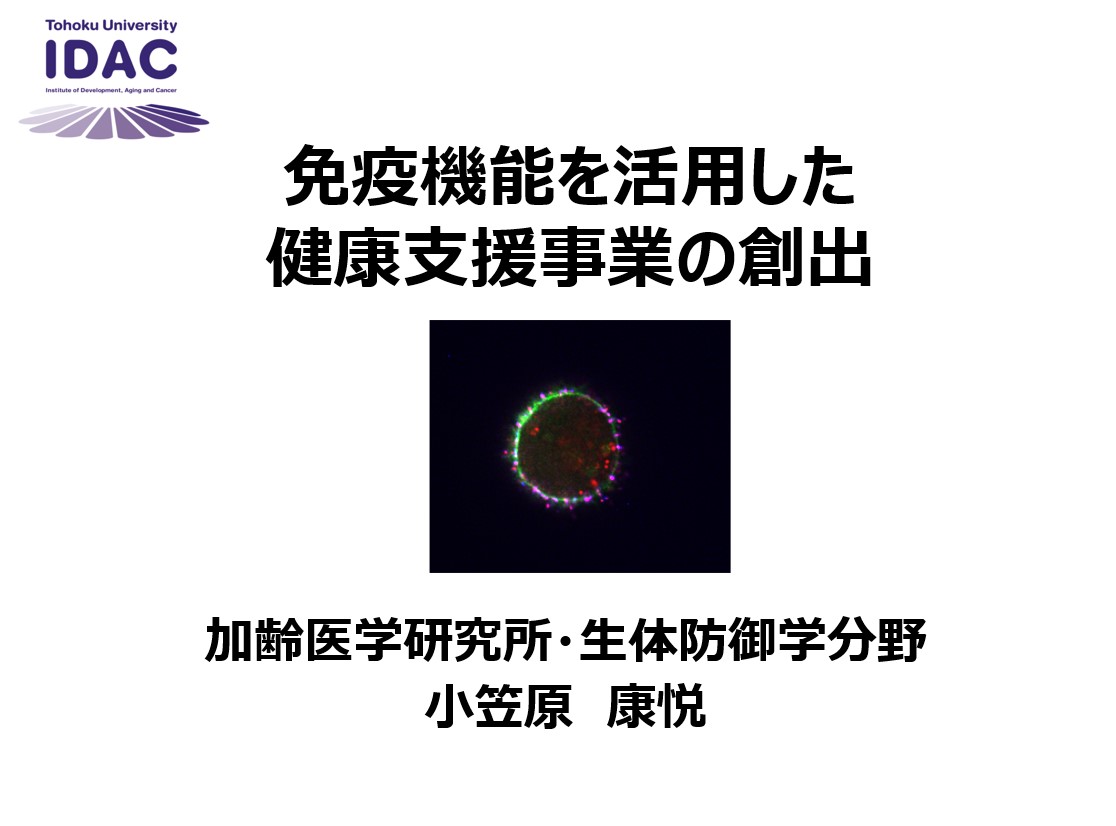 10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。
10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。