SAC東京6期コースⅡ第12回月例会 参加者の声
3月10日、SAC東京コースⅡ第12回月例会 参加者の声
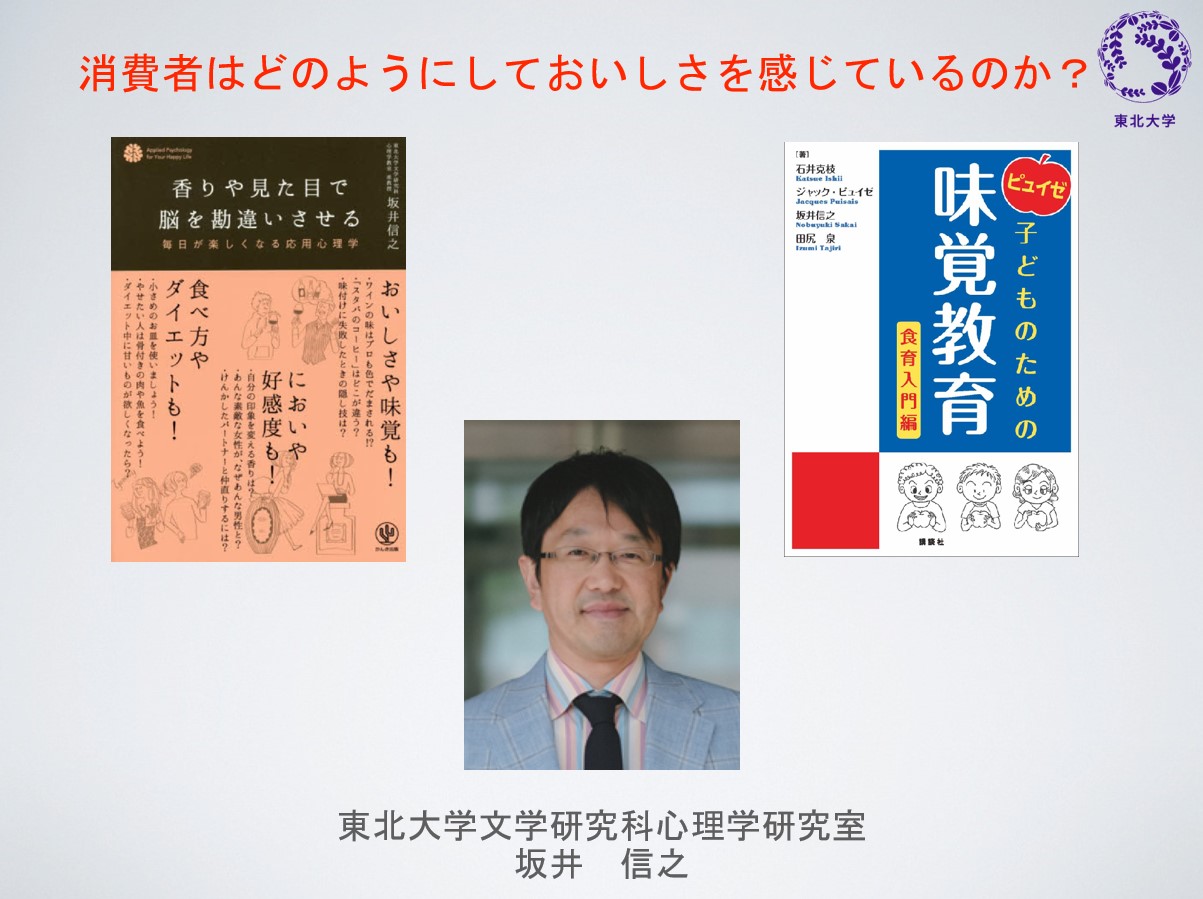 3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は大学院文学研究科心理学研究室 坂井 信之(さかい のぶゆき)教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。
3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は大学院文学研究科心理学研究室 坂井 信之(さかい のぶゆき)教授。講義テーマは「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。
「おいしい食品」というコンセプトで商品を開発しても、消費者はそのように受け取ってくれるとは限らないという経験はありませんか?
商品の設計意図と異なる受け取り方をされて予想以上に売れてしまった(しかし、原因がわからない)という経験もあるかもしれません。今回は、これらの見込み違いについて、心理学や脳科学の観点から解説していただきました。
結論は「人は美味しさを舌で味わっているわけではない」「食品自体においしさが含まれているのではない」ということになります。消費者は商品の何に注目して購入を決定するのか。また、どのようにしてその商品を使って評価するのか。さらに、その商品に対する印象をどのように形成し、次の商品購入の基礎情報とするのか、などについてもお話がありました。
これらの知識は、食品に限らず、日用品やサービスにも適用でき、宣伝広告やマーケティング戦略の計画立案にも適用できるでしょう。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

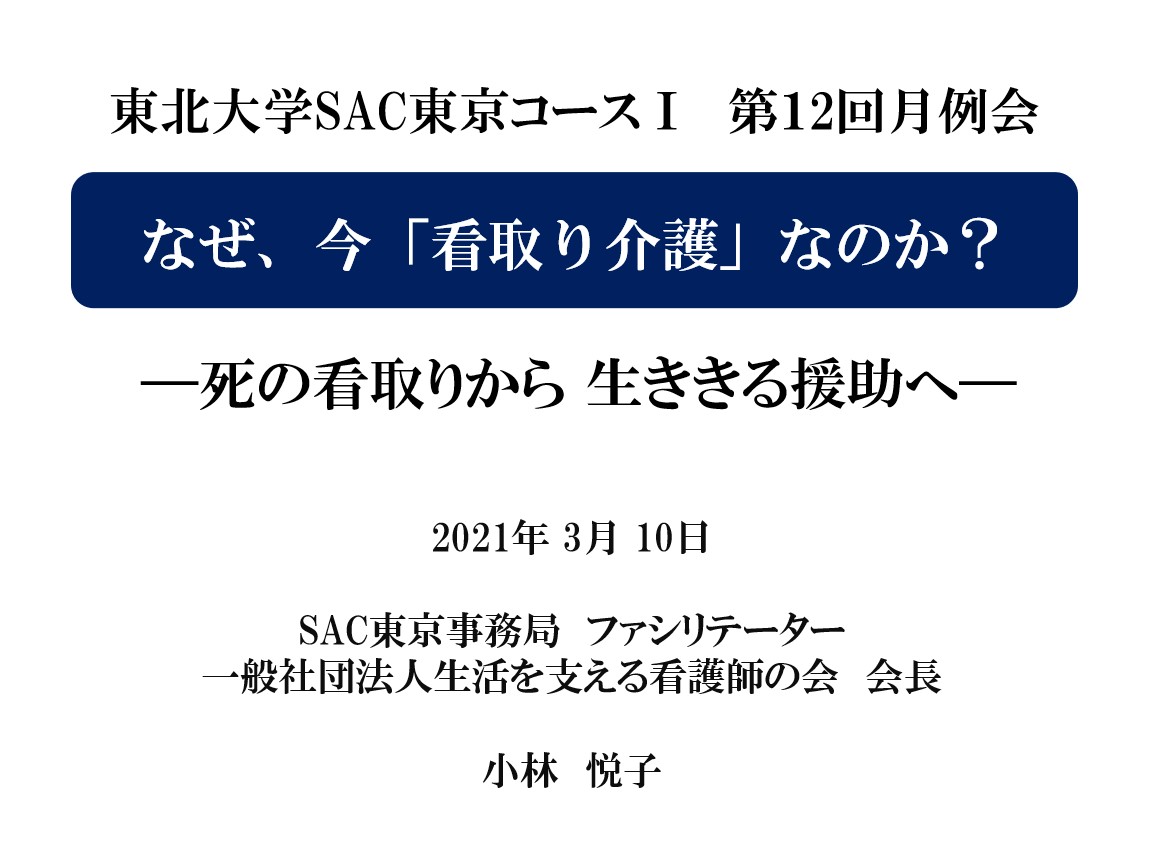 3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は東北大学ナレッジキャスト 小林 悦子(こばやし えつこ) ファシリテーター。講義テーマは「なぜ、今「看取り介護」なのか?―死の看取りから生ききる援助へ―」でした。
3月10日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は東北大学ナレッジキャスト 小林 悦子(こばやし えつこ) ファシリテーター。講義テーマは「なぜ、今「看取り介護」なのか?―死の看取りから生ききる援助へ―」でした。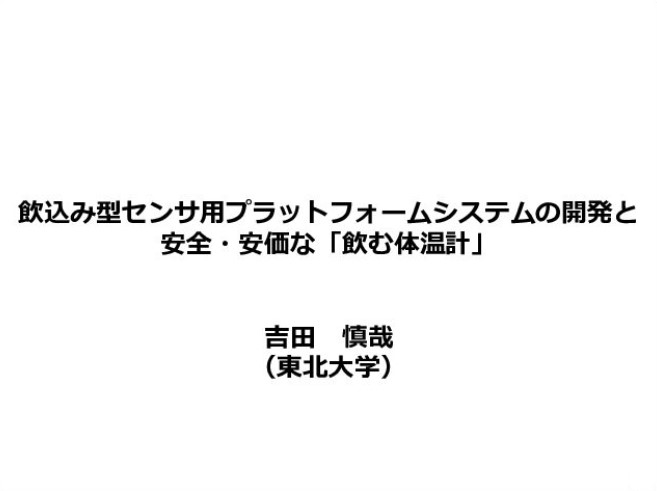 講師は大学院工学研究科 ロボティクス専攻 吉田慎哉 特任准教授。講義テーマは「飲込み型センサ用プラットフォームシステムの開発と安全・安価な「飲む体温計」でした。
講師は大学院工学研究科 ロボティクス専攻 吉田慎哉 特任准教授。講義テーマは「飲込み型センサ用プラットフォームシステムの開発と安全・安価な「飲む体温計」でした。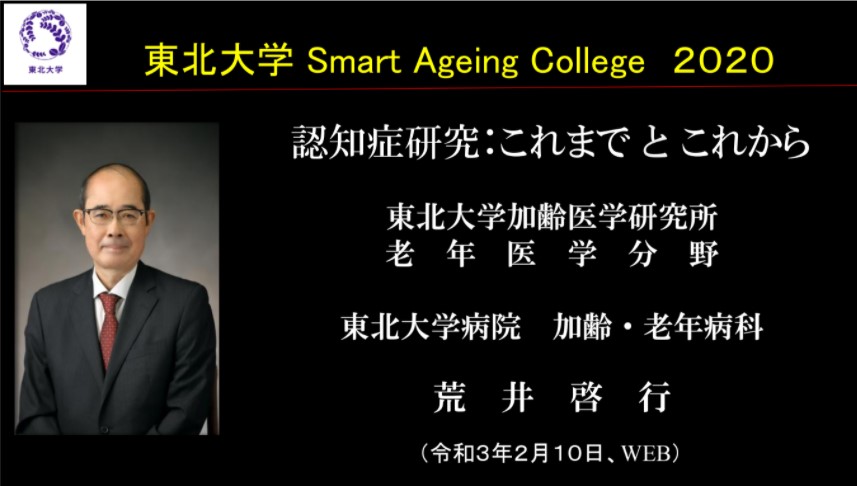 2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は加齢医学研究所 脳科学部門 老年医学分野、東北大学病院 加齢・老年病科長 荒井 啓行教授。講義テーマは「認知症研究:これまでとこれから」でした。
2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は加齢医学研究所 脳科学部門 老年医学分野、東北大学病院 加齢・老年病科長 荒井 啓行教授。講義テーマは「認知症研究:これまでとこれから」でした。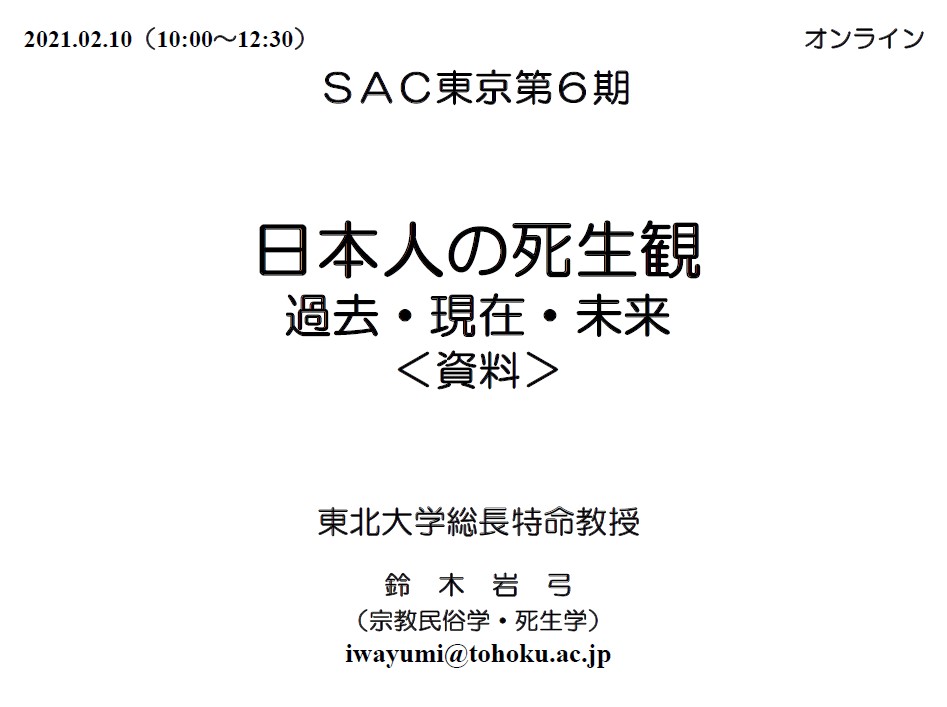 2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は教養教育院 鈴木岩弓総長特命教授。講義テーマは「日本人の死生観 ―過去・現在・未来―」でした。
2月10日、SAC東京6期 第11回月例会開催されました。講師は教養教育院 鈴木岩弓総長特命教授。講義テーマは「日本人の死生観 ―過去・現在・未来―」でした。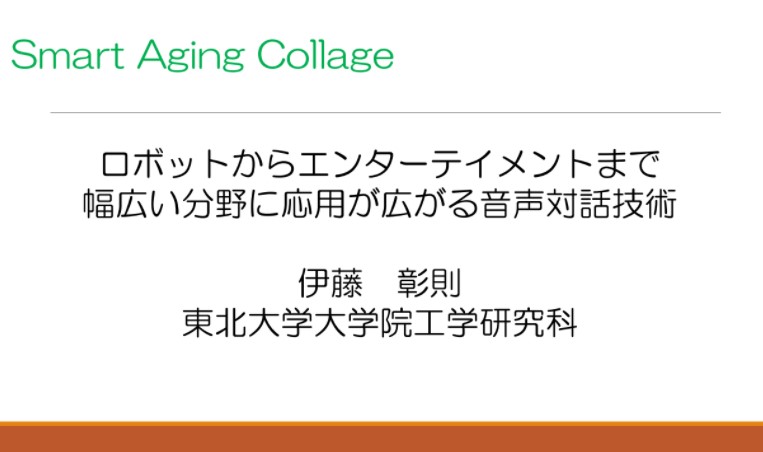 1月27日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は大学院工学研究科 総長特別補佐(情報基盤担当)情報シナジー機構 副機構長 伊藤 彰則教授。講義テーマは「ロボットからエンターテイメントまで ~幅広い分野に応用が広がる音声対話技術~」でした。
1月27日、SAC東京6期 第10回月例会開催されました。講師は大学院工学研究科 総長特別補佐(情報基盤担当)情報シナジー機構 副機構長 伊藤 彰則教授。講義テーマは「ロボットからエンターテイメントまで ~幅広い分野に応用が広がる音声対話技術~」でした。