SAC東京6期コースⅢ第7回月例会 事務局レポート
iPS細胞を利用した骨再生材料の創生

コースⅢ第7回月例会は、大学院歯学研究科 分子・再生歯科補綴学分野、歯学イノベーションリエゾンセンター長、先端再生医学研究センター長、東北大学病院 副病院長の江草宏教授による「iPS細胞を利用した骨再生材料の創生」が講義テーマです。
江草教授は、香港やアメリカなど海外での研究を重ね、日本に帰国後は京都大学山中伸弥教授との交流から歯科に初めてiPS細胞の研究概念を持ち込みました。歯茎からiPS細胞をつくる研究を始めた第一人者です。大学院の分子・再生歯科補綴学分野では、患者の診断、臨床教育、研究の三本柱で、無くなった歯を再生する業務に携わっています。
本日の講義は以下の4つの構成で進められました。
- 再生医療とは?
- 歯茎×iPS細胞=再生医療?
- iPS細胞から骨を作って、歯も創る?
- 人生100年時代の再生医療


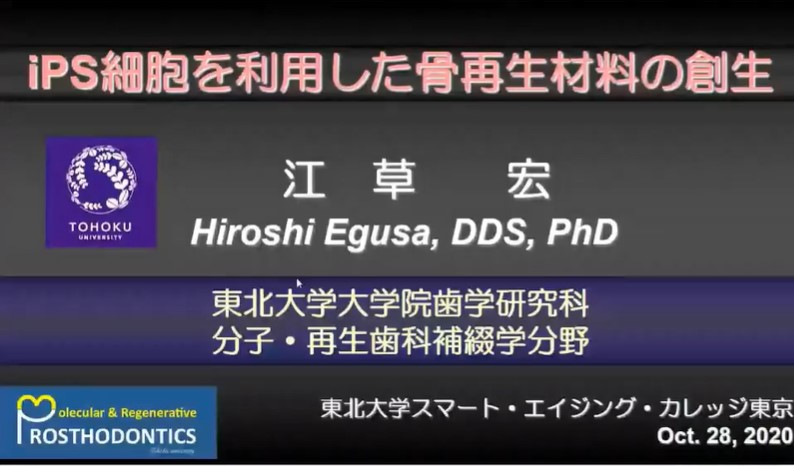 10月28日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。
10月28日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。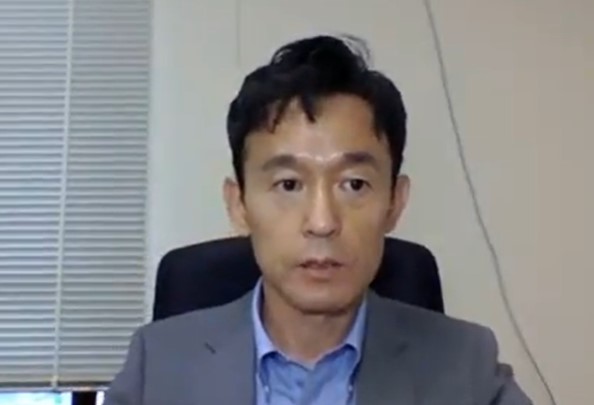

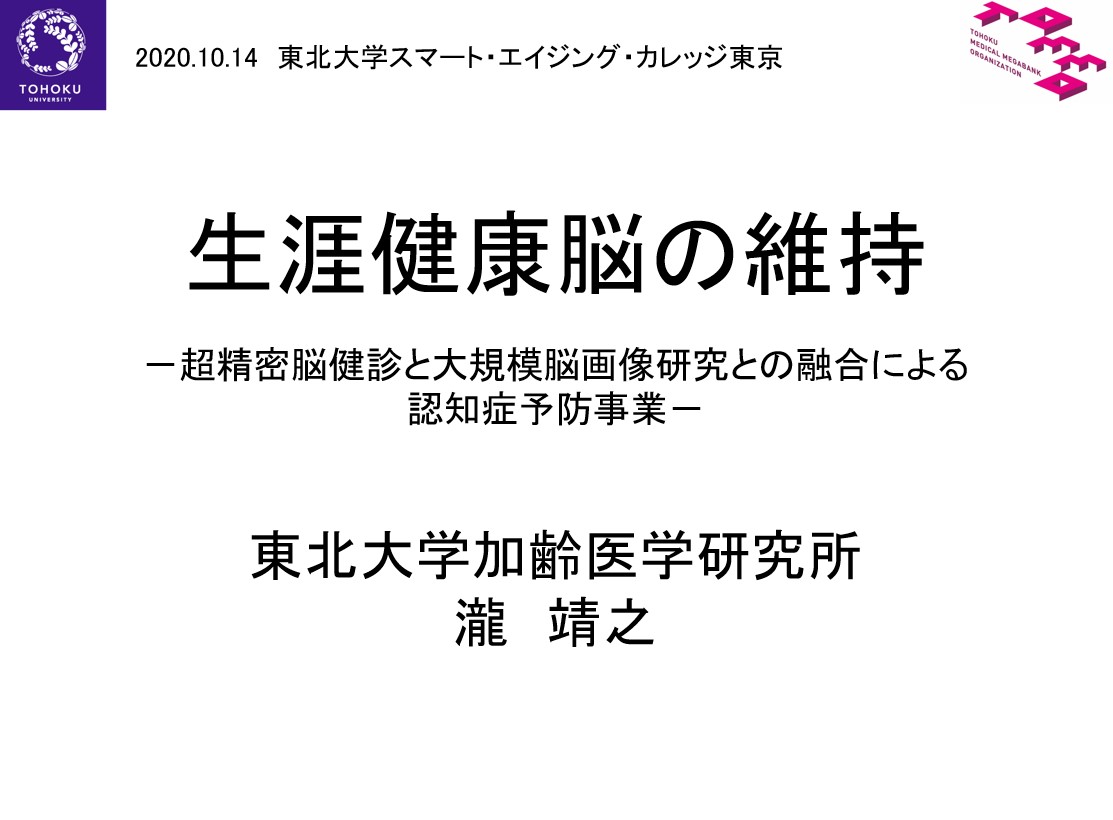 10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。
10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。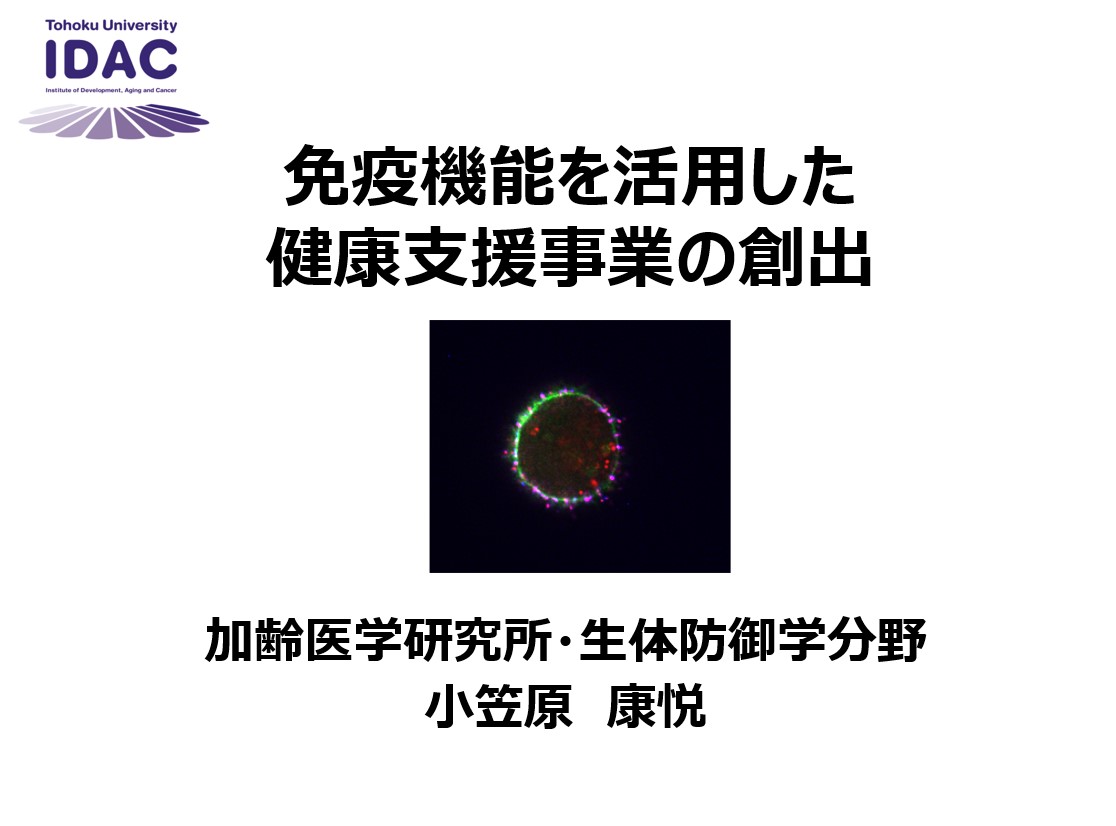 10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。
10月14日、SAC東京6期 第7回月例会開催されました。