SAカレッジ21年度 コースⅡ第7回月例会 参加者の声
本橋ほづみ 教授「酸化ストレス防御と健康」
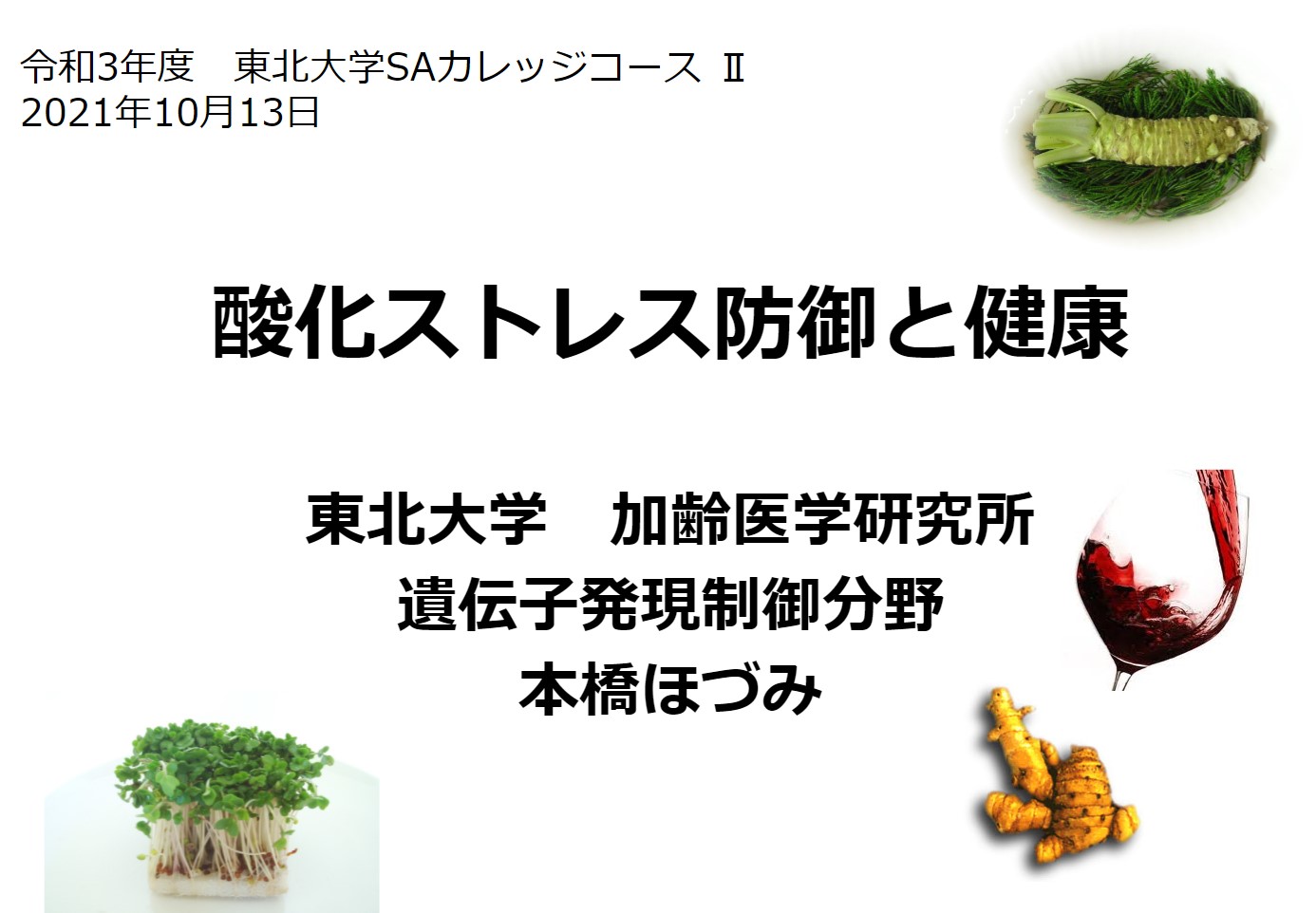 10月13日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第7回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所 副所長・加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野・スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長 本橋ほづみ(もとはしほづみ)教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。
10月13日、SAカレッジ21年度コースⅡ 第7回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所 副所長・加齢制御研究部門遺伝子発現制御分野・スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長 本橋ほづみ(もとはしほづみ)教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。
酸化ストレス応答は、酸素呼吸を行う生物にとって生体防御の重要な柱です。
本橋先生は、酸化ストレス応答を担う制御タンパク質NRF2が環境ストレスに対する転写因子であることを世界に先駆けて発見した、酸化ストレス応答研究の第一人者です。
最近、NRF2を活性化させる食品中の化学物質の一部に、新型コロナウイルスに対する抗ウイルス活性の存在が報告されています。
今回の講義では感染症のコントロールを含めて、健康長寿の実現のためにKEAP1-NRF2制御系の適切な利用が有効であること、また体の酸化ストレス応答や炎症の状態を診断する呼気診断システムの開発最前線についてもお話いただきました。この検査方法は多くのテレビ・新聞等のメディアに取り上げられたきわめて注目度の高いものです。
認知症治療から新型コロナ対策までの研究最前線について解説いただきました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。


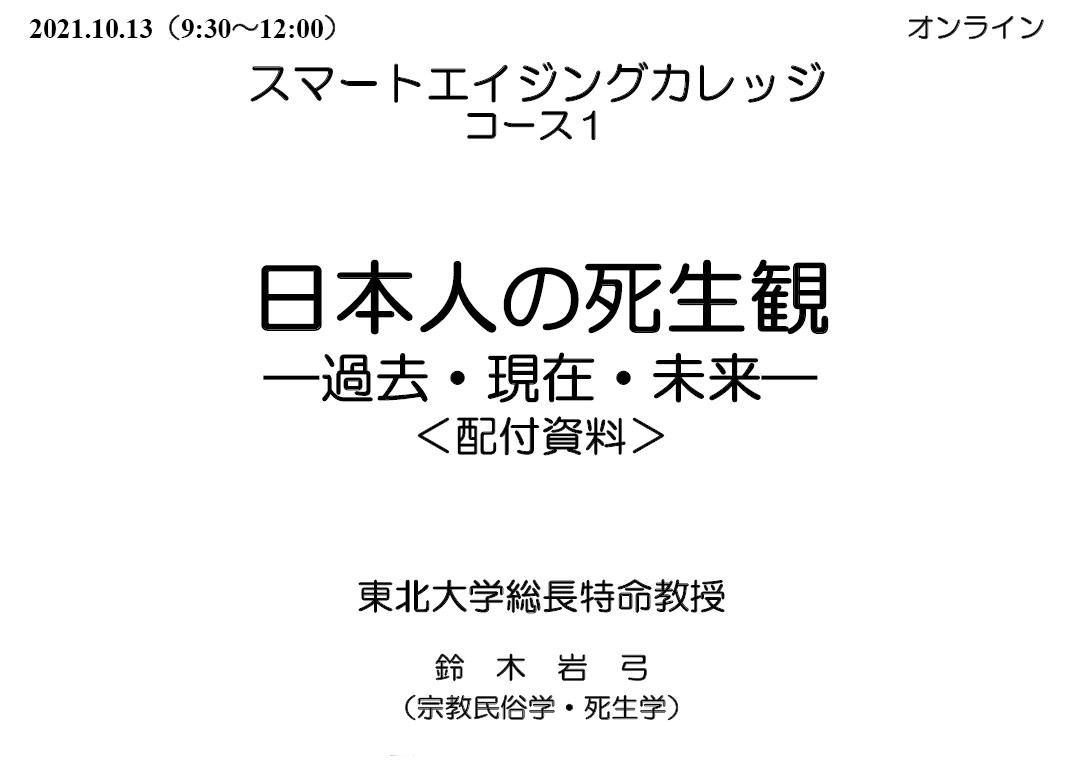 10月13日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第7回月例会開催されました。講師は、教養教育院 鈴木 岩弓(すずき いわゆみ)総長特命教授・名誉教授。講義テーマは「日本人の死生観—過去・現在・未来—」でした。
10月13日、SAカレッジ21年度コースⅠ 第7回月例会開催されました。講師は、教養教育院 鈴木 岩弓(すずき いわゆみ)総長特命教授・名誉教授。講義テーマは「日本人の死生観—過去・現在・未来—」でした。 本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環であります。
本カレッジは、東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターの村田裕之特任教授監修のもと、介護の質を向上させるためにチャームケアが取り組んでいる「認知症改善プロジェクト」の一環であります。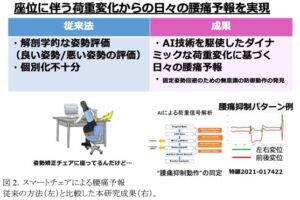
 シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第13回が公開されました。
シニア向け旅行サービスNo.1のクラブツーリズムと東北大学ナレッジキャストとのコラボによる「旅と人生を楽しむ スマート・エイジング術」の連載第13回が公開されました。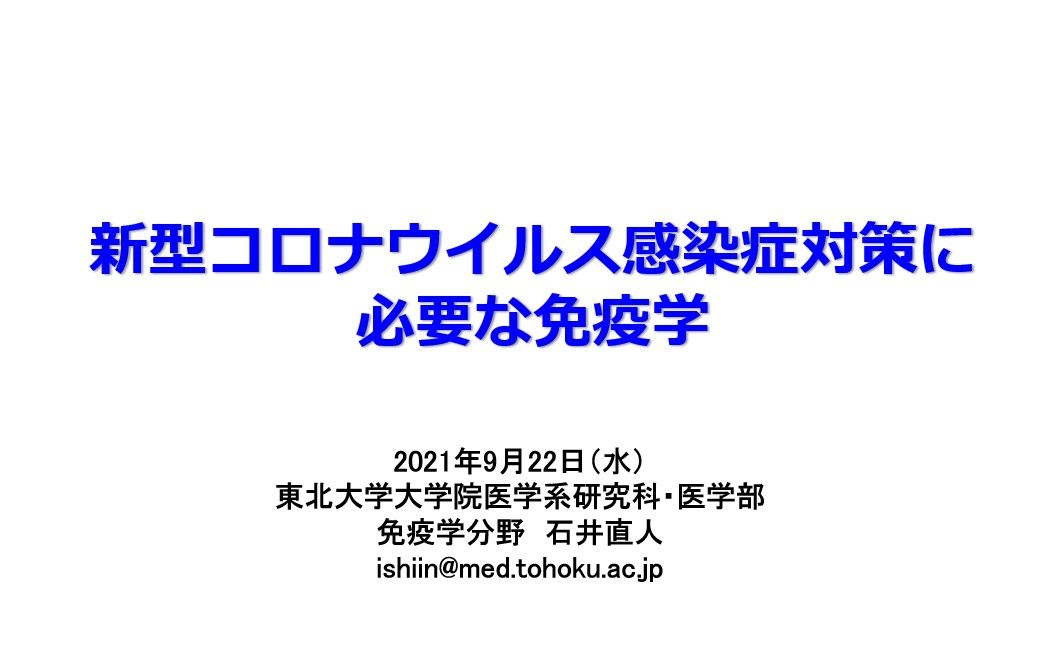 9月22日、SAカレッジ21年度コースⅢ 第6回月例会開催されました。講師は、医学系研究科免疫学分野 医学部医学科長 石井 直人(いしいなおと)教授。講義テーマは「新型コロナウイルス感染症対策に必要な免疫学」でした。
9月22日、SAカレッジ21年度コースⅢ 第6回月例会開催されました。講師は、医学系研究科免疫学分野 医学部医学科長 石井 直人(いしいなおと)教授。講義テーマは「新型コロナウイルス感染症対策に必要な免疫学」でした。