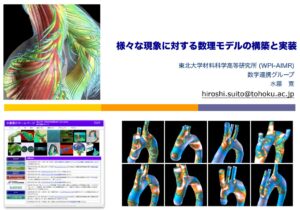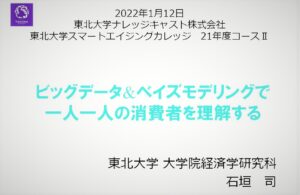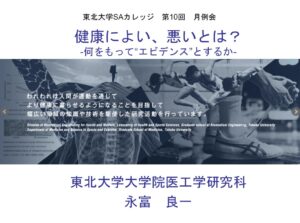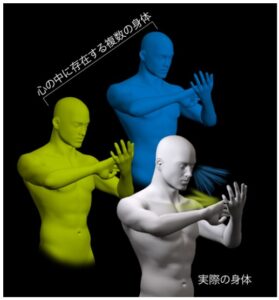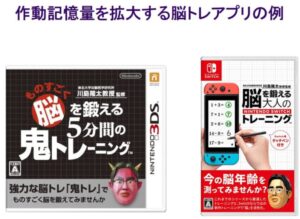SAカレッジ21年度 コースⅠ 第11回月例会 参加者の声
本間 経康 教授「計算知能技術による医用機器の高性能化」
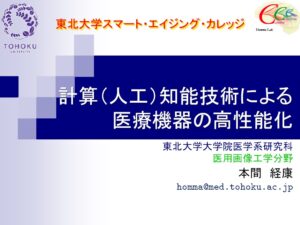 2022年2月9日、SAカレッジ21年度コースⅠ第11回月例会開催されました。講師は、スマート・エイジング学際重点研究センター 人間福祉工学研究部門長、創生応用医学研究センター 副センター長(AI応用医学部門長)本間 経康(ほんま のりやす)教授。講義テーマは「計算知能技術による医用機器の高性能化」でした。
2022年2月9日、SAカレッジ21年度コースⅠ第11回月例会開催されました。講師は、スマート・エイジング学際重点研究センター 人間福祉工学研究部門長、創生応用医学研究センター 副センター長(AI応用医学部門長)本間 経康(ほんま のりやす)教授。講義テーマは「計算知能技術による医用機器の高性能化」でした。
本月例会で、最近隆盛の人工知能AIの基盤技術の1つである機械学習の医療応用について説明いただきました。
特に人工神経回路網を用いた深層学習の得意分野である医用画像診断への応用、例えばアルツハイマー型認知症の画像診断例や、適応的数理モデルを用いた治療装置の知能化など、臨床応用に向けた具体例を紹介していただきました。
また、深層学習と従来の数理モデルとの相違に着目し、医療応用に際しての注意点やその対策も考察、さらに人工知能を製造・開発する立場や使用する立場の医療従事者だけでなく、使用される側の患者の意見など様々な立場から期待される機能や運用法など、実装に向けた最近の動向についても紹介いただきました。
本間先生は大学発ベンチャーZelowaとCOVID-19感染対策の共同研究を通して、人工知能の社会実装も推進しています。実ビジネスに直結する研究の最前線のお話が聴ける貴重な機会となりました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。