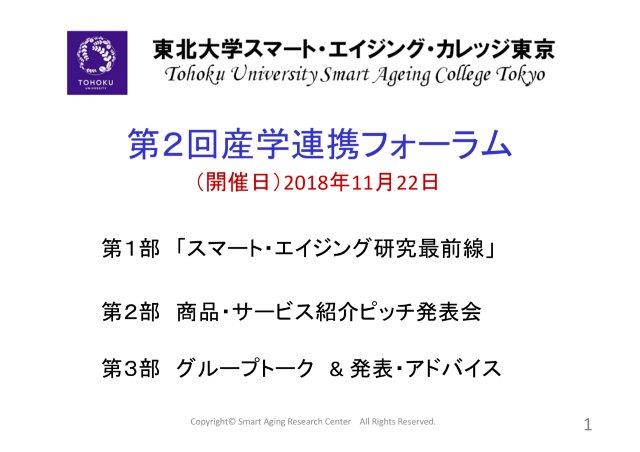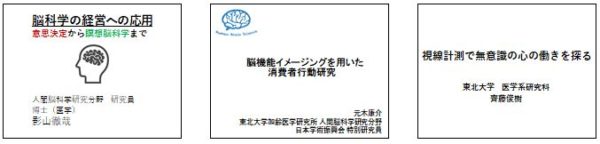SAC東京活動(36 / 61ページ)
SAC東京4期コースⅠ第7回月例会 参加者の声
12月20日、SAC東京コースⅠ第7回月例会 参加者の声
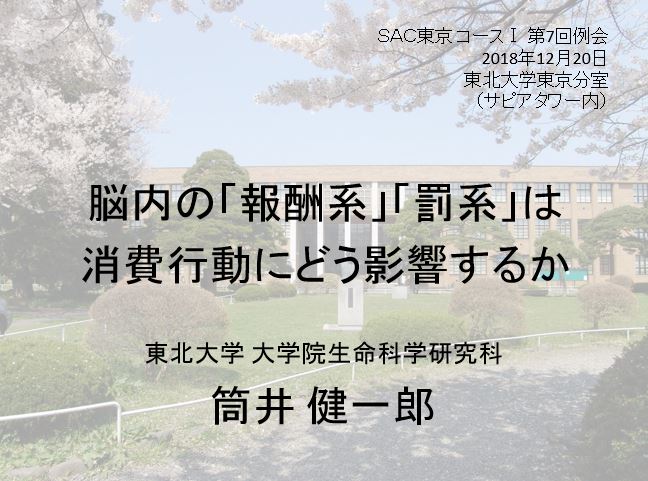
12月20日、SAC東京4期 第7回月例会開催されました。講師は、大学院生命科学研究科 脳情報処理分野の筒井 健一郎教授。講義テーマは「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。
私たちの脳の神経ネットワークには元気ややる気を感じさせる「報酬系」と、恐怖や不安を感じさせる「罰系」があります。また、これらの働きに関わる脳内物質が、ドーパミンやセロトニン等のモノアミンと呼ばれる物質です。
近年、これら「報酬系」「罰系」が、人の行動に対して様々な影響を与えていることがわかってきました。
ビジネス現場では消費者の潜在的な消費性向を理解し、購買行動を理解することが不可欠です。そのためには脳内の「報酬系」「罰系」の仕組みの理解が極めて有用です。
今回は、複数の消費行動事例を取り上げ、脳の「報酬系」「罰系」が、どのように働くのかを事例を踏まえてお話しいただきました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
SAC東京4期コースⅡ第7回月例会 参加者の声
12月20日、SAC東京コースⅡ第7回月例会 参加者の声
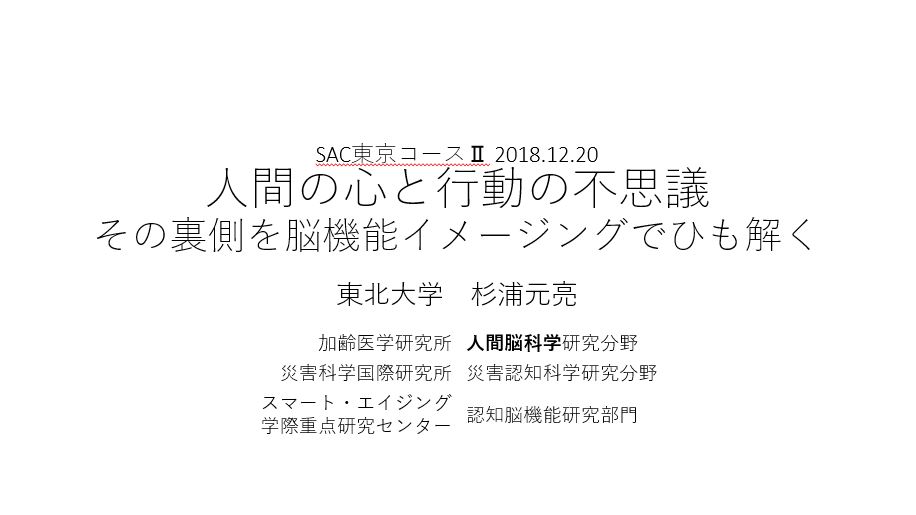 12月20日、SAC東京4期 第7回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所・災害科学国際研究所の杉浦元亮教授。講義テーマは「人間の心と行動の不思議 ~その裏側を脳機能イメージングでひも解く」でした。
12月20日、SAC東京4期 第7回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所・災害科学国際研究所の杉浦元亮教授。講義テーマは「人間の心と行動の不思議 ~その裏側を脳機能イメージングでひも解く」でした。
人間の行動の裏側には様々な心の働きがあります。現代はその働きを脳機能イメージングでかなり明らかにできるようになりました。
例えば、実際に顔を合わせての面談とビデオ画面で行う面談とでは、脳の使い方が異なることがわかっています。E-ラーニングは多くの人に情報提供するのに向いていますが、ライブの魅力を超えられない理由がここにあります。
また、自分の顔が魅力的に見える時、「場」を認知する脳領域が活性化することがわかっています。これより、「場」のつくりかたによって顧客の意識や行動が変わることが脳科学的にもわかります。
今回の講義では、脳機能イメージングを使って、人の行動とその裏側にある心の動きをひも解くための手法をお話しいただきました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
SAC東京4期コースⅠ第6回月例会 参加者の声
10月25日、SAC東京コースⅠ第6回月例会 参加者の声
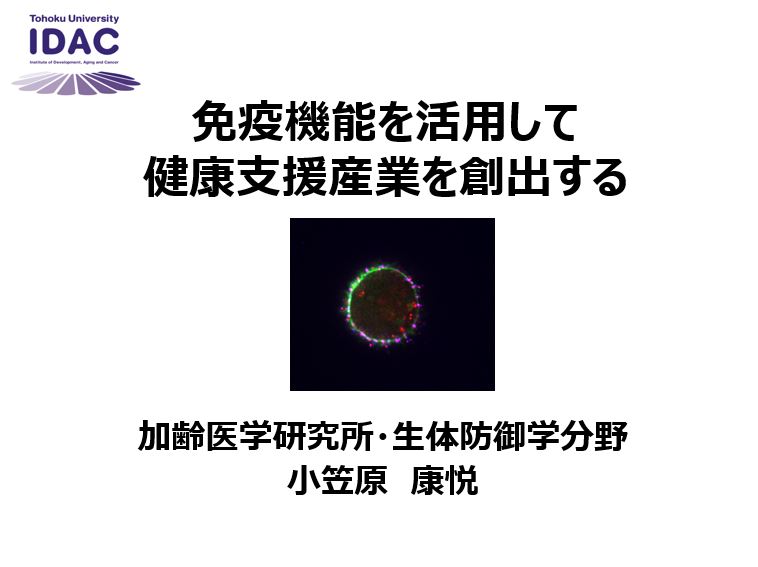
10月25日、SAC東京4期 第6回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所 生体防御学分野の小笠原康悦教授。講義テーマは「免疫機能を活用して健康支援産業を創出する」でした。
免疫のしくみを応用した産業として抗体医薬が有名で、今年度のノーベル医学生理学賞を受賞した本庶佑先生のがん免疫療法もそのひとつになります。
抗体医薬以外にも免疫を応用した産業化の大きな可能性があります。
例えば、がん(抗原)にぴったり一致したT細胞の「受容体(抗体)」が選択されることによって、がんをやっつけることができます。これが免疫の働きです。
T細胞受容体は、10の18乗(100万テラバイト)という膨大な数の「レパートリー」と呼ばれる複数の形を持っています。この多様性に富む仕組みのために、私たちの体はどんな異物や病原体へも対応できます。
このT細胞受容体の「レパートリー」を解析することで、生まれてから後天的に感染した病気やがんなどの刻々と変化している身体の状態を計測できるのです。
この原理を用いて低コストでのモニタリング商品が実用化できれば、遺伝子検査以上に精度の高い健康管理商品として健康関連市場に大きなインパクトを与えると予想されます。
今回の月例会では、こうした小笠原先生の研究最前線をご紹介いたしました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。