SAカレッジ21年度 コースⅡ第2回月例会 参加者の声
村田 裕之 特任教授「シニア市場とスマート・エイジング・ビジネス② ~日常消費以外にどんな消費の可能性があるのか~」
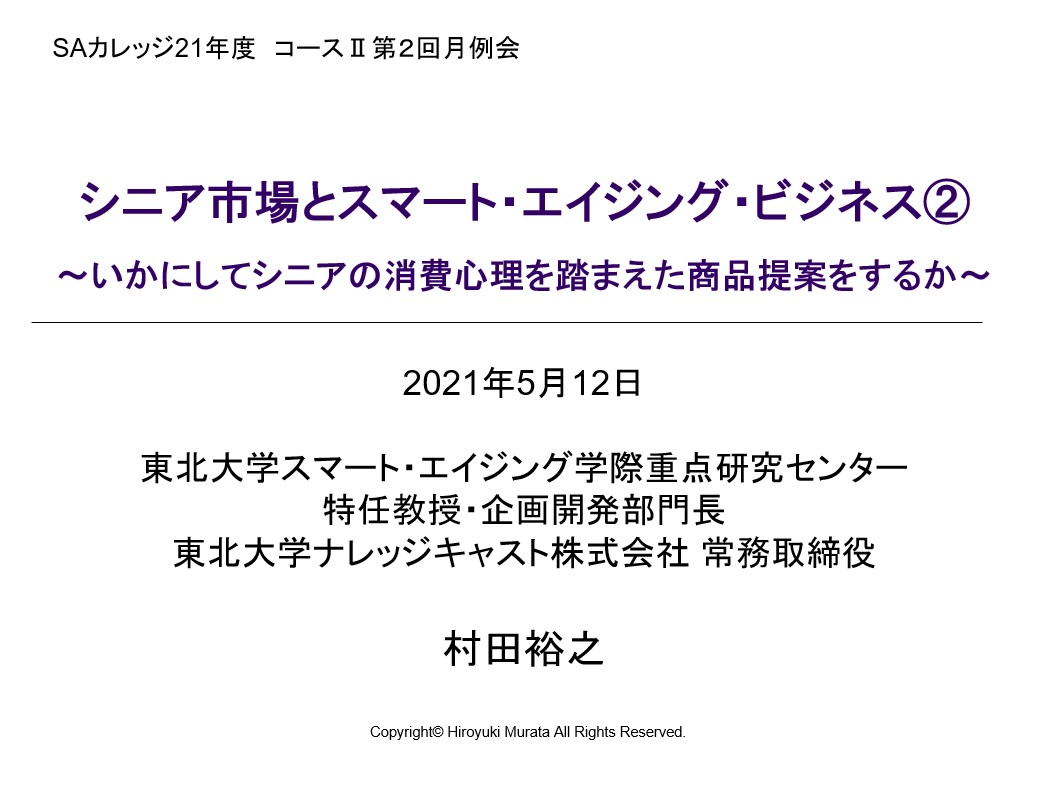 5月12日、コースⅡ第2回月例会開催されました。講師は、スマート・エイジング学際重点研究センター企画開発部門長、東北大学ナレッジキャスト常務取締役 村田 裕之(むらた ひろゆき)特任教授。講義テーマは「シニア市場とスマート・エイジング・ビジネス② ~日常消費以外にどんな消費の可能性があるのか~」でした。
5月12日、コースⅡ第2回月例会開催されました。講師は、スマート・エイジング学際重点研究センター企画開発部門長、東北大学ナレッジキャスト常務取締役 村田 裕之(むらた ひろゆき)特任教授。講義テーマは「シニア市場とスマート・エイジング・ビジネス② ~日常消費以外にどんな消費の可能性があるのか~」でした。
そもそもシニア層は若年層より資産が多くあるのに、なぜ、それが消費に回りにくいのでしょうか?
その最も大きな理由は、病気・介護など老後に対する漠然とした不安があるからです。人は将来に対して不安があると、いざという時のために備えるため、財布のひもが固めになり、普段はお金を使わなくなるのです。
シニアの資産を消費に促すには、「漠然とした将来不安」の解消につながる価値の提案が必要です。別の言い方では、資産を使ってでも「必要だと思わせる説得力」「お金では買えないもの(健康・時間・楽しさ・喜び等)を手に入れたいという気持ちに働きかけること」等が重要といえます。
コースⅡでは、そうしたアプローチをいくつかお話しいただき、シニアビジネスの可能性を知りたい方は必聴の講義となりました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

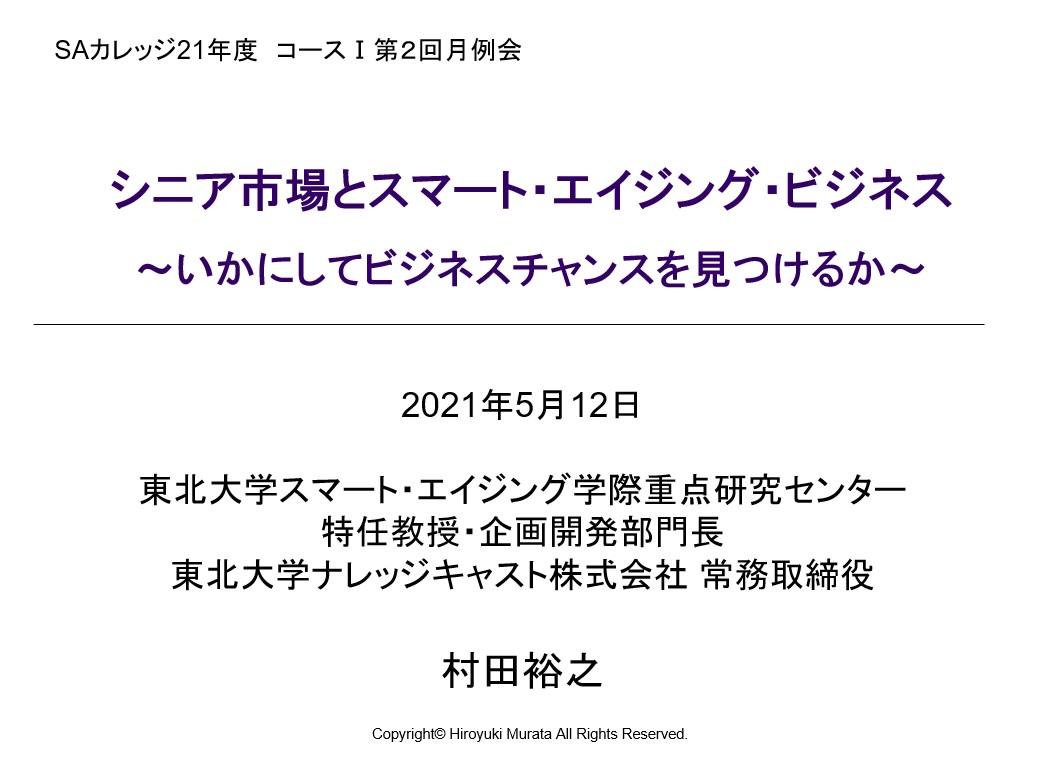
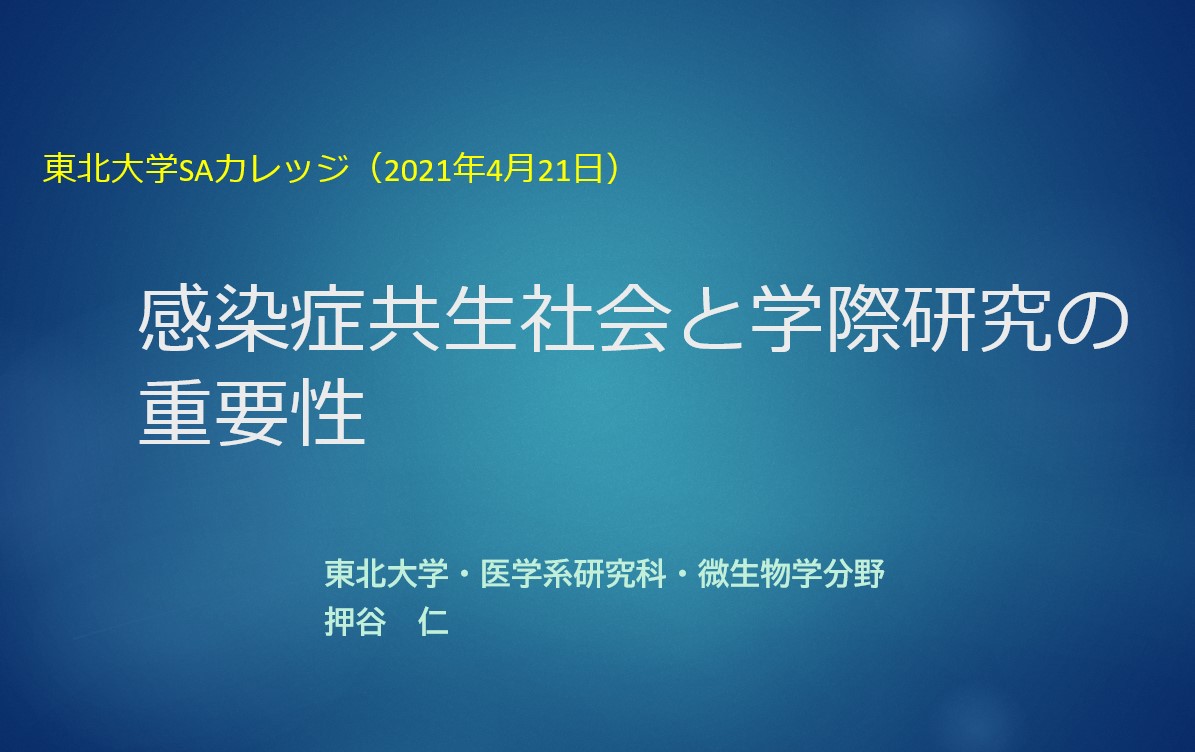
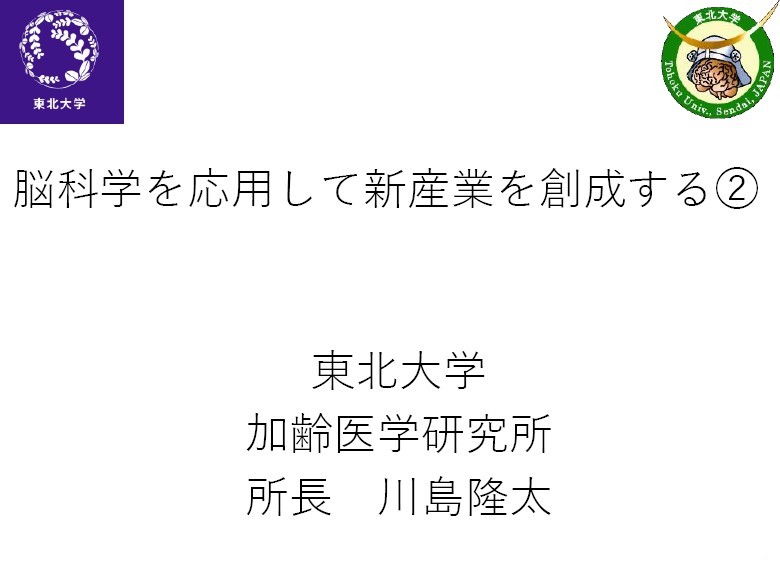
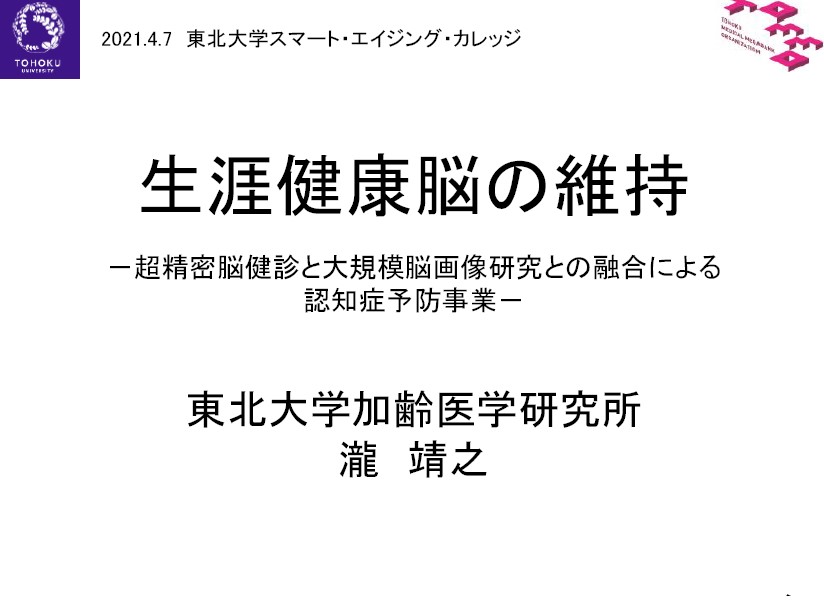
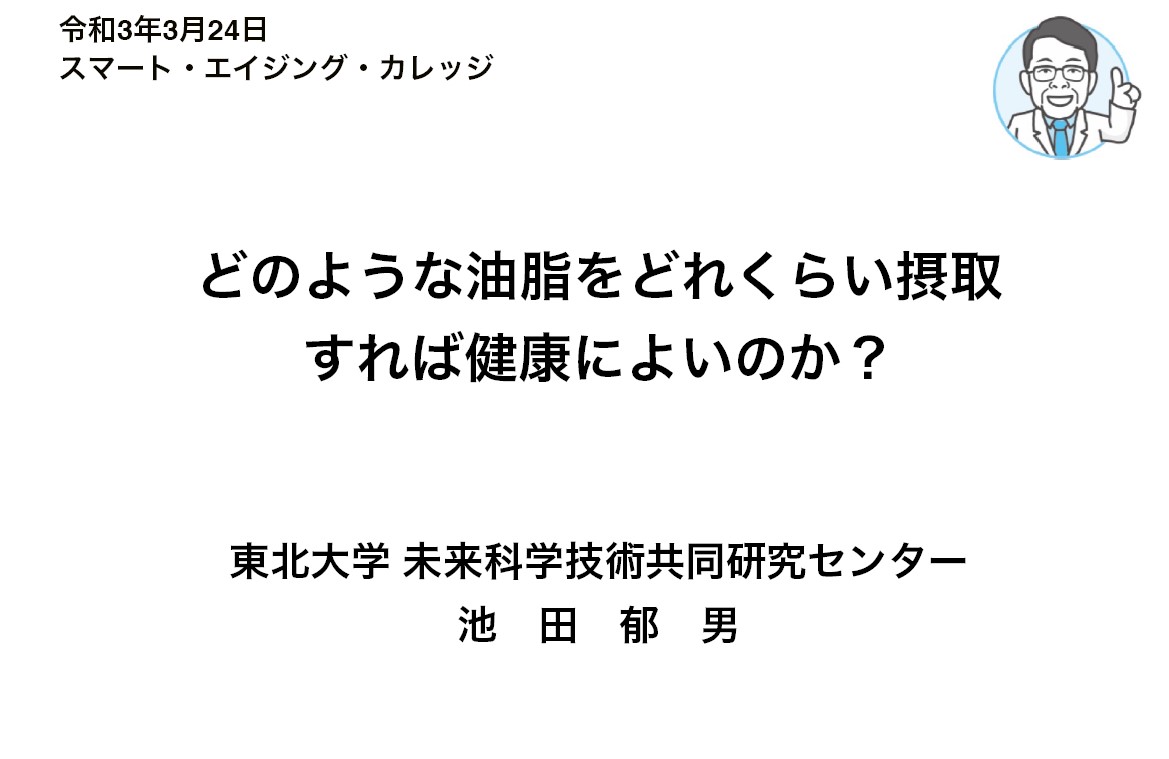 3月24日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は未来科学技術共同研究センター 池田 郁男(いけだ いくお)教授。講義テーマは「どのような油脂をどれくらい摂取すれば健康によいのか?」でした。
3月24日、SAC東京6期 第12回月例会開催されました。講師は未来科学技術共同研究センター 池田 郁男(いけだ いくお)教授。講義テーマは「どのような油脂をどれくらい摂取すれば健康によいのか?」でした。