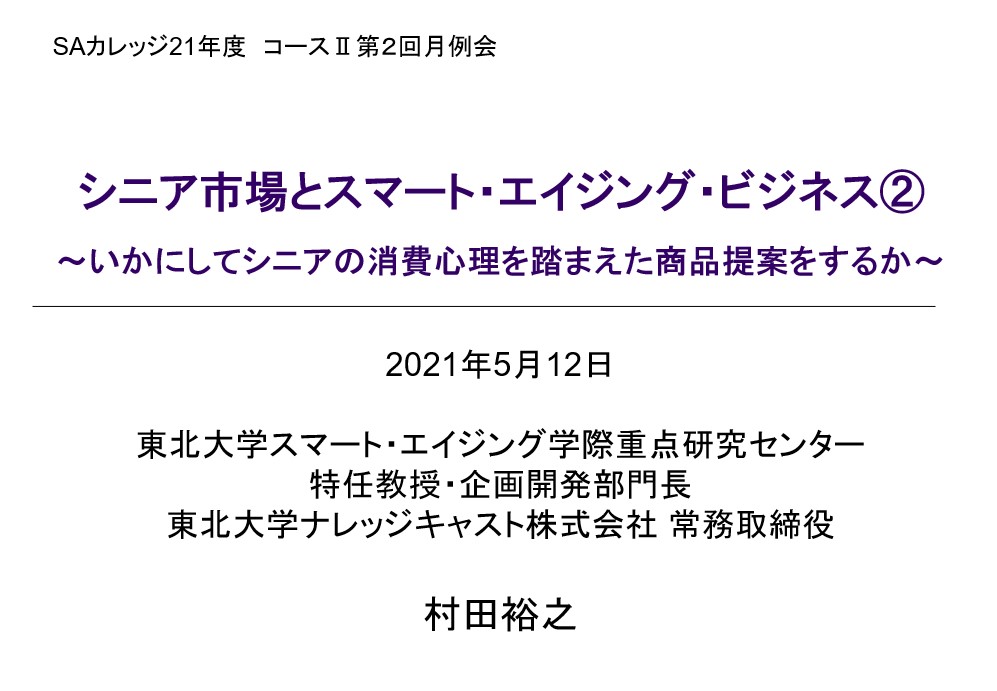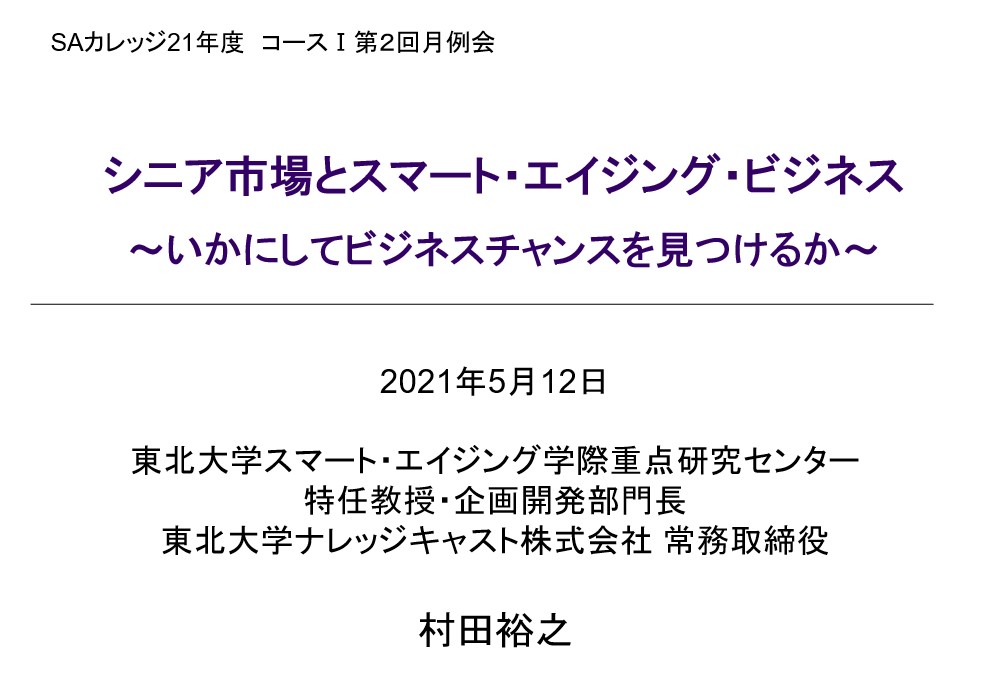SAカレッジ22年度 コースⅡ第3回月例会は、坂井信之教授です!
わが国における食心理学のパイオニア
 SAカレッジ22年度 コースⅡ第3回月例会は、坂井信之教授の「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」です。
SAカレッジ22年度 コースⅡ第3回月例会は、坂井信之教授の「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」です。
坂井先生は応用心理学がご専門で、日々の生活に役立つ心理学を研究されています。また文学研究科では、「おいしさを知覚する人間の仕組み(知覚、感情、認知、社会、健康)」「購買行動とヒトのモノの知覚の仕組み」についての授業をされています。
また、産学連携として「ネスカフェ ゴールドブレンド」50周年記念「Thanks Coffee」プロジェクト第二弾「コーヒーの香りと人間の行動変容」に関する日本初の実験を実施、これは香りと人の親切行動の関係を心理学的に調査した事例となります。
そんな坂井先生ですが、SAカレッジコースⅡ第3回月例会では、食についての見込み違いについて解説されます。例えば「おいしい食品」という商品を開発しても、消費者がそのように受け取ってくれるとは限りません。商品提供側の意図と異なる受け取り方をされたが予想以上に売れてしまった、だが、原因がよくわからないというケース。
この結論は「人はおいしさを舌で味わっているわけではない」「食品自体においしさが含まれているのではない」ということになります。人がなぜそれを食べるのか、なぜそれを選ぶのか、判断基準は味覚や嗅覚と思われがちですが、マズローの欲求5段階説の図式で表すと階層ごとに欲求は異なり、視覚や聴覚あるいは五感全てが大きく影響しています。このことを心理学・脳科学の観点でお話していただきます。
また、消費者は商品の何に注目して購入を決定するのかも考察します。どのようにその商品を評価するのか。さらに、その商品に対する印象をどのように形成し、次の商品購入の基礎情報とするのか、などについてのお話しがあります。これらの知識は、食品はもちろんのこと、日用品やサービスにも適用でき、宣伝広告やマーケティング戦略の計画立案にも適用できます。
「研究の最終目標は「『幸せ』になる方法をみつける」ことである」という坂井先生の講義と質疑セッション、非常に楽しみです!


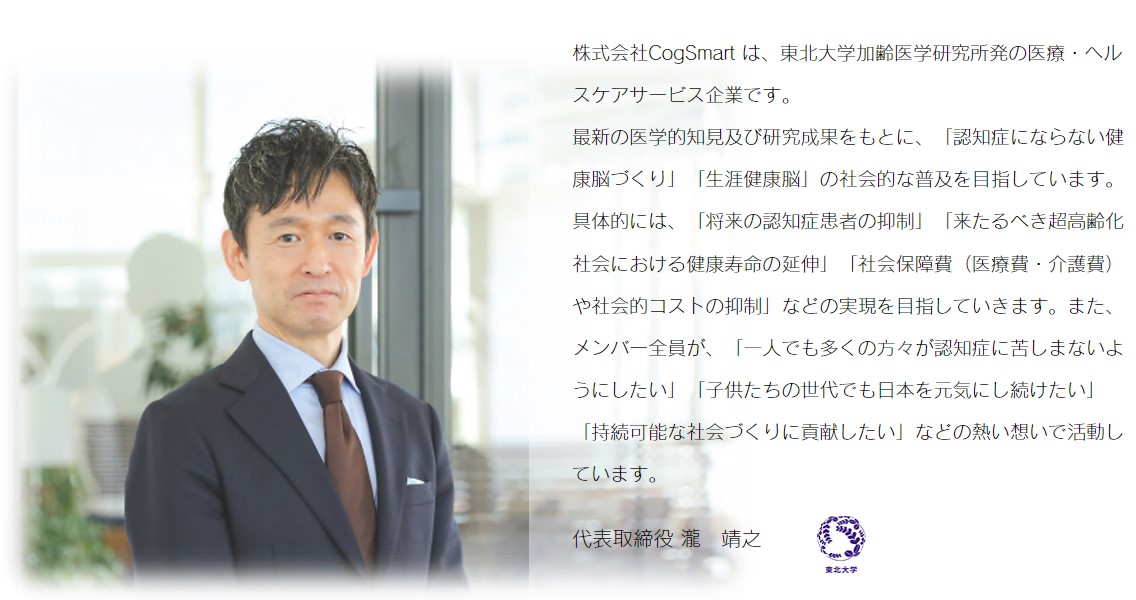
 2022年5月26日、SAカレッジ22年度 第1回参加企業ピッチ&交流会が開催されました。交流会は村田特任教授からの趣旨説明から始まりました。
2022年5月26日、SAカレッジ22年度 第1回参加企業ピッチ&交流会が開催されました。交流会は村田特任教授からの趣旨説明から始まりました。