「参加者の声」の記事一覧(32 / 36ページ)
SAC東京コースⅡ第7回月例会 参加者の声
10月18日開催 SAC東京コースⅡ第7回月例会 参加者の声
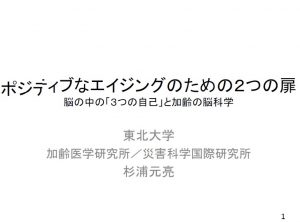 10月18日、SAC東京2期 第7回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所 災害科学国際研究所 兼務 杉浦元亮教授。講義テーマは、「ポジティブなエイジングのための2つの扉~脳の中の『3つの自己』と加齢の脳科学」でした。
10月18日、SAC東京2期 第7回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所 災害科学国際研究所 兼務 杉浦元亮教授。講義テーマは、「ポジティブなエイジングのための2つの扉~脳の中の『3つの自己』と加齢の脳科学」でした。
杉浦先生は社会脳科学研究のパイオニアで、「自己」脳研究の第一人者です。人は齢を取るにつれ、ネガティブになりがちです。心身の衰えを超えてポジティブに生きるにはどうすればよいか。今回の講義では、脳科学の観点から、高齢者が陥りがちなネガティブ志向をブレークスルーするヒントをお話頂きました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
SAC東京コースⅡ第6回月例会 参加者の声
9月21日開催 SAC東京コースⅡ第6回月例会 参加者の声
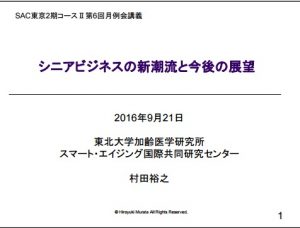 9月21日、SAC東京2期 第6回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所スマート・エイジング国際共同研究センター 村田裕之特任教授。講義テーマは、「シニアビジネスの新潮流と今後の展望」でした。
9月21日、SAC東京2期 第6回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所スマート・エイジング国際共同研究センター 村田裕之特任教授。講義テーマは、「シニアビジネスの新潮流と今後の展望」でした。
村田先生は「アクティブシニア」「スマートシニア」「スマート・エイジング」などのコンセプト提唱者であり、多くの民間企業と常に時代の一歩先を行くシニアビジネスの創出に携わってきました。
今回の講義では、シニアビジネスに関わる最近の話題について、村田先生独自の見方・考え方やビジネスチャンス探索につながるヒントをお話されました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
SAC東京コースⅠ第6回月例会 参加者の声
9月21日開催 SAC東京コースⅠ第6回月例会 参加者の声
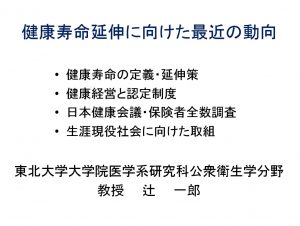 9月21日、SAC東京2期 第6回月例会が開催されました。講師は生活習慣病・老化の疫学、健康寿命がご専門の医学系研究科 副研究科長 東北メディカルメガバンク機構予防医学・疫学部門長の辻一郎教授。講義テーマは「健康寿命延伸に向けた最近の動向」でした。
9月21日、SAC東京2期 第6回月例会が開催されました。講師は生活習慣病・老化の疫学、健康寿命がご専門の医学系研究科 副研究科長 東北メディカルメガバンク機構予防医学・疫学部門長の辻一郎教授。講義テーマは「健康寿命延伸に向けた最近の動向」でした。
辻先生は健康寿命の提唱者であり、著書「健康長寿社会を実現する〜2025年問題と新しい公衆衛生戦略の展望」や政府の各種審議会委員としての発言を通じて政策提言を活発に行っています。健康寿命延伸政策の一連の流れを独自の視点でまとめるとともに今後の展望についてお話しされました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

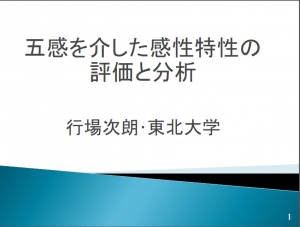 11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は、文学研究科心理学講座 行場次朗 教授。講義テーマは、「五感を介した感性特性の評価と分析」でした。
11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は、文学研究科心理学講座 行場次朗 教授。講義テーマは、「五感を介した感性特性の評価と分析」でした。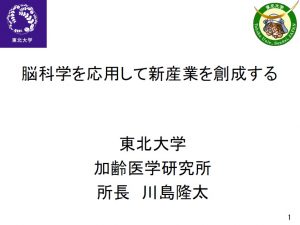 11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は加齢医学研究所所長、スマート・エイジング国際共同研究センター長の川島隆太教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する」でした。
11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は加齢医学研究所所長、スマート・エイジング国際共同研究センター長の川島隆太教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する」でした。 10月18日、SAC東京2期 第7回月例会が開催されました。講師は加齢医学研究所副所長 加齢制御研究部門 遺伝子発現制御分野の本橋ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。
10月18日、SAC東京2期 第7回月例会が開催されました。講師は加齢医学研究所副所長 加齢制御研究部門 遺伝子発現制御分野の本橋ほづみ教授。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」でした。