SAC東京活動(51 / 61ページ)
SAC東京コースⅠ第7回月例会 事務局レポート
10月18日開催 SAC東京コースⅠ第7回月例会 事務局レポート
 今回の講師は加齢医学研究所副所長の本橋ほづみ教授です。専門は遺伝子発現制御分野です。SAC初となる女性講師ということもあり会場に流れる柔らかな空気を感じながら講義が始まりました。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」です。
今回の講師は加齢医学研究所副所長の本橋ほづみ教授です。専門は遺伝子発現制御分野です。SAC初となる女性講師ということもあり会場に流れる柔らかな空気を感じながら講義が始まりました。講義テーマは「酸化ストレス防御と健康」です。
「酸化ストレス防御」を一筋に研究をしてきた本橋教授の講義内容は以下の6項目について行われました。
1. 酸素が生命にもたらした功罪
2. 酸化ストレスは多くの病気の原因になっている
3. 毒とは?親電子性物質とは?
4. 解毒のはたらき
5. 生体防御機構を担うタンパク質NRF2
6. NRF2を活性化させると健康増進につながる
SAC東京コースⅡ第7回月例会 事務局レポート
10月18日開催 SAC東京コースⅡ第7回月例会 事務局レポート
 東北大学加齢医学研究所と災害科学国際研究所の2つの研究所に兼務している杉浦元亮教授です。「給与が2倍というわけではありません」と参加者の緊張をほぐしながら、4つのコンテンツの説明から講義は始まりました。
東北大学加齢医学研究所と災害科学国際研究所の2つの研究所に兼務している杉浦元亮教授です。「給与が2倍というわけではありません」と参加者の緊張をほぐしながら、4つのコンテンツの説明から講義は始まりました。
脳機能イメージングで何を見るか
脳機能イメージングで見るものは2つの種類の信号です。一つは、神経細胞群の電気活動で、脳波や脳磁図で見ます。もう一つは、神経細胞群のエネルギー需要(血液量増加)で、陽電子断層画像法(PET)、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)、近赤外分光法(NIRS)で見ます。本日のメインはfMRIです。一般に病院で行うMRIは脳の形をみますが、fMRIは脳の機能を見ます。
SAC東京コースⅡ第7回月例会 参加者の声
10月18日開催 SAC東京コースⅡ第7回月例会 参加者の声
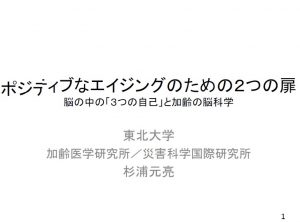 10月18日、SAC東京2期 第7回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所 災害科学国際研究所 兼務 杉浦元亮教授。講義テーマは、「ポジティブなエイジングのための2つの扉~脳の中の『3つの自己』と加齢の脳科学」でした。
10月18日、SAC東京2期 第7回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所 災害科学国際研究所 兼務 杉浦元亮教授。講義テーマは、「ポジティブなエイジングのための2つの扉~脳の中の『3つの自己』と加齢の脳科学」でした。
杉浦先生は社会脳科学研究のパイオニアで、「自己」脳研究の第一人者です。人は齢を取るにつれ、ネガティブになりがちです。心身の衰えを超えてポジティブに生きるにはどうすればよいか。今回の講義では、脳科学の観点から、高齢者が陥りがちなネガティブ志向をブレークスルーするヒントをお話頂きました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。

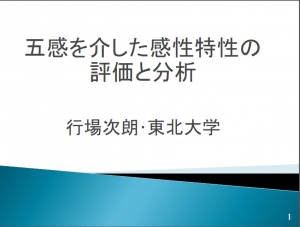 11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は、文学研究科心理学講座 行場次朗 教授。講義テーマは、「五感を介した感性特性の評価と分析」でした。
11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は、文学研究科心理学講座 行場次朗 教授。講義テーマは、「五感を介した感性特性の評価と分析」でした。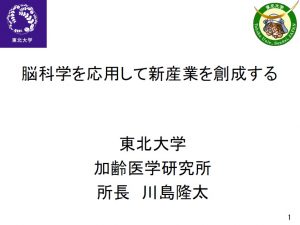 11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は加齢医学研究所所長、スマート・エイジング国際共同研究センター長の川島隆太教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する」でした。
11月24日、SAC東京2期 第8回月例会が開催されました。講師は加齢医学研究所所長、スマート・エイジング国際共同研究センター長の川島隆太教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する」でした。 第3回となる今回は、村田特任教授(コースⅡ担当)と小川事務局長(コースⅠ担当)がそれぞれのコースに分かれて、分科会の進捗状況報告、月例会講義内容の整理、設定されたテーマをもとにグループディスカッションが行われました。
第3回となる今回は、村田特任教授(コースⅡ担当)と小川事務局長(コースⅠ担当)がそれぞれのコースに分かれて、分科会の進捗状況報告、月例会講義内容の整理、設定されたテーマをもとにグループディスカッションが行われました。