SAC東京活動(46 / 61ページ)
SAC東京3期コースⅠ第2回月例会 事務局レポート
5月18日開催 SAC東京コースⅠ第2回月例会 事務局レポート
 今回の月例会は情報科学研究科応用情報科学専攻バイオモデリング論研究室の中尾光之教授による「眠る脳のバイオモデリングとQOL向上策」をテーマとした講義です。中尾教授はSAC東京に初めての登壇となります。
今回の月例会は情報科学研究科応用情報科学専攻バイオモデリング論研究室の中尾光之教授による「眠る脳のバイオモデリングとQOL向上策」をテーマとした講義です。中尾教授はSAC東京に初めての登壇となります。
中尾教授は日本の女性3人組のテクノポップユニットであるPerfume(パフューム)の関ジャニの番組に出演していた時の映像を流し、講義に入っていきました。 「複雑なダンスの行程をどう覚えているか?」という問いに対してメンバーの一人が「寝て記憶を熟成させる」と答えています。何が分からないのかが分からない状態で練習を続けるのですが、寝るとそれが明瞭に構造化して分かる様になるというのです。

 このたび、東北大学は、平成29年6月30日付けで文部科学大臣より「指定国立大学法人」の指定を受けました。東京大学、京都大学と並んでの指定です。
このたび、東北大学は、平成29年6月30日付けで文部科学大臣より「指定国立大学法人」の指定を受けました。東京大学、京都大学と並んでの指定です。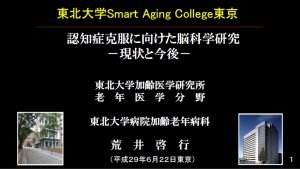 6月22日、SAC東京3期 第3回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所 脳科学部門 老年医学分野、東北大学病院老年科科長の荒井啓行教授。講義テーマは、「認知症克服に向けた先端研究の動向」でした。
6月22日、SAC東京3期 第3回月例会が開催されました。講師は、加齢医学研究所 脳科学部門 老年医学分野、東北大学病院老年科科長の荒井啓行教授。講義テーマは、「認知症克服に向けた先端研究の動向」でした。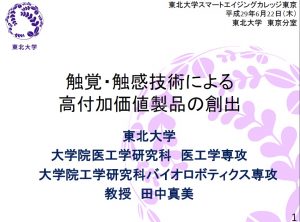 6月22日、SAC東京3期 第3回月例会が開催されました。講師は医工学研究科、医療福祉工学、バイオメカトロニクス専門の田中真美教授。講義テーマは「触覚・触感技術による高付加価値製品の創出」でした。
6月22日、SAC東京3期 第3回月例会が開催されました。講師は医工学研究科、医療福祉工学、バイオメカトロニクス専門の田中真美教授。講義テーマは「触覚・触感技術による高付加価値製品の創出」でした。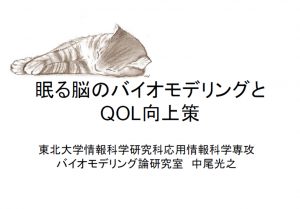 5月18日、SAC東京3期 第2回月例会が開催されました。講師は東北大学情報科学研究科 中尾光之教授。講義テーマは「眠る脳のバイオモデリングとQOL向上策」でした。
5月18日、SAC東京3期 第2回月例会が開催されました。講師は東北大学情報科学研究科 中尾光之教授。講義テーマは「眠る脳のバイオモデリングとQOL向上策」でした。 5月18日、SAC東京3期 第2回月例会が開催されました。講師は、食心理学のパイオニアである東北大学大学院文学研究科 の坂井信之教授。講義テーマは、「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。
5月18日、SAC東京3期 第2回月例会が開催されました。講師は、食心理学のパイオニアである東北大学大学院文学研究科 の坂井信之教授。講義テーマは、「消費者はどのようにしておいしさを感じているのか?」でした。