SAC東京6期コースⅡ第9回月例会 事務局レポート
東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療

コースⅡ第9回月例会は、東北メディカル・メガバンク機構長、大学院医学系研究科 医化学分野の山本雅之教授による「東北メディカル・メガバンク計画とゲノム医療」が講義テーマです。
東日本大震災で大きなダメージを受けた東北地方の創造的復興のために、東北メディカル・メガバンク機構が設立されました。最先端の未来型医療を地震と津波で被災した方々に迅速に届けたいという願いは、より健康で豊かな生活を実現し「健康長寿の国」を作る活動につながっています。「未来型医療の代表例は個別化予防と個別化医療である」ということを、被災地でやろうと決心した山本先生の講義が始まりました。


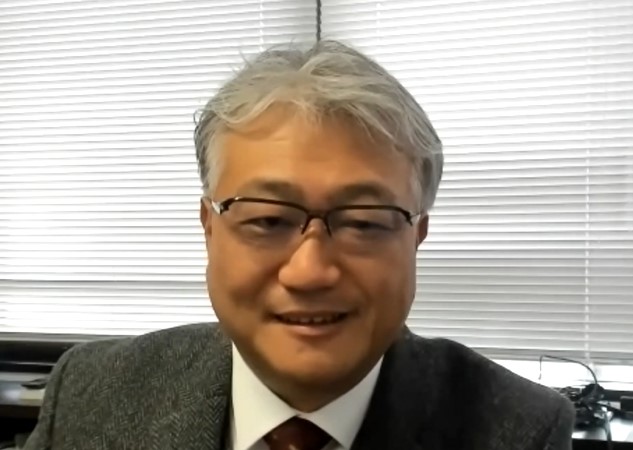
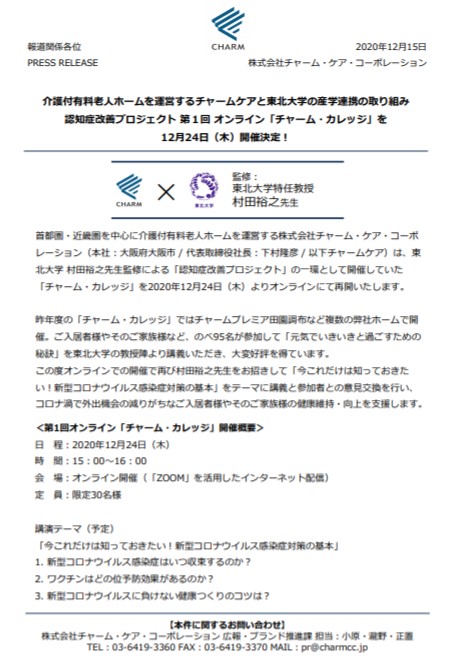
 11月25日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。講師は大学院教育学研究科の佐藤克美 准教授。講義テーマは「郷土芸能とテクノロジーを活用した地域と人の活性化」でした。
11月25日、SAC東京6期 第8回月例会開催されました。講師は大学院教育学研究科の佐藤克美 准教授。講義テーマは「郷土芸能とテクノロジーを活用した地域と人の活性化」でした。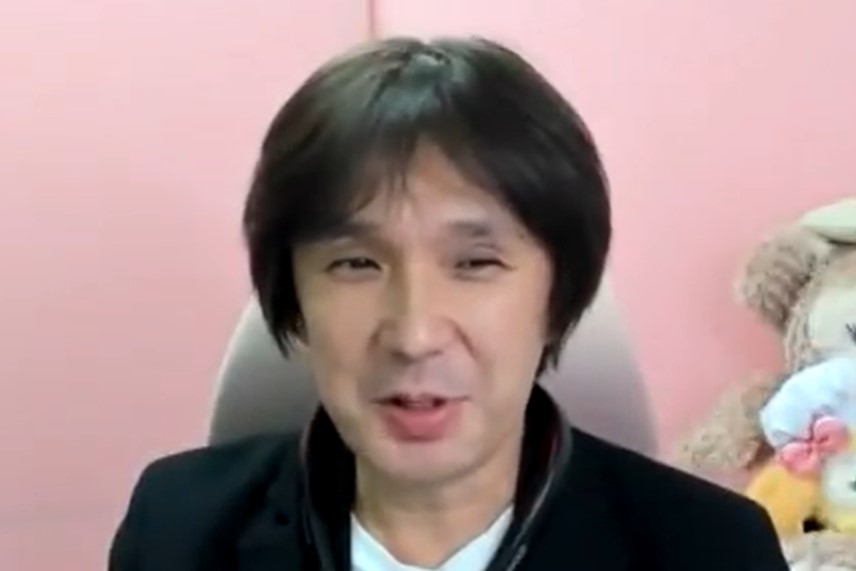
 11月25日、SAC東京6期 第1回産学連携フォーラムが開催されました。
11月25日、SAC東京6期 第1回産学連携フォーラムが開催されました。