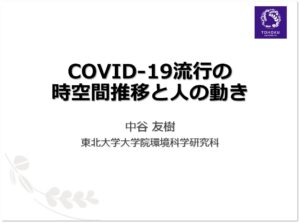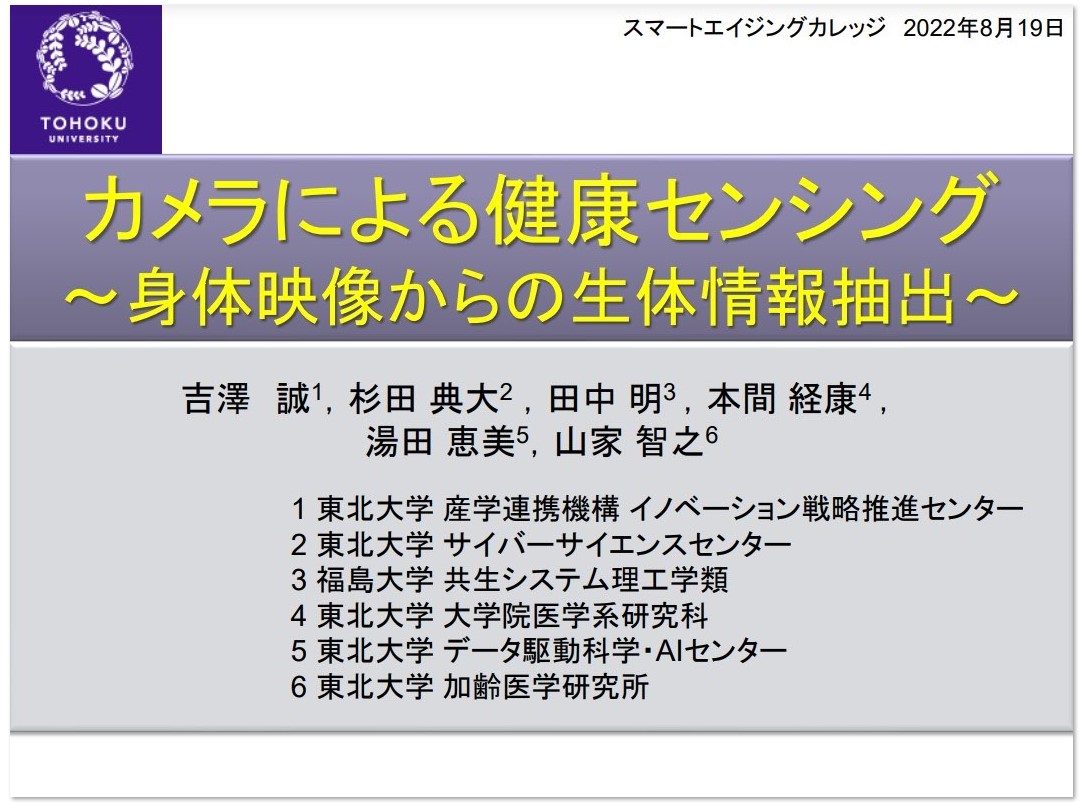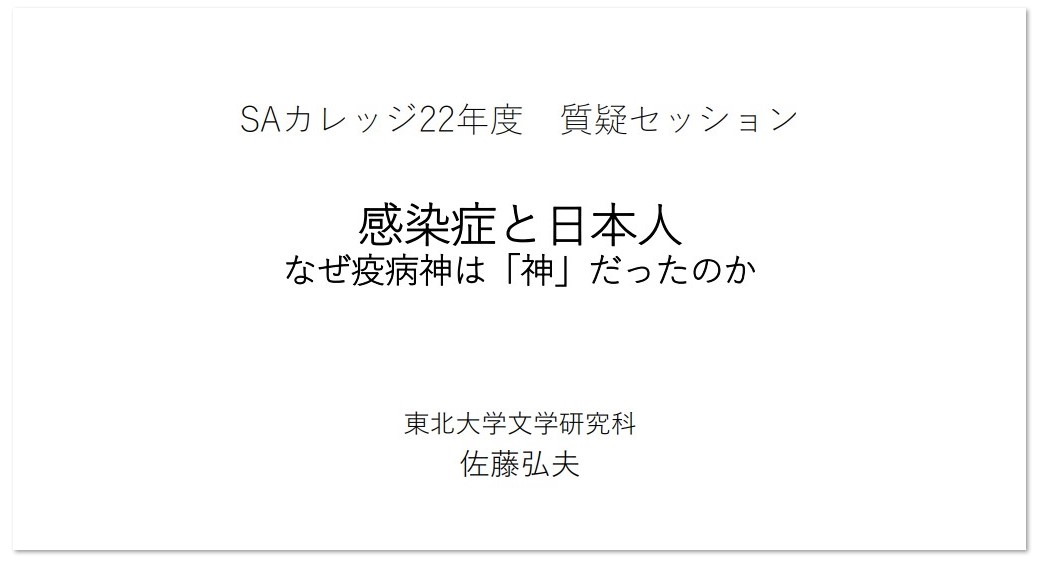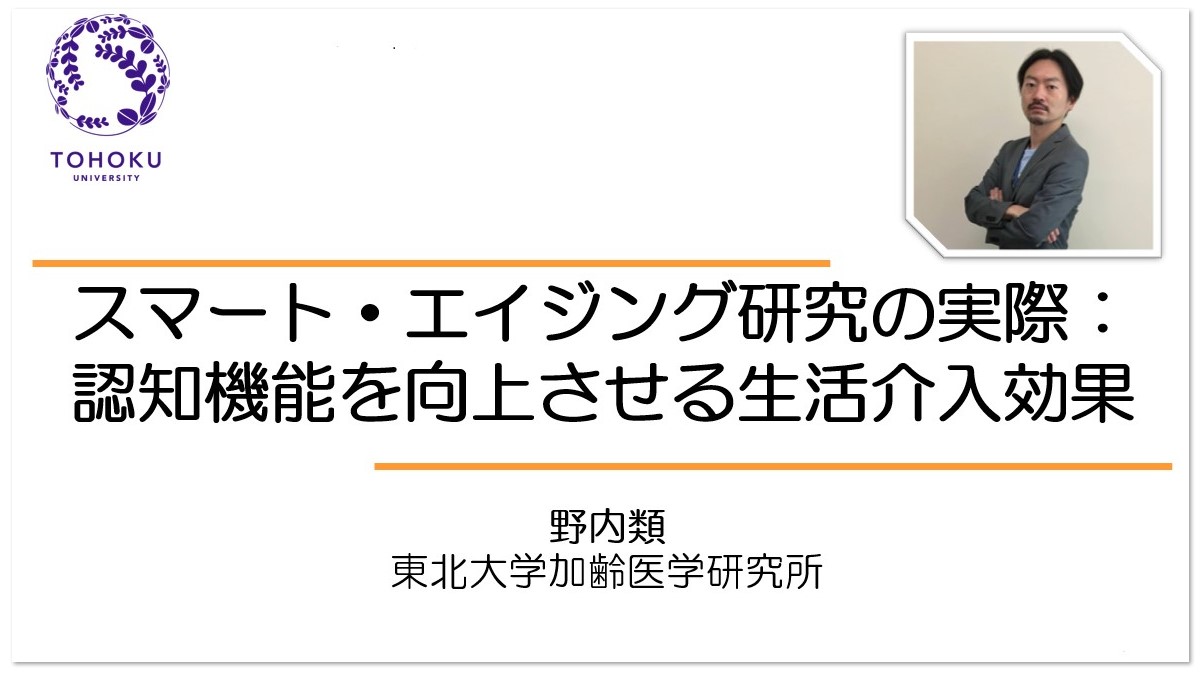SAC東京活動(4 / 61ページ)
SAカレッジ22年度 第2回参加企業ピッチ&交流会が開催されました
異業種企業とのネットワークが財産になる
 2022年9月7日、SAカレッジ22年度 第2回参加企業ピッチ&交流会がオンラインで開催されました。交流会は村田特任教授からの趣旨説明から始まりました。
2022年9月7日、SAカレッジ22年度 第2回参加企業ピッチ&交流会がオンラインで開催されました。交流会は村田特任教授からの趣旨説明から始まりました。
「この交流会の目的は、参加企業同士のコラボ活動のきっかけづくりです。本来このイベントは5月と11月に開催するだけでしたが、「参加企業同士で交流がしたい」という強いご要望をいただきましたことと、期中参加の企業様にピッチしていただく、という二つの理由から、本日行うことにしたものです。
本来、対面での開催をしたかったのですが、コロナ禍での諸般の状況を考慮してオンライン開催とさせていただきました。「いったいこのコロナ禍は、いつまで続くのか」という疑問を、コースⅢに参加されたことのある方は一度はされているんじゃないかと思います。
9月に入って感染者の数が、地域により減っているように見えますが、実は過去2年間をみても毎年気候がよくなると減少してきます。これは気候要因と言われ、要は真夏や真冬はエアコンで部屋を閉め切るため、これだけが理由ではないんですが、家庭内感染などが起きやすくなるんですね。
我々は2年前からウィズコロナを申し上げていますが、要は感染拡大期と縮小期が周期的に表れております。そのような状況で、拡大期ではおとなしく極力感染しないように行動を気を付け、縮小期が見えてきたらアクティブに動き波乗りの波に乗るようなことを身に付けないといけない、ということがこの2年半で分かってきました。
次回開催の11月は、おそらく次の波が来る前の縮小期になるかと思いますが、ぜひリアルでの開催でお会いしたいと思います。今回は残念ながらオンラインですが、盛り上がっていただき次回対面開催でリアルでの再会を喜ぶような関係性を作っていただければと思います。」という内容のお話しをしてくださいました。
参加企業ピッチでは、期中からの参加企業をメインに発表がありました。