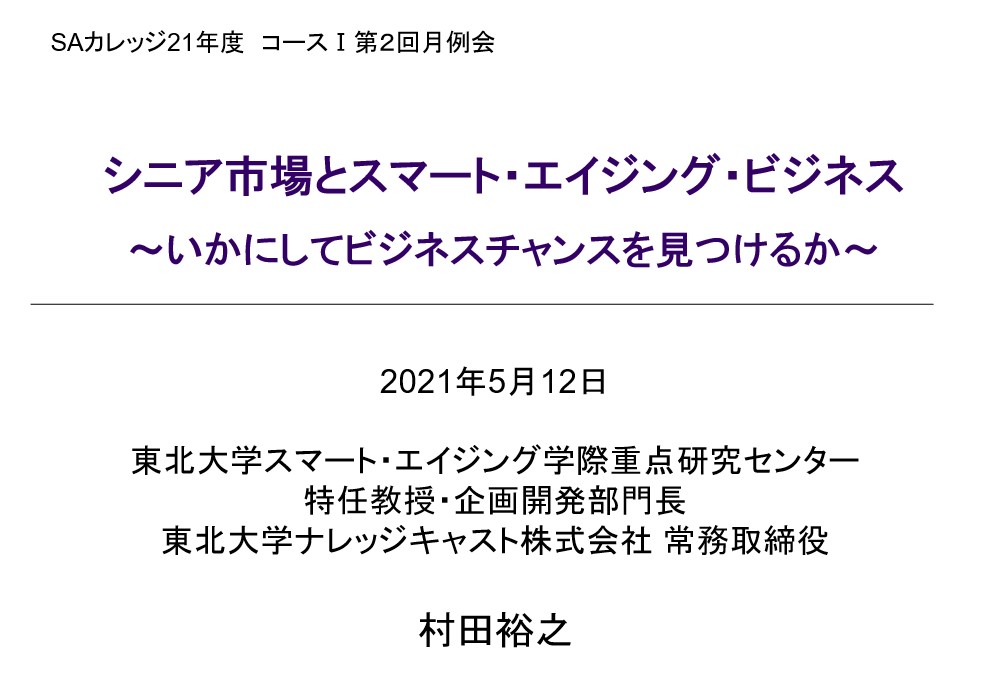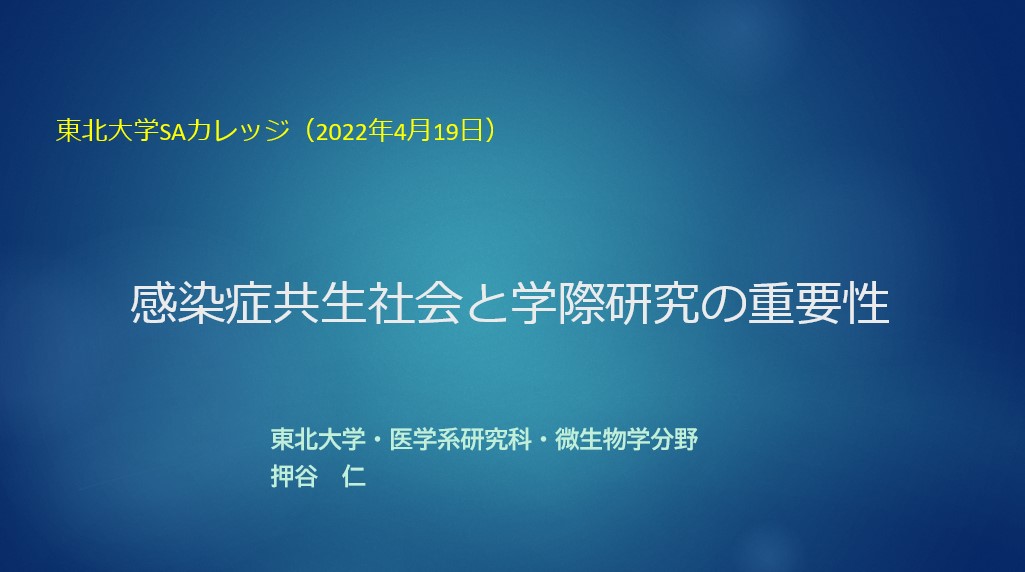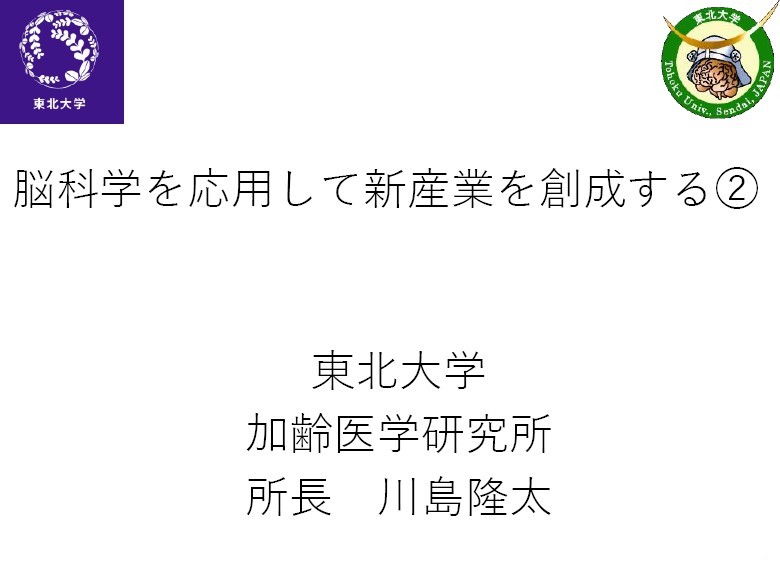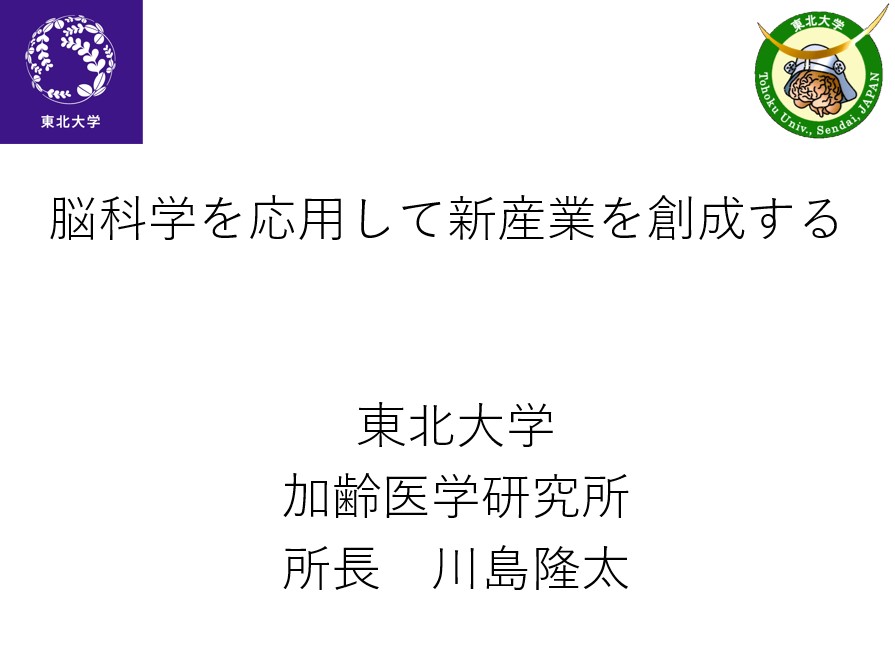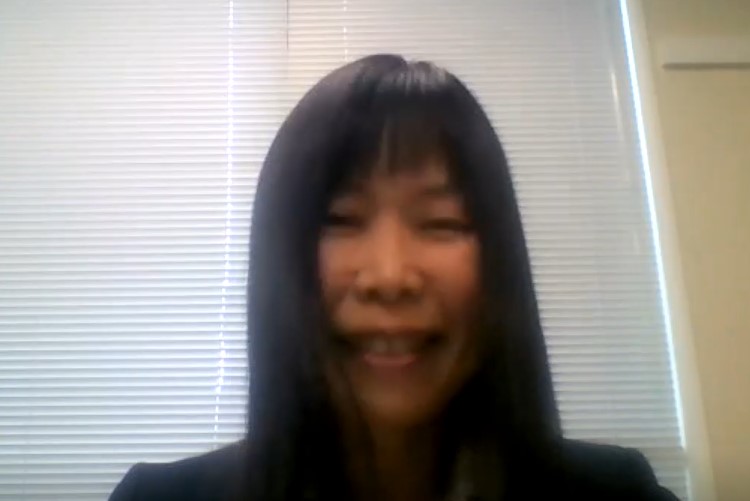SAカレッジ22年度 コースⅡ 第2回月例会質疑セッション 参加者の声
村田 裕之 特任教授「シニア市場とスマート・エイジング・ビジネス② 」
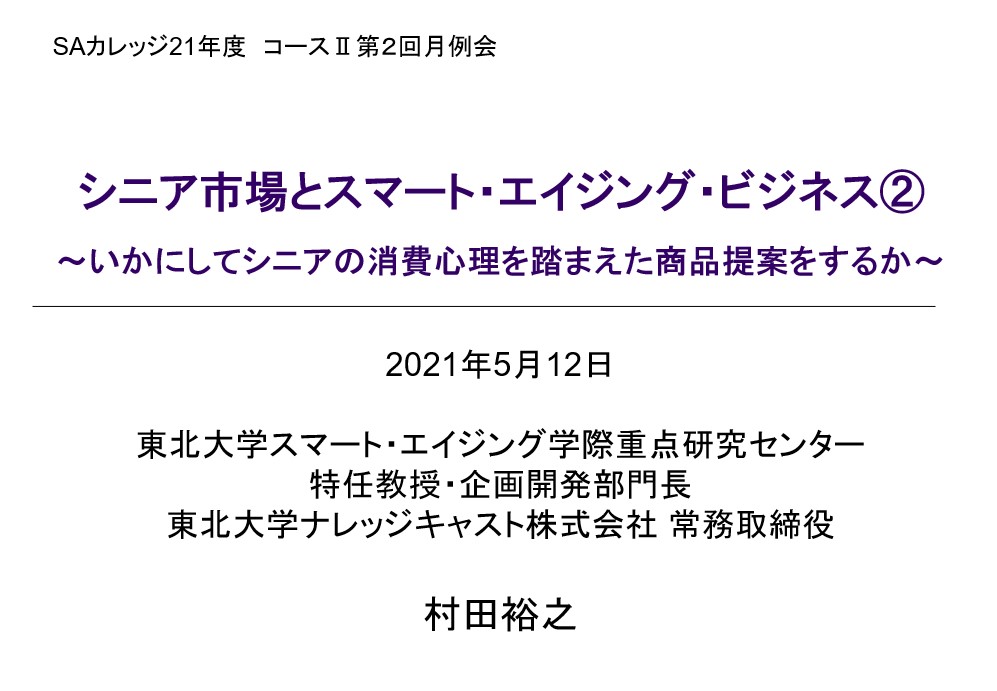
2022年5月17日、SAカレッジ22年度コースⅡ第2回月例会 質疑セッションが開催されました。
講師は、スマート・エイジング学際重点研究センター企画開発部門長、東北大学ナレッジキャスト常務取締役、村田 裕之(むらた ひろゆき)特任教授。講義テーマは「シニア市場とスマート・エイジング・ビジネス② いかにしてシニアの消費心理を踏まえた商品提案をするか?」でした。
セッションの最後に村田先生から「このように、いろんな立場の人が質問すると密度が上がって面白い学びの場になると考える。講義を聞いて質問を練ってもらい、質疑セッションでも足りなければリポートに質問書いていただきたい。
コロナ禍における質問があったが、私も重要なファクターだと思っている。シニアビジネスは5つのファクターあるが、コロナは5番目の社会的ファクター。しばらくつづきそうだが、波が来たときはシェルターにおさまって家での消費が増え、波がおさまると解放型の消費が広がるだろう。このサイクルの波がどうくるかを考えると事業ロス減るのではないか」というお言葉がありました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。