SAC東京4期コースⅡ第6回月例会 参加者の声
10月25日、SAC東京コースⅡ第6回月例会 参加者の声
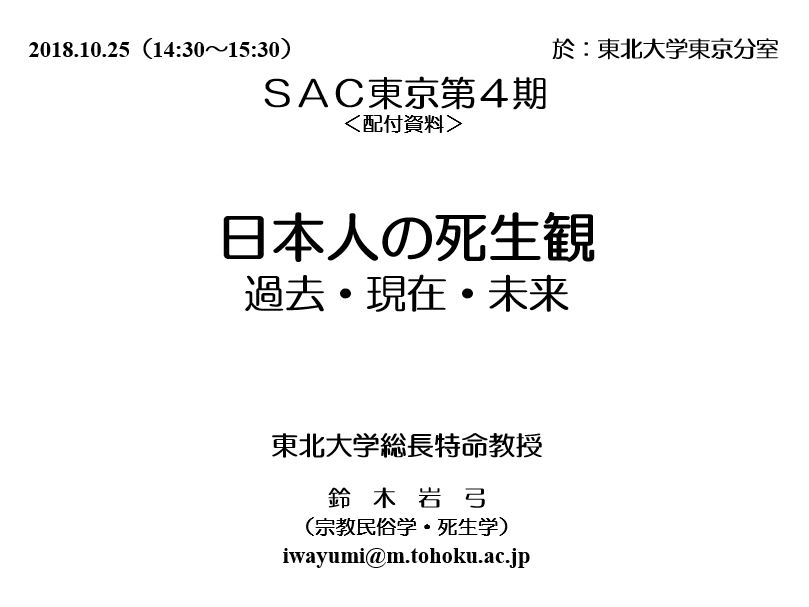
講師は宗教民俗学・死生学専門の鈴木 岩弓(すずき いわゆみ)総長特命教授・名誉教授。講義テーマは「日本人の死生観 過去・現在・未来」でした。
超高齢社会における看護・介護やシニアビジネスを行う上で、私たち日本人の「死生観」がどのようなものであるかを理解することが不可欠です。
「死生観」というのは、観念の問題であるため目で見ることができません。従って、ここでは観念に基づいて執り行われる行為、特に死者に対してなされる「葬送習俗」をお話しすることで死生観のイメージを深めました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
ご意見・ご感想(抜粋)
講義が参考になった理由は?
- 土葬について。日本が近代化するとともに衛生上、そして埋葬手順などの背景から日本ではすでに土葬は行われていない、という説明を海外に対して行ってきたことが誤りということがわかり、助かった。
- 死生観について地域性があること、信仰と宗教・宗派は別ものであること、が新たな気づきとなりました。
- 普段ではあまり考えない内容、今まで当たり前であったと思っていた儀礼などについて改めて歴史・背景を通じて学ぶことができとても興味深い内容でした。
- 蘊蓄を傾けた講義内容で、普段は深く考えることのないテーマについて、深く考えるきっかけをいただきました。ところどころで披露されるトリビアも参考になりました。
- 生死感という通常考えが及ばない事象を考える機会ができたことがよかった
- 超高齢化社会を迎えるにあたり、墓や供養の永続性も不十分になる可能性が大いにあるなか、儀礼の必要性や意味について深く考える機会になった。
- 「日本人の死生観」について、体系的なお話を伺うことができ、参考になりました。以前デスカフェに参加した際、自分の中でなんとなくタブー視していたが、「死について考えることは後ろ向きなことではなく、生を考えることであり、前向きなことなんだ」と感じました。これから多死社会を迎えるに当たり、もっと死について考え語る=いかに生き死を迎えるかを考える機会が増えるべきと感じました。
- 重いテーマではないか、との事前イメージを覆す講義を拝聴することができました。生の儀礼、死の儀礼の時期に共通点があるなど、初めて気づくことが多くもっと聞きたい内容でした。
- 最近、私は母を亡くしたばかりでして、人の死について直面したばかりであったこともあり、大変考えさせられる機会でした。特に、儀礼や葬送習俗について、世界だけではなく日本の中でも違いがあることに驚きました。
- 死生観についてあまり意識せずにいたので考えるきっかけになった。宗教と信仰の考えも勉強になった。
- 暗い内容になりがちな「死」に関するテーマを地域や社会環境の変化も交えながら分かりやすく講義していただけたため。
- 自らの知識習得には参考になったが、ビジネスに繋げるという観点からは、参考にしにくいと感じました。
- 福士や介護の日常の仕事の先には、必ずより良い「死」が避けて通れない課題としてあります。当社でもエンディングケアとどの様にかかわっていくか、或いはどの様に人様に伝えていくのかは日々迷うところです。今回ご講義いただいたことで、「看取りとは単に見送ることではなく、その人らしく生ききることを見守ること」と学びました。このことは、大いに今後の私共の取り組みに勇気を与える指針となります。個人的には、日本人独特の文化のなかで「死」を民俗学の視点から考察する、ということに大変興味を持ちました。遠野物語のような世界観は多分、日本的な生死感に触れる場ではないのではないでしょうか?東北地方のお話しが多い中でそのようなことを考えておりました。幼い子供たちに「生死感」を伝え養うには日本昔話の読み聞かせが良いのかもしれない、と先生のお話しを聞きながら思っておりました。機会がありましたら、是非もっと沢山の講義を伺いたいと思います。ありがとうございました。
- ライフスタイルを考えるときに、最終的に人の死生観にたどり着く。その部分の疑問や課題が見えてきた気がいたします。
- 死生観について考えることは普段なく、講義内容は興味深かったが、ビジネスへどのようにつなげるかという観点では難しいように感じた。
- 死を見据えた生き方を考える上で,「地域性」というところはひとつのキーワードのように思え,地域性の違いを念頭に人生最期の〇〇の提供について考えていきたいと思いました。一時間では足りず,もっと多くのお話を聞いてみたいと思いました。
- 私は岩手出身であり、葬送儀礼が他の地域と違うことを知らなかった。
- 死生観の変遷、教誨師、臨床宗教士、実務に生かせそうな、取り入れられそうな内容であった。
- 普段、聞くことの出来ない「死生観」について成り立ち、宗教との関係性、儀礼など様々な角度からお話が伺え参考になりました。
- 意識が希薄だった死生観について参考になる話が多かったです。
- 講義内容はわかりやすくて興味深かったが、弊社のビジネスにつながるヒントは現時点で得られていないため
アイスブレイクが有用だった理由は?
- 講義内容を何げなく聞いた直後に当日の講義内容の中で価値がある情報に注意を喚起してもらえるから。
- 自分では気づかなかった観点からの質問・回答が聞けました。
- 細かい部分まで掘り下げて頂き自分でも気づいていなかった点について深堀することができとても参考になりました。
- 講義後に、頭をニュートラルにするのに役立ちました。
- 教誨の話が大変ためになった
- 論点や着眼点を整理し際立たせて頂きました。
- 村田先生の鋭い質問に、鈴木先生がユーモアを交えた言葉で正直に返す展開が楽しかったです。
- 日本人の生死観の中で、儀礼について多く質問されましたが、私も由来を知りたく思っておりました。
- 疑問に思った内容を聞いてくださったので内容がよく理解できた。
- 講義の中で、自分の頭の中では考えていなかった点についてご質問いただけたため。
- 特筆すべきことはなく、毎回毎回、要点をわかりやすく、解説等を行っていただけるため。
- 的を得た質問が投げかけられたことで、漠然としていた思考をとりまとめるのに役に立ちました。
- アイスブレイクとしては、参加者が自分事として考えたり意見を言ったりするまでには至っていないのではないかと思いました。
- 理解を深めるのに有用でした。
- ビジネスとして展開を考えた場合に、非常に難しいテーマだった。
- 宗教と信仰の違いなどにフォーカスできたから。
- いつも内容の確認を頂け、前提を統一できるので。
- 講義内容を適切に纏めていただいた上でより深い理解に繋がる質問などがあり有用でした。
- 講義中の疑問のいくつかを聞いていただけたため
パネルトークが有用だった理由は?
- 介護事業に携わっている参加者から現場の声を聴くことができたことは有益。
- 今回パネリストとして参加させていただき、大変貴重な経験となりました。高齢者ビジネスには、死生観をはじめとした「心のケア」の要素が必要であることを、改めて実感する良い機会となりました。ありがとうございました。
- それぞれの分野からのご意見をうかがうことができ参考になりました。特に「教誨師」については興味深く、何かビジネスにつなげられる可能性があるのか考えるきっかけになりました。
- 分野が違う方々のご意見を伺えました。
- 臨死の経験のある方のお話はやはり参考になった
- それぞれの立場からのご経験を伺うことができ、自分が経験することはないと意味で参考になりました。
- 今回はパネリストの大役を仰せつかり緊張しましたが、鈴木先生、小川さんのリードにお任せすることで無事に終了しました。ありがとうございます。
- 風土、宗教、信仰により独自の死生観があり、それも時代と共に変化していく。お墓や僧侶の需要、安楽死まで様々な疑問がありとても参考になりました。教誨師についても、介護の現場支援のヒントがあるように思います。
- きょうかいしや傾聴ボランティアの話など今後の参考になりました。
- 適切な表現とは言えないかもしれませんが、今回のパネリストの方々は、仕事を通じ死に関わることが、自分よりは多いはずです。そのため、質問や意見が重みがある一方で、温かさも感じられるものでした。
- 立場の違いはありましたが、どなたも同じようなことを課題だと感じていられるのだと知りました。
- 現場での死生観への対峙の仕方に業界ごとの違いや苦労があることがわかりました。
- パネリストの方が代表して質問をしていただいたことで、講義とは違った観点で先生から解説をいただけたため。
- 死に向き合う仕事をされている方からの質問は,先生のお話をさらに引き出していただき大変参考になりました。
- 将来お墓はなくなるのか? というテーマにおいて、散骨をした人でも墓を作っている、とかすべてがバーチャルになるかは疑問だ、といった意見を聞いて、お墓というものに対して、まだまだ新しい展開があるように感じた。
- 生命保険と死生観については考えてこなかった。新しい視点をいただけた。
- 各会社のビジネス上の課題、特に保険ビジネスの課題感を聞けた。
- パネリスト各人の専門分野から質問があったため興味深い内容となっており参考になりました。
- 当社のようなメーカーの場合は直接ビジネスにつながるアイディアはなかなか生みづらいかもしれませんが、保険会社さんや高齢者向け住宅会社さんの視点からの質問は新たな視野となりました。
