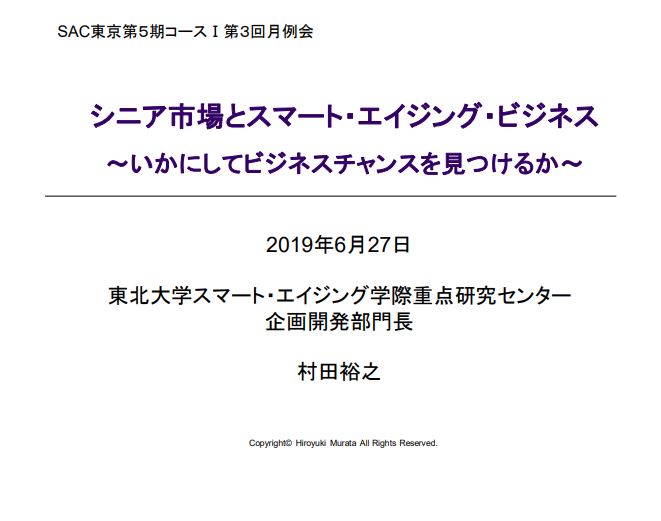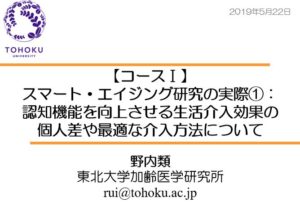第2回産学連携フォーラムが開催されました
 昨日は東北大学スマート・エイジング・カレッジ(SAC)東京の今年度の第2回産学連携フォーラムを開催しました。
昨日は東北大学スマート・エイジング・カレッジ(SAC)東京の今年度の第2回産学連携フォーラムを開催しました。
目的は、東北大学における研究最前線を参加企業の皆さんにお伝えすることと、参加企業と大学・参加企業同士の連携・提携のきっかけ作りです。
前者では歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター 異分野融合部門長の金髙弘恭先生から最新の活動状況をお話頂きました。後者ではSAC東京参加企業6社からピッチ(ショートプレゼンテーション)を頂き、その後8つのグループに分かれてグループトークと質疑を行いました。
こうした場のメリットは、大学の多くの部門の研究活動と、多くの異業種企業の商品・サービスとが、市場のなかで互いにどのように位置づけられるかが「全体的に俯瞰」でき、具体的な提携のイメージが湧きやすいことです。

これは例えば、ある分野に関する書籍を5、6冊一気に速読すると、その分野の動向・全体像が見えてくるのと似ています。
「何だ、それならテレビ会議とか、SNSでもできるじゃないか」と思われるかもしれません。
結論から言うと、できません。その理由は、60名近い人たちが、同じ場にいて、互いに顔を突き合わして意見交換する「即興性の高い、生のコミュニケーション」だからです。
さらに、参加者全員が「スマート・エイジング」というコンセプトのもと、ビジネスを創出するという「共通の目的意識」があることも重要です。
異なる者同士が円滑に連携するには、何が必要なのかを改めて考える機会となりました。
(文責:SAC東京事務局)
 |
 |
 |
 |
 |
 |