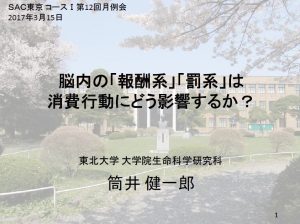2月3日放送 NHK総合「チコちゃんに叱られる!」に瀧 靖之 教授が出演されました
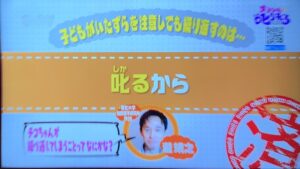 SAカレッジの講師でもあり、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長、瀧 靖之(たき やすゆき)教授が、2月3日放送 NHK総合「チコちゃんに叱られる!」に出演されていました。
SAカレッジの講師でもあり、加齢医学研究所 機能画像医学研究分野、スマート・エイジング学際重点研究センター 副センター長、瀧 靖之(たき やすゆき)教授が、2月3日放送 NHK総合「チコちゃんに叱られる!」に出演されていました。
ご自身も10歳のお子様がいらっしゃる瀧先生。「子どもがいたずらを注意されても繰り返すのはなぜ?」というチコちゃんの疑問に、分かりやすく解説されていました。
子どもがいたずらを注意しても繰り返すのは、いたずらをすることで、親が反応すると想像し、興味を持ってもらえたことで(怒ってはいますが)、ドーパミンが出て脳内は気持のよい状態になっている、ということでした。叱られるのを楽しんでいる様子なのは、理性を司る前頭葉が未発達のためブレーキがきかない状態であり、脳内作用によるものであり、本人の性格によるものではないそう。
ですから、子どものいたずらには過剰に反応せず、どうして困るのかを冷静に説明することで、自然にいたずらはなくなっていくというようなお話でした。



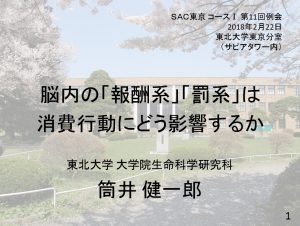 2月22日、SAC東京3期 第11回月例会が開催されました。講師は、東北大学 生命科学研究科 脳情報処理分野の 筒井健一郎教授。講義テーマは、「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。
2月22日、SAC東京3期 第11回月例会が開催されました。講師は、東北大学 生命科学研究科 脳情報処理分野の 筒井健一郎教授。講義テーマは、「脳内の「報酬系」「罰系」は消費行動にどう影響するか?」でした。