SAカレッジ21年度 コースⅡ第1回月例会 参加者の声
川島 隆太 教授「脳科学を応用して新産業を創成する②」
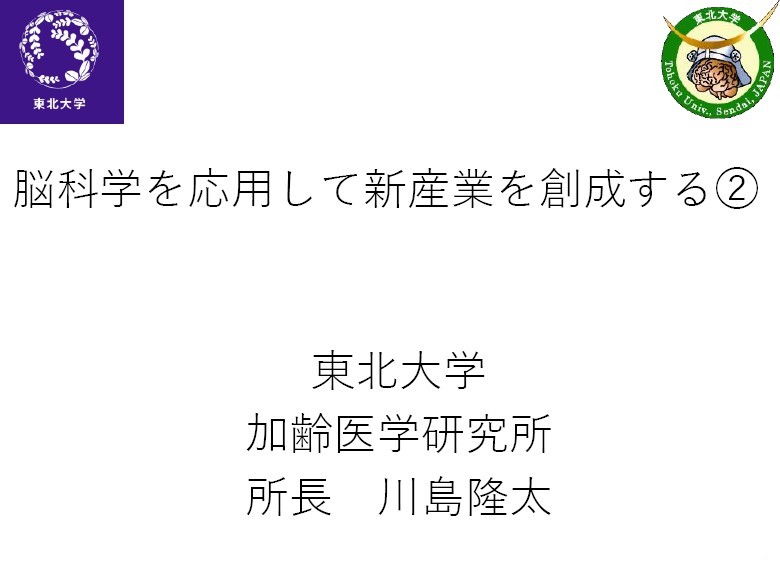 4月7日、SAカレッジ21年度 第1回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所所長、スマート・エイジング学際重点研究センター長、東北大学ナレッジキャスト株式会社取締役 川島 隆太(かわしま りゅうた)教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する②」でした。
4月7日、SAカレッジ21年度 第1回月例会開催されました。講師は、加齢医学研究所所長、スマート・エイジング学際重点研究センター長、東北大学ナレッジキャスト株式会社取締役 川島 隆太(かわしま りゅうた)教授。講義テーマは「脳科学を応用して新産業を創成する②」でした。
21年度最初のコースⅡ月例会では、川島教授による脳科学の産業応用の最新動向でした。
まず、様々な脳機能イメージング装置で何ができるかの基礎知識を次の項目で確認しました。
-
- 脳機能イメージング装置の違いは?
- ブレインマッピングとは?
- デコーディングとは?
- ニューロ・マーケティングとは?
- コミュニケーションの質の定量化
そのうえで、最新応用事例として世界中の経営者が関心を持っている「マインドフルネス瞑想」を取り上げ、瞑想アプリの作成と社会実装の詳細をお話ししていただきました。
最後に「バーチャルリアリティによる疑似運動」と脳活動の関係、「高齢者の安全運転能力向上脳トレ」など最新事例を通じて、脳科学からビジネスを生み出す際の勘所を伝えていただきました。脳機能イメージング研究の第一人者が脳科学と社会実装を余すことなく語る貴重な機会となりました。
参加された皆様からいただいたご意見やご感想を掲載します。
ご意見・ご感想(抜粋)
講義が参考になった理由は?
- 後半で、教えていただいた見識がビジネスに結びつくことが具体的にイメージできました。初めてこのような場に参加させていただきましたが、多くの企業の方々がこのような場でビジネスチャンスや組織内での企画提案されるのだなと感心致しました。
- 脳血流の測定技術とその応用について整理することができた。
- 脳科学に関してビジネスと結び付けた具体例をいくつも出して頂き、今後弊社で事業化を考える上で参考になった。
- つい一括りに「脳波測定」と捉えてしまっていたが、用途に応じて適切な項目を適切な方法で測定しないといけないというのは新たな気づきになった。Web会議での脳同調が生じない実験や、没入型VRで実際に運動したときのような身体変化が起こる実験は非常に興味深かった。Webmtgが定着し、5Gも拡がっていく中で、新たなサービス開発のタネを考えるきっかけとなった。
- 脳機能イメージングを脳波として一括りに考えてしまっていたが、それぞれの簡単な原理や特徴について理解することができた。また、デフォルトモードネットワークの活動計測による集中力の評価は非常に興味深かった。
- スライド17の「ツボの電気刺激箇所と、脳の中の小人」が一致した実験結果については、非常に興味深いものを感じました。東洋医学を、脳科学的見地からとらえたエビデンスについて、もっと広く知られると、東洋医学も変わっていくかもしれないと思いました。
- 没入型VRを使用することで、脳をだまして認知機能・自律神経機能の向上をはかることができるということは、年齢や健康状態を問わず、今回のコロナを皮切りに増加した運動不足の人たちにも効果があると感じました。
- ニューロマーケティングなど、先端の産学連携事案をお伺いできてよかったです。
- 脳の活動を可視化を、マーケティングに活かす、コミュニケーションや集中力の指標にする等、社会実装の例まで聞くことができて興味深く、参考になりました。
- 脳波の理解が間違っていたので、講義を聞いて良かったです。NIRSの商業利用の可能性をお聞きできたので、今後の政策に盛り込んでみたく思っております。
- 脳トレを学生時代にかなり遊ばせて頂いていましたが、具体的に何をしようとしていたのかまでは知らなかったので大変勉強になりました。専門家でないとノイズがあるのかどうかすら判断できない分野であり、協力して事業を創り出す必要があると感じました。
- 脳のデータを活用事例に正直驚きました。ブレインマッピング(癒しの状態、好き嫌い)ニューロ・マケティング(興味の有無)コミニュケーション質:相手の気持ちがわかる(心の理論)バーチャルリアリティ:脳をだまして認知症の防止への活用世の中のよくする視点が広がりました。
- 新産業に対する事例が多く理解できた。Webコミュニケーションでは脳の同調は起きないことは驚きであった。
- 脳科学研究やその応用例を知ることができ、とても有意義でした。ニューロマーケティングが実際あれほど小型のポータブル機器でできるようになっていることも驚きできたし、VRの応用については、レジャーなどが先行しているイメージがありましたが、より幅広い分野に広がっていることを実感することができました。
- ニューロ・マーケティングや、VRのビジネス利用の可能性を知ることができた。また、コロナ禍でオンライン会議の多いシステムエンジニア職にとって、Web会話の実験等大変興味深いものだった。
- 脳血流と感情の関係について知ることができ、大変有意義でした。
- 昨年度も受講させていただきましたが、研究内容がアップデートされており、とても興味深く拝聴させていただきました。
- 「コミュニケーションの質の定量化」について、現在担当している業務で必要としていることだったので。
- 脳の状態を把握する方法について学ぶことができ、今後自社素材を評価する際の参考になった。
- 脳波ではなく、fMRIでの血流信号や、NIRSでの脳表面での血流信号の解析から、マッピング、デコーディング、ニューロ・マーケティング、コミュニケーション状態解析、迷走状態解析等、今後のビジネスのネタとして非常に面白い話をきけた。人の感情などの数値化が可能な未来が待っているのをおもしろいと思う反面、ミシェル・フーコーが提唱したような、生権力、のように、得られた数値をもとに人間の優劣を決めさせてしまうような動きにならないよう、サービスとしてはどこまでを明示的にユーザーに提示するか、は慎重に決めていかなければ、と感じた。
- 瞑想を脳科学の観点で説明されると納得感が高く、ビジネスへの発展に活用したいと思いました。
- 脳の複雑さを知ったことと、こんなに進んだ科学技術の中で、今でもまだ解明されている脳活動の神秘さを知ることができたこと。
- 脳波、脳磁、fMRI、NIRSの流れに合点がいき、残念な実験の存在がよくわかったことと、現在の研究テーマを垣間見ることができたため。
- ニューロ・マーケティング、や瞑想アプリなど実用的な情報があった為。
- 感情や運動、瞑想との脳の関係について、こんなに解明されているのか、と勉強になりました。また今後VRの可能性が非常に大きいと感じました。
- 非常に興味深い講義で、面白かったです。実際の商品化の事例などがあり、今後のビジネスアイディアの検討に資するものになりそうです。
過去のSAC月例会 事務局レポートはこちら
過去のSAC月例会 参加者の声はこちら
SAC月例会にご興味のある方はこちら
タグ:スマート・エイジング, バーチャルリアリティ, ブレインマッピング, 川島隆太, 脳機能イメージング
